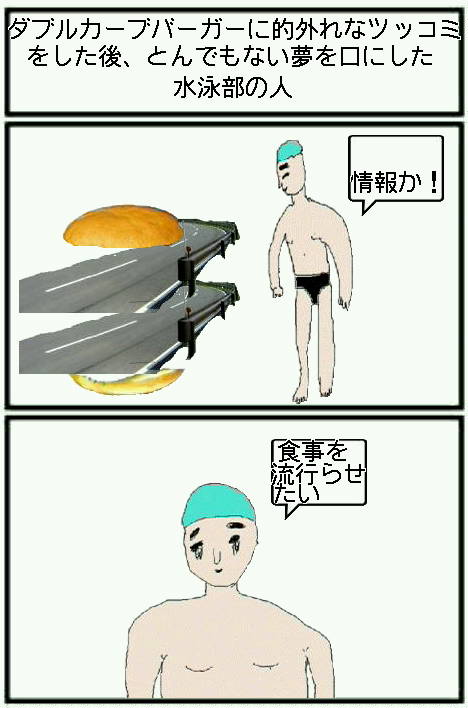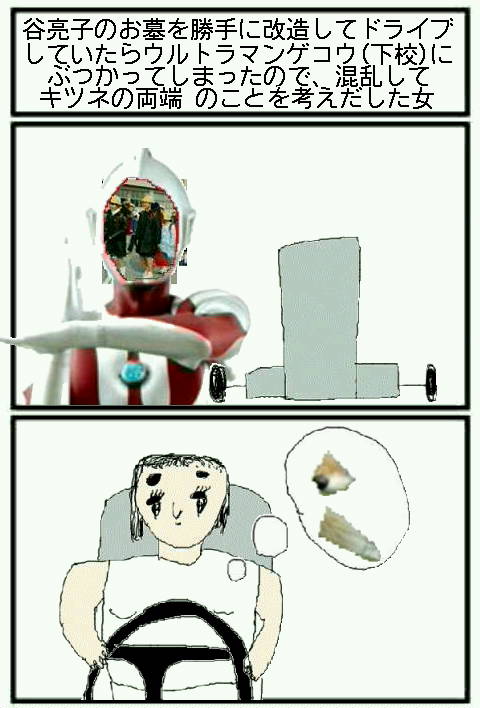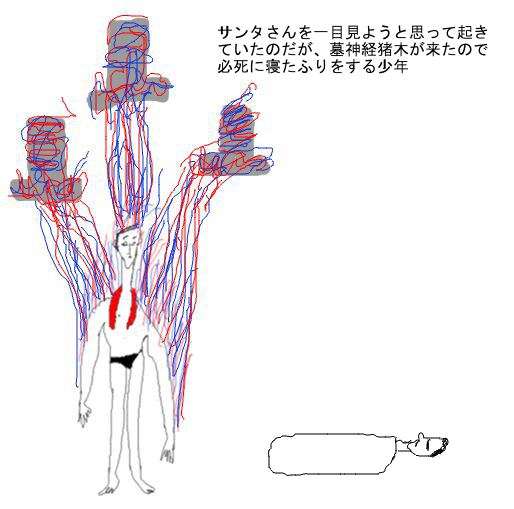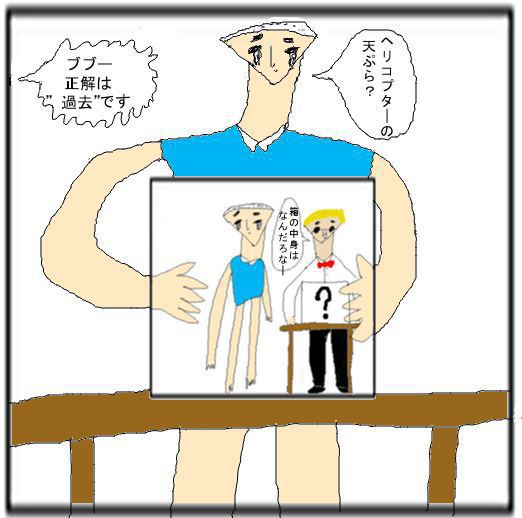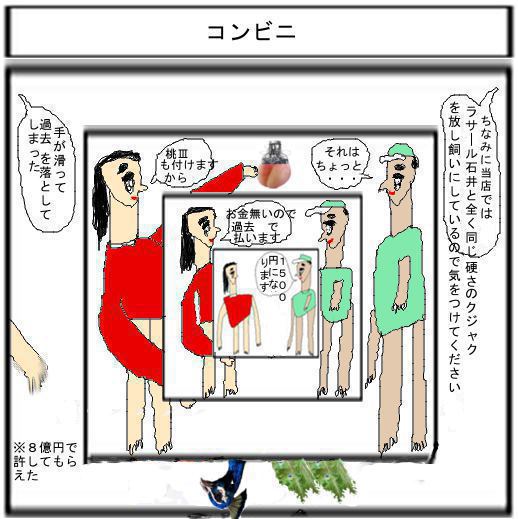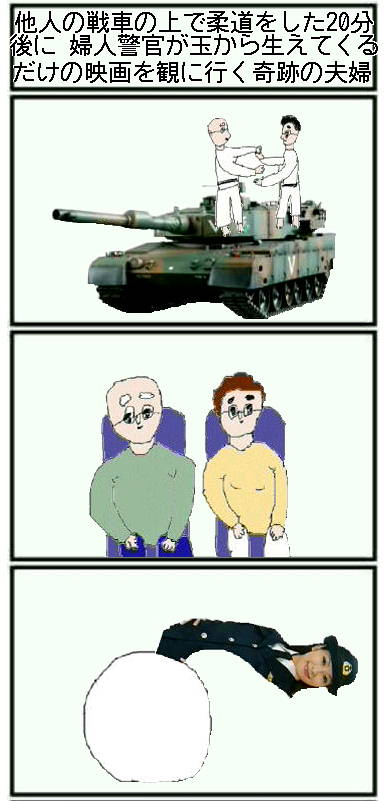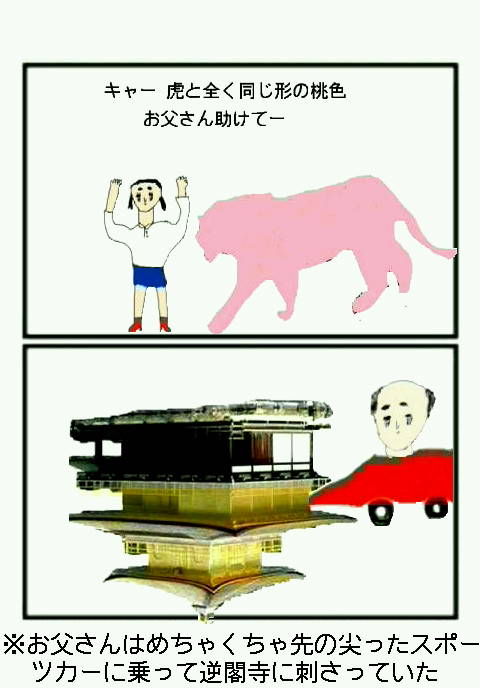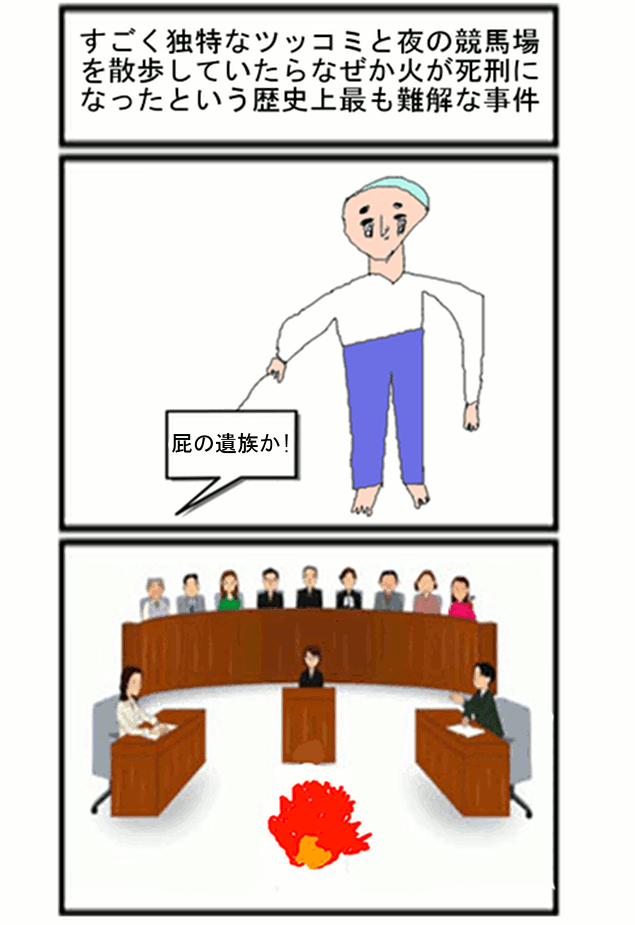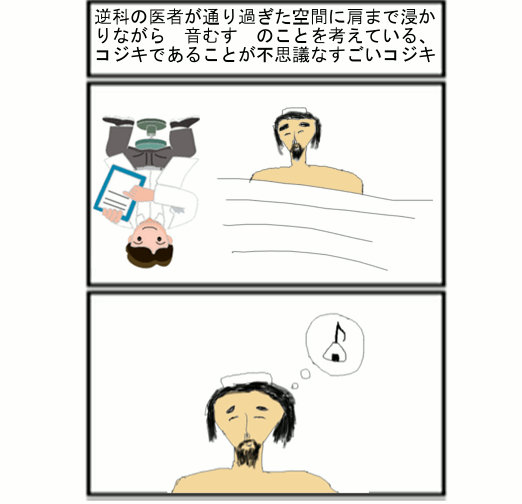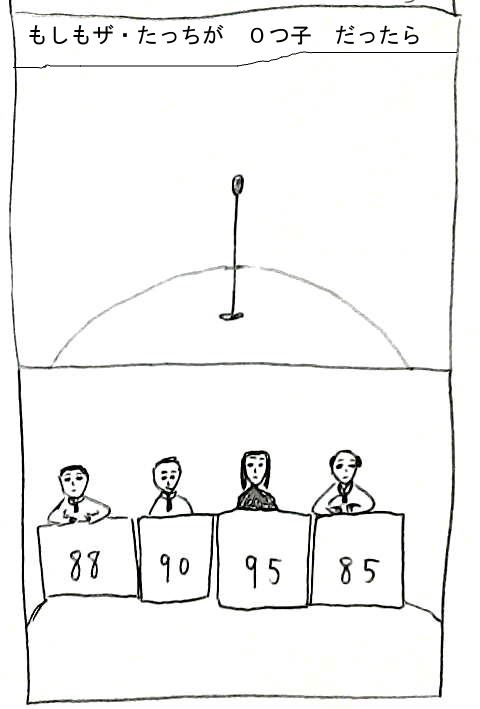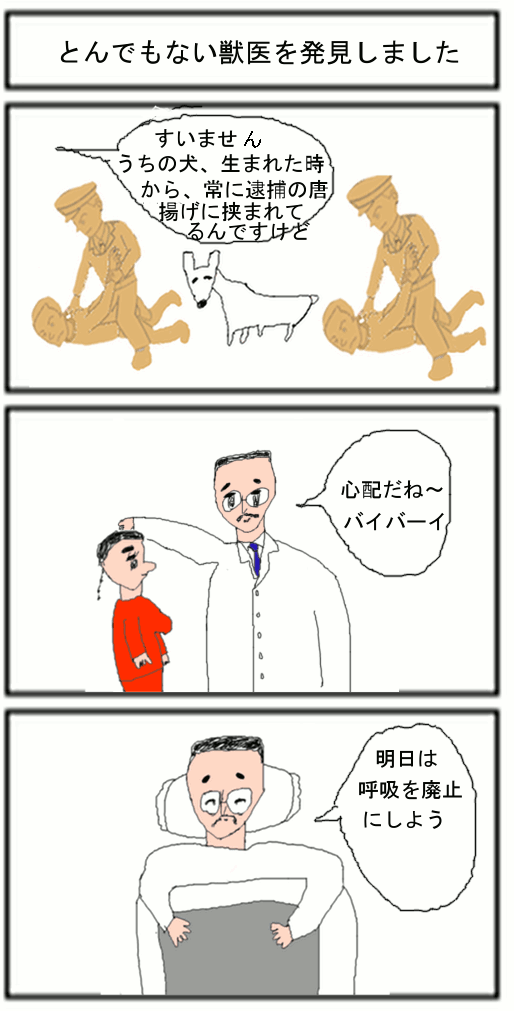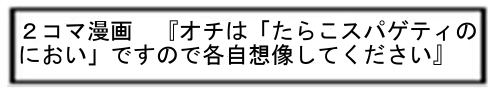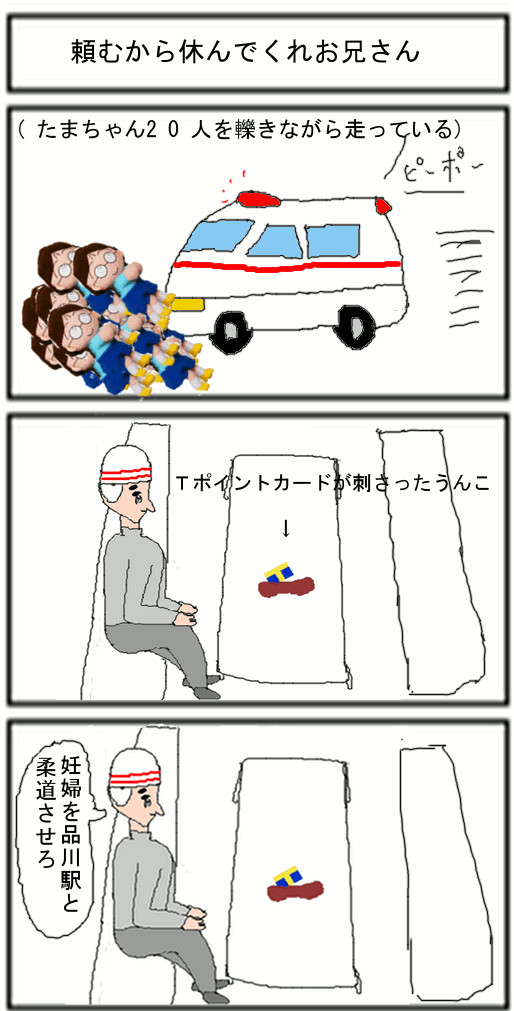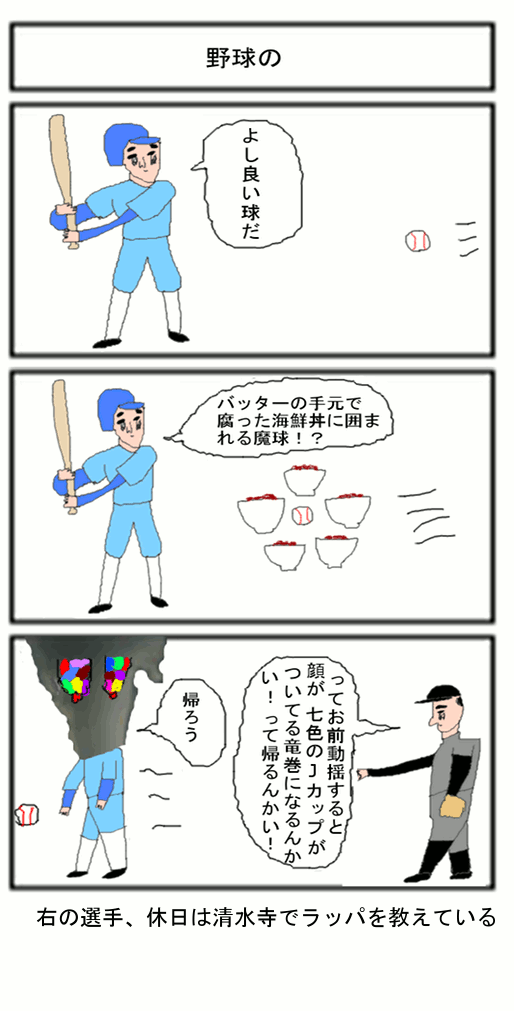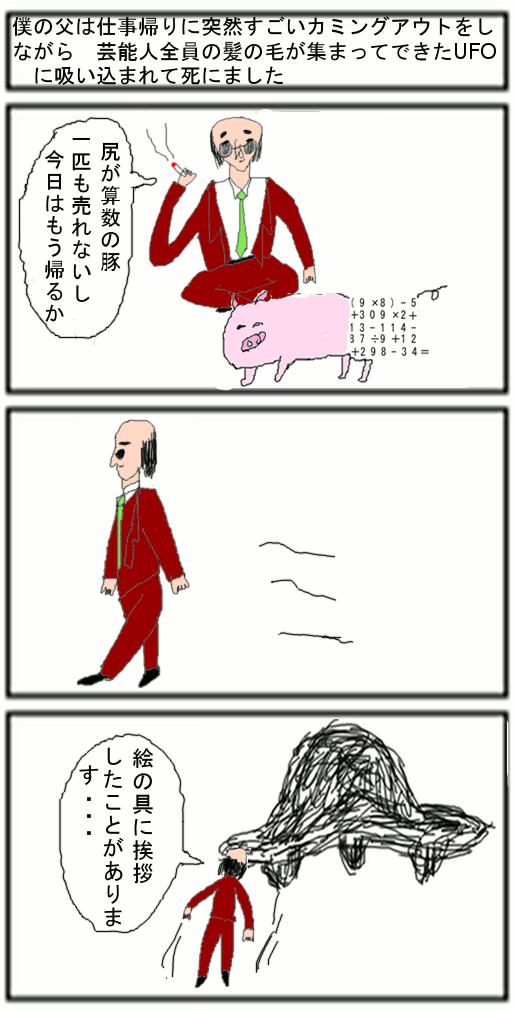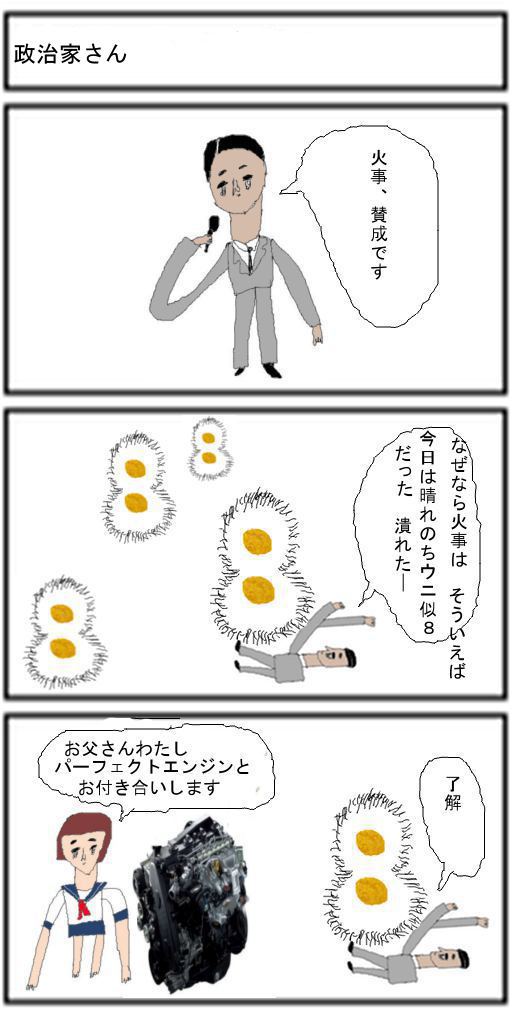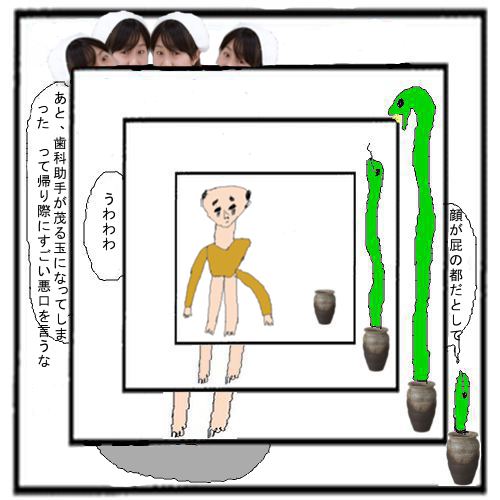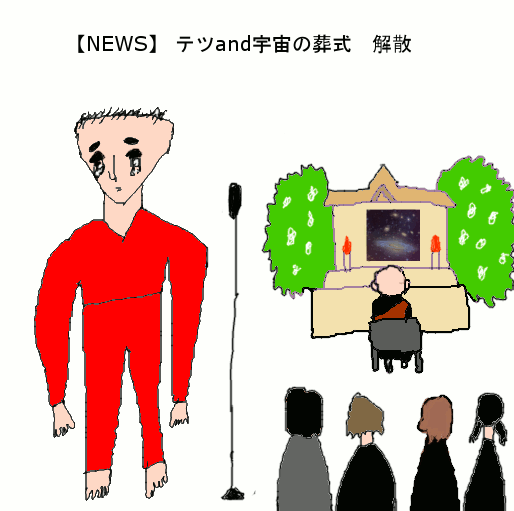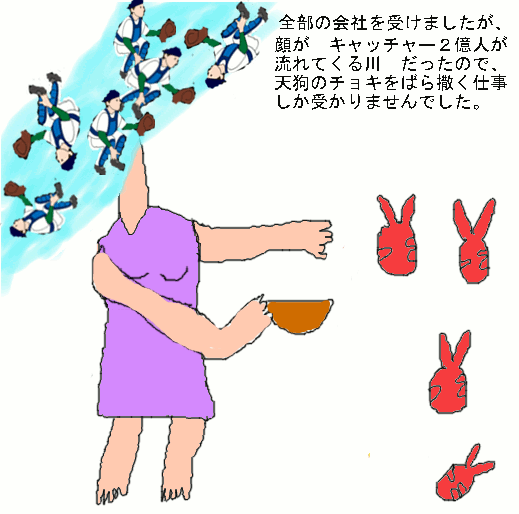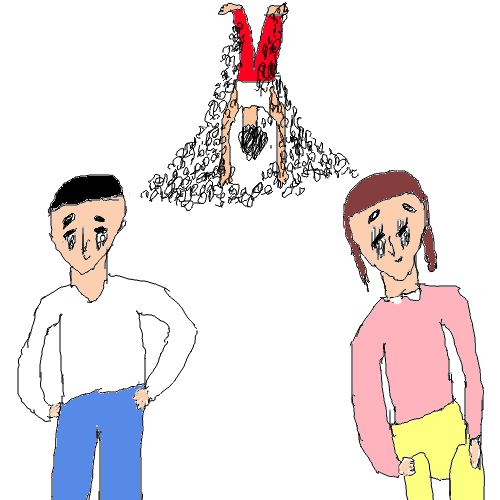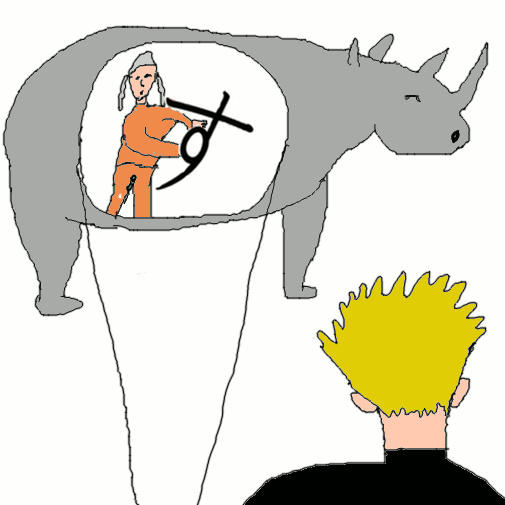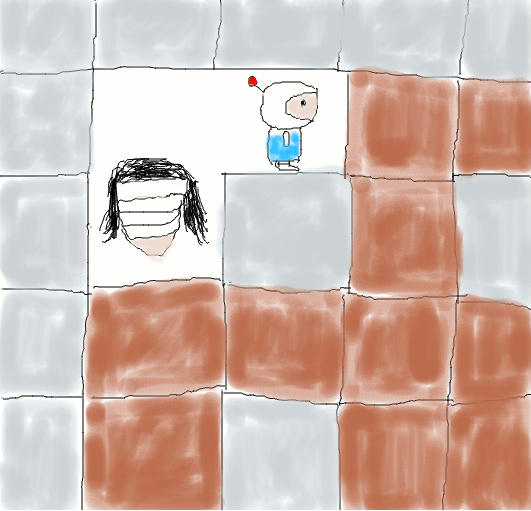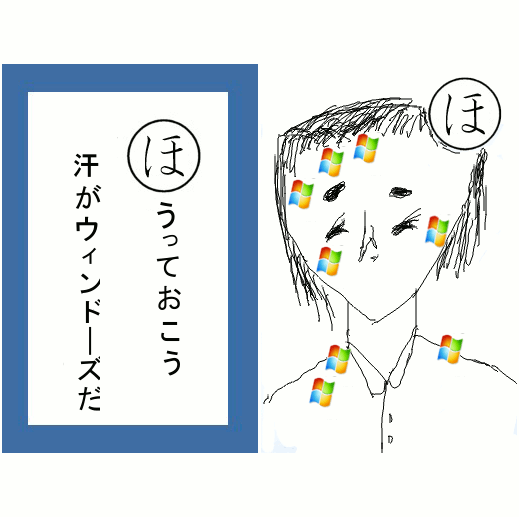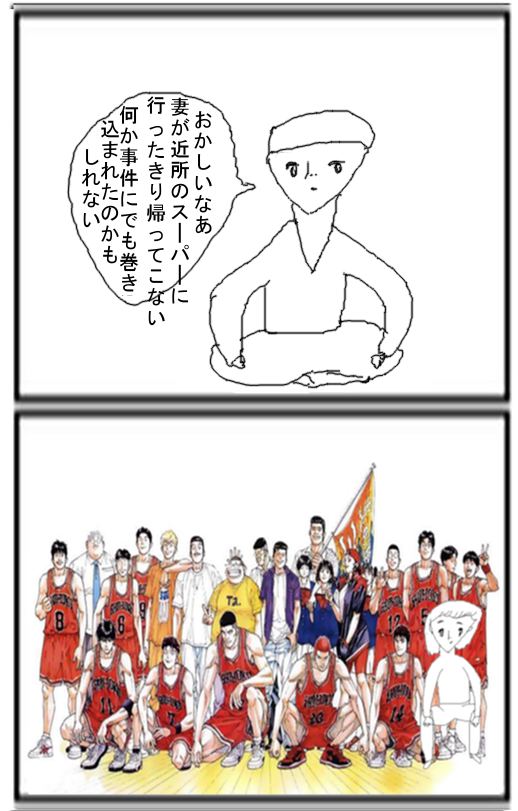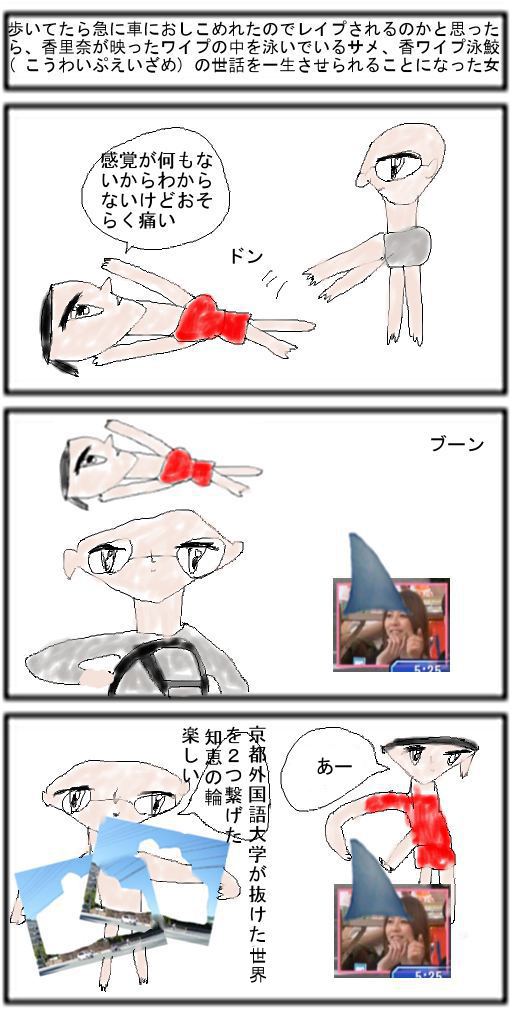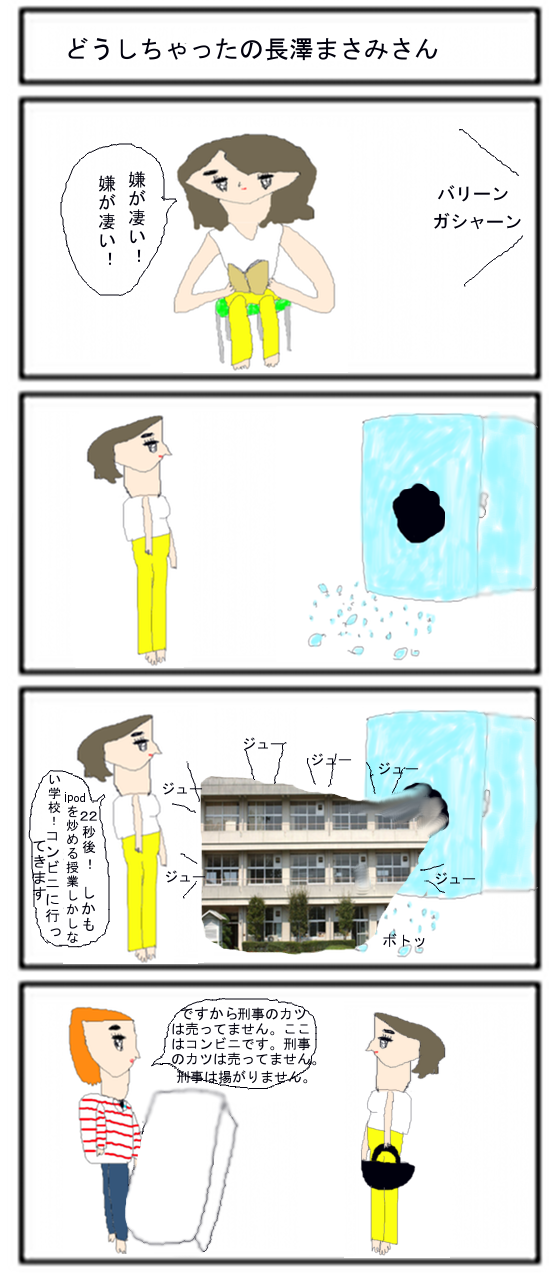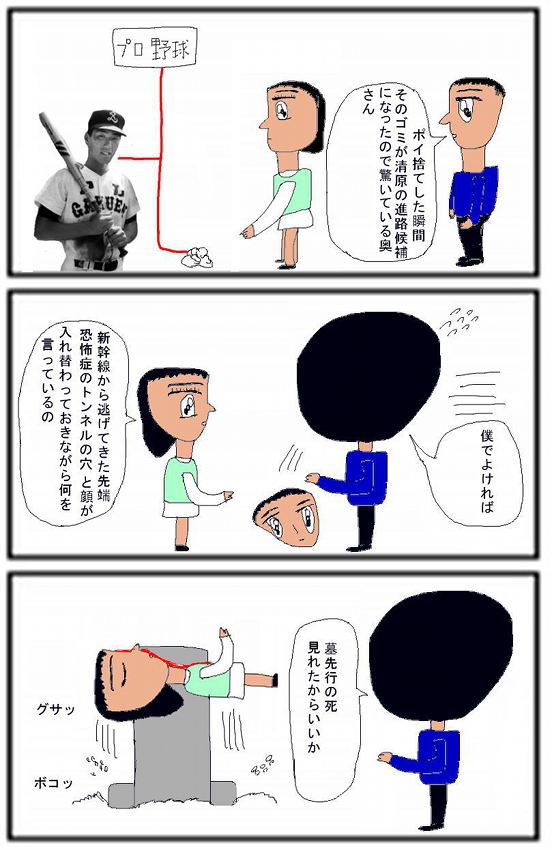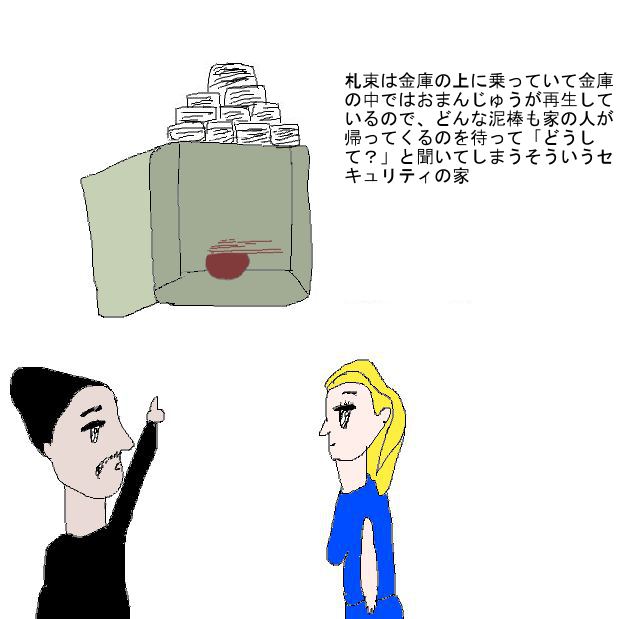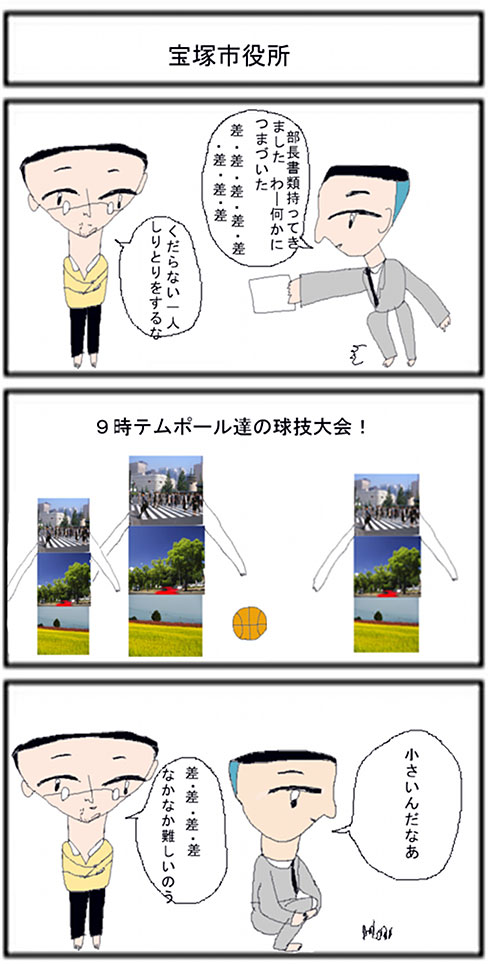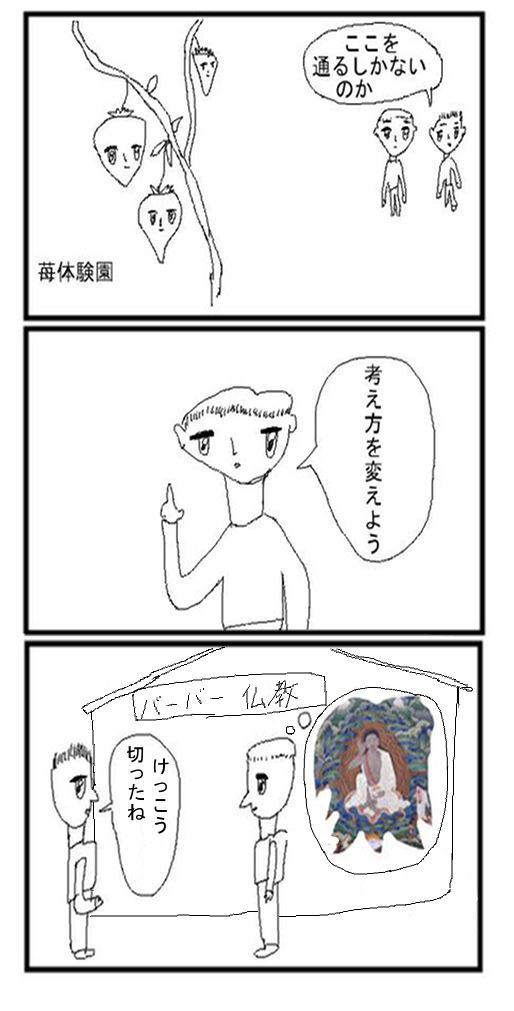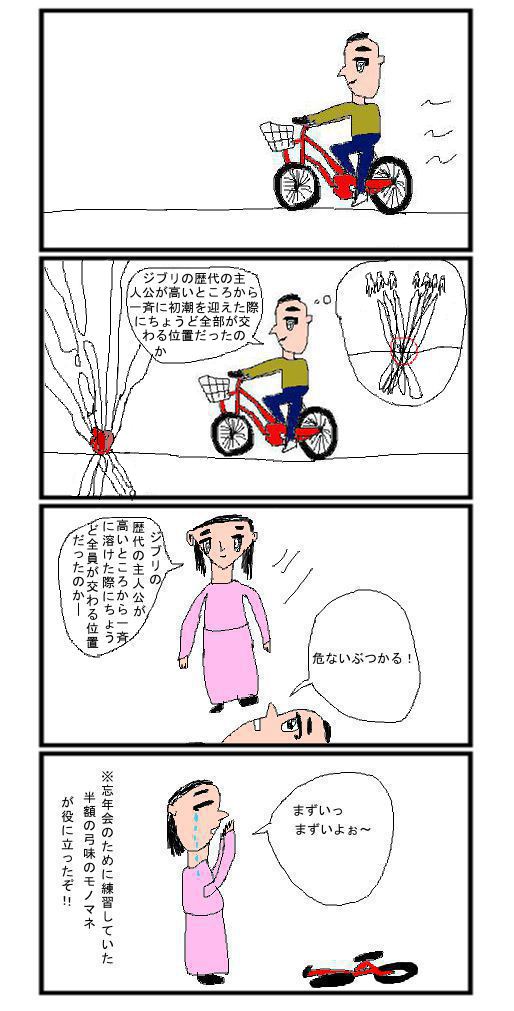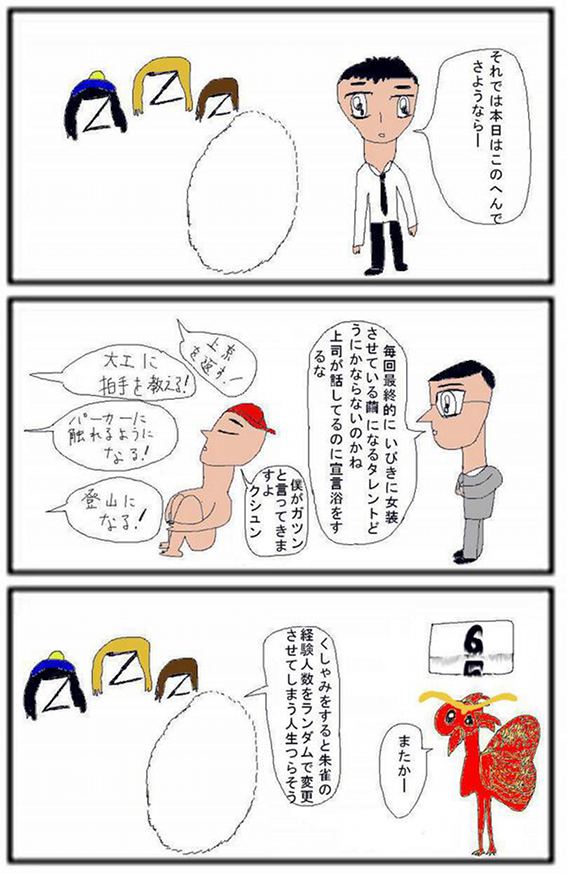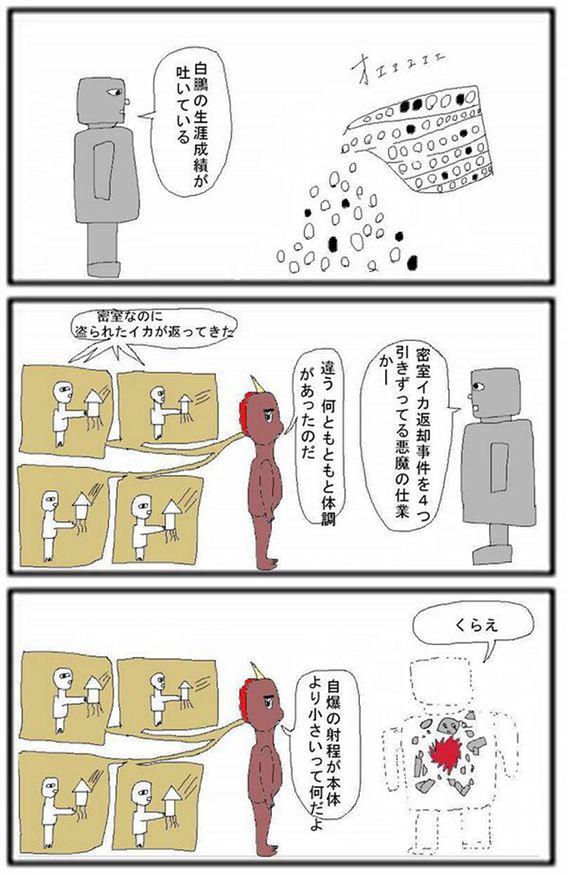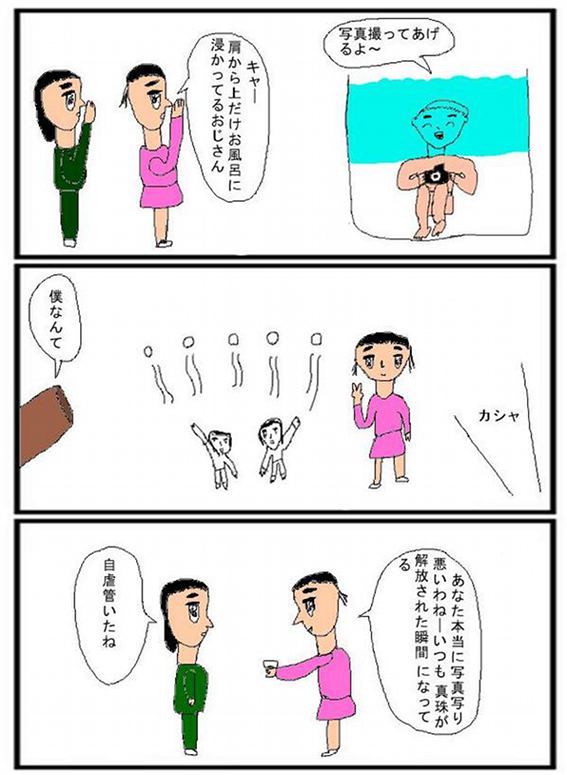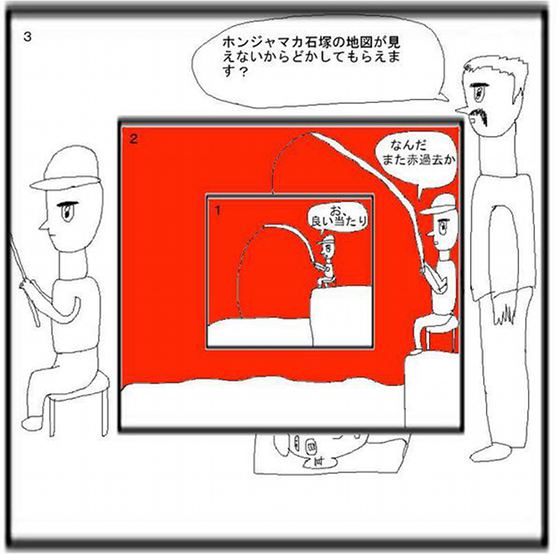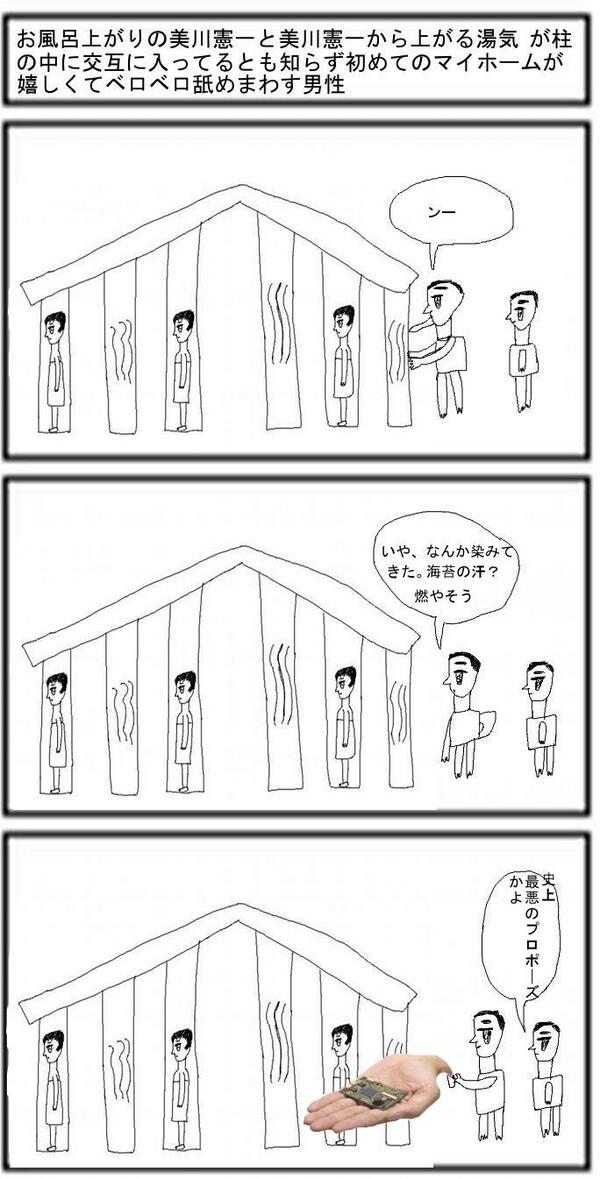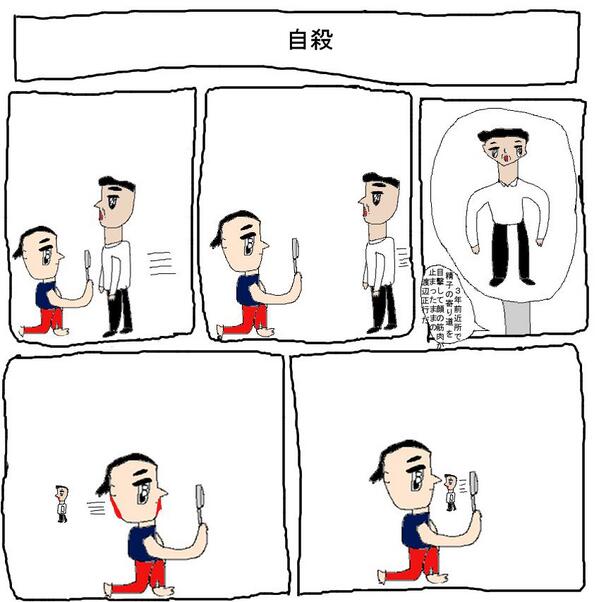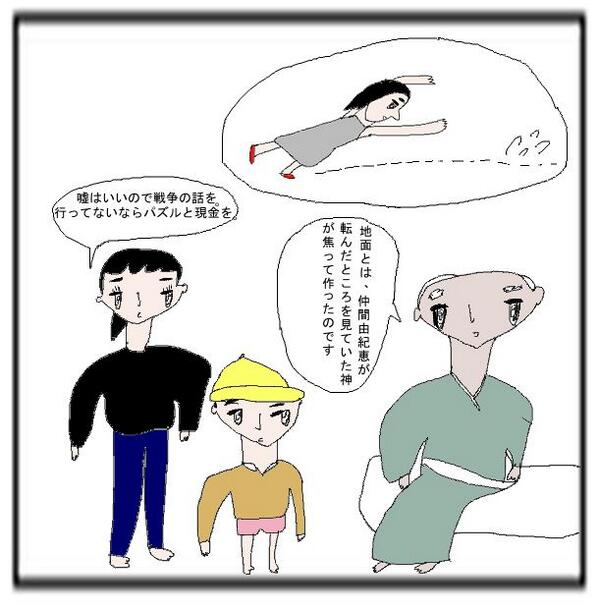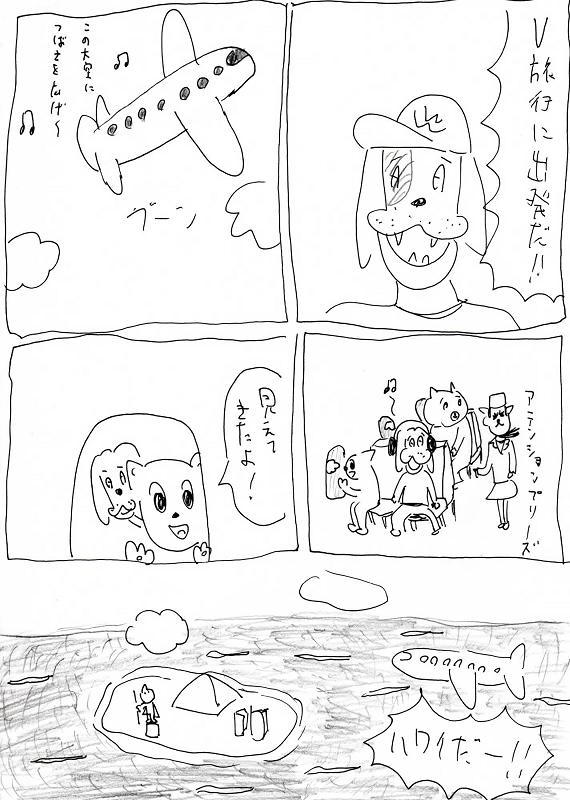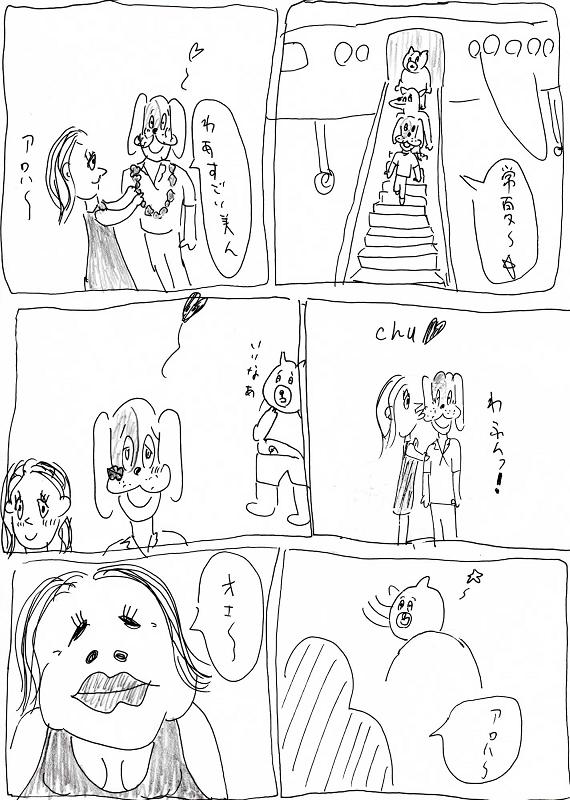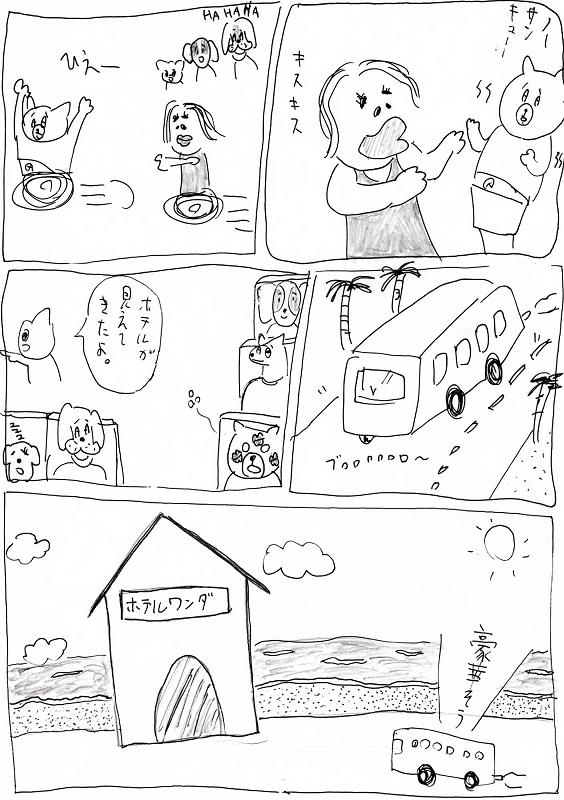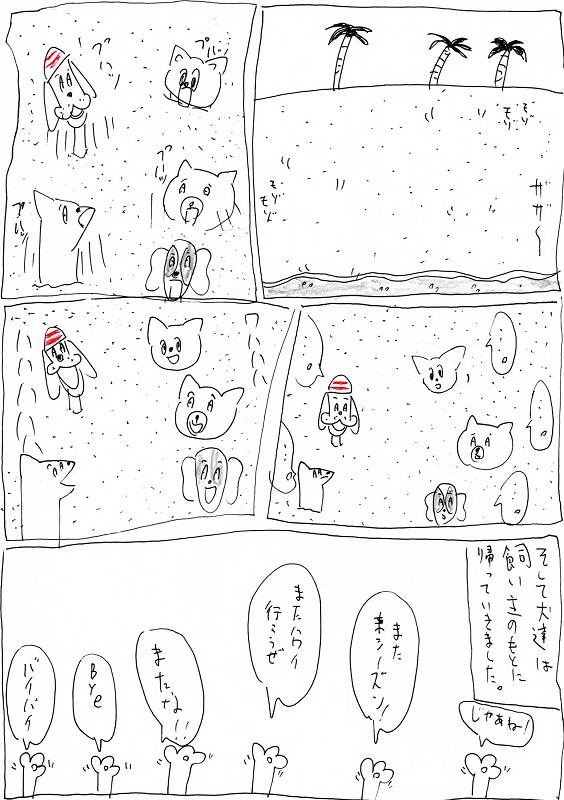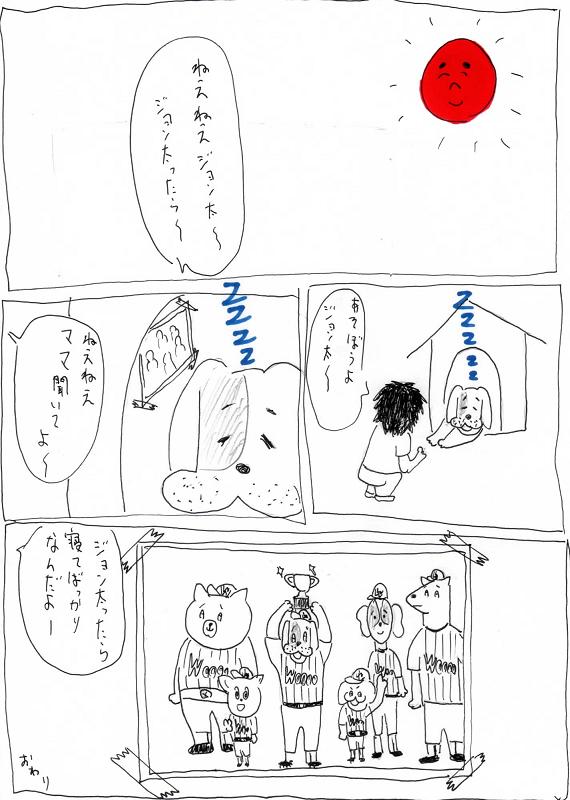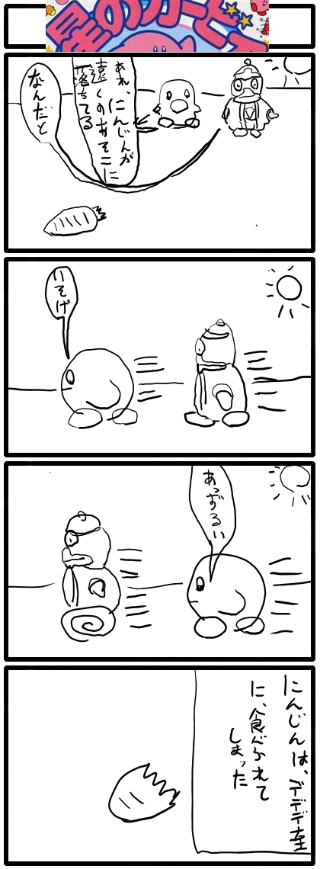私がイラッとした時の人間学
所属するゼミの先生が、大学時代の恩師にあたる偉い教授と対談するということで、私は勇んで見に行きました。四百人は入るという大教室はすでにいっぱいで、私は席に座ることができず、一番後ろで立ち見することになりました。
「須藤君、今日はおもしろい試みをしたいと思うんだ」
「なんでしょう」
「少しでもイラッとしたら、相手をぶん殴る」
「いいですね」
そこで、ドッと笑いが起こりました。お二人は口裏を合わせて、ふざけているのです。私も楽しくなって、くつくつと笑いました。こうした場で飛び出すユーモアというのが、私は大好きです。
「それでテーマなんだけど、何にしようか。僕は、『沈黙は、完全性の属性のひとつである』というカフカの言葉について話してみたいと思うんだがね」
「大学生には刺激になるでしょうね」
「相手を言い負かしたい連中ばかりだからね」
その時、先生が突然立ち上がると、教授をぶん殴りました。教授はパイプ椅子に座っていましたが、そのまま椅子ごと後ろに倒れました。マイクが飛んで床を跳ね、ドッドと音がしました。
私は唖然としました。教室に緊張が走るのがはっきりとわかりました。
「そんなことないでしょう」
先生が教授を見下ろしながらマイクを通さず直接空気を震わせた音は、一番後ろにいる私にも微かに聞き取ることができました。
教授は何も言わず、ガタガタと椅子を直して、また座りました。そして、何事もなかったように喋り始めました。
「君の方から何もなければ、それで一つ話してみようと思うよ」
「それなら僕はあれですね、カフカならば『意識に制約をもうけることは、社会的要求である。すべての徳行は個人的であり、すべての悪徳は社会的である。社会的徳行と見なされているもの、たとえば愛、無私、正義、自己犠牲などは、〈おどろくほど〉弱められた社会的悪徳にすぎない』というやつの方が」
その時、教授が飛び掛るように椅子を立って、先生をぶん殴りました。先生は「新婚さんいらっしゃい」の桂三枝のような動きで、椅子ごと横に倒れてしまいました。また、マイクが床に当たるゴツゴツとした音が教室に流れました。そして、教授がマイクを通さない声で言いました。
「それなら僕はあれですね、ってなんだよ」
私は、少し理不尽だと思いました。あの教授は、それしきのことでイラッとするなんて、大人気ないのではないでしょうか。先ほど先生が教授をぶん殴ったのは、私達大学生が侮辱されたからです。それなのに、教授の方は、個人的にイラッとしたので先生をぶん殴ったのです。
教授は、先生が椅子を戻す前に喋り始めました。
「今の二つは、ほとんど同じ話題なんじゃないか。意識の制約が社会的に強く要求されれば、究極には沈黙の形を取らざるを得ない。だからこそ、沈黙は完全性の一つの属性となる。愛や正義に基づく徳行を為せるとしても、それが個人的なものから逸脱すれば悪徳だ。徳行が沈黙しないのならね。逆に言って構わないなら、社会においては主張そのものが悪徳となる。報道なんて徳行のフィルター、悪徳の鋳型そのものだ。しかしそれならば、我々がこうして喋るのも悪徳ということになるね」
その間に、先生はようやく椅子を直して座りました。
「悪徳でしょうね」
教授は、また先生をぶん殴りました。先生は、今度は椅子ごと後ろに倒れました。でも、これは教授が倒れる時に一度見た動きです。先生は油断していたのか、マイクが派手に飛んで、離れたところに落ちました。ゴッ、ドッとこれまでで一番大きな音がしました。
「目を見て喋るな」
教授は、今度はマイクを口に当てたまま言いました。私は衝撃を受けました。私だけではありません、教室中が、ざわめきました。みんな、小さい頃から、人の目を見て喋ったり聞いたりするように教わってきたのです。
先生が黙って椅子を直すのを、私はじっと見つめていました。先生は襟を正してから椅子に座りましたが、教授をイラッとさせるのが怖いのか、なかなか喋りだそうとしませんでした。しかし、そのまま口を噤んでいたら、きっと教授をイラッとさせてしまうのです。沈黙は、完全性の属性の一つに過ぎないのです。
しばらくの間、教室は静寂に包まれました。私は息を呑んで、その様子を見守っていました。
やがて、教授が大きく息をついて、窓の外に目をやりました。が、次の瞬間、ゆっくりと先生の方を向きながら立ち上がり、歩み寄ると、思いきりぶん殴りました。
「あっ」
私は驚いて、思わず声を出してしまいましたが、そういう人は何人もいました。
教授のその拳は、今までで一番力のこもったものでした。先生は、斜め後ろに、吹き飛ばされるように倒れました。マイクも同じ方へ飛ばされて、学生の座っている最前列の席へぶつかって、その場所とスピーカーから大きな音が聞こえました。
誰もが、教授はどうしてイラッとしたのかと外に目をやりました。すると、雨がぽつぽつと降り出していました。
「傘を持ってきてないんだ!」
誰かが叫びました。私はなるほどと思いましたが、教授の荷物が置いてある場所を見ると、椅子のところに、傘の柄が見えました。
「傘は持ってきてるわ!」
私は一歩前に出て、そこを指さし、大きな声で叫びました。教室中の人が私を振り返りました。自分でもこんな大胆なことをするのに驚きましたが、私は知らぬ間に、ノリノリになっていたのです。
「傘はあるけど、ただ単にイラッとしたんだわ!」
私は、人間こうでなくっちゃと、なんだか途轍もない感銘を受けていることがはっきりとわかりました。私は今、人間のことが、どんな言葉で語られるよりも、ずっと鮮明にわかって、悲しくなるよりは、なんだか清々しいような気がしたのです。出かけた先で雨が降り出してイラッとした時、私達は、傘があろうとなかろうと、目の前の人間をぶん殴りたいに違いない、なぜだかそう思いました。
その時、私は、否応無く秋葉原の事件を思い起こしたのです。私達はイラッとします。彼の人生をなぞっても、彼のイラッを知ることは出来ません。誰のイラッも知ることが出来ません。でも、誰のイラッも同じような気もするのです。私は時々イラッとしますが、ずっとずっとイラッとしていたら、人をぶち殺してしまうというのは、今この瞬間だけかも知れませんし大きな声では言えませんが、なんだか少しわかる気がするのです。イラッとしてぶん殴れるような今のこの気持ちなら、イラッとして殺してしまうのも、もう一息だというような気もしてしまうのです。でも、私はまだこの先、いいことがあると自分で思っていますし、期待しているし、そして実際、いいことは多分あるのです。私を「普通の生活」にとどめて置いているのは、そのことだけかも知れません。そして彼は、他の人にとっての「かけがえのない人生」というのはそういうものであるということを、むしろ私達よりも考えていたように思えるのです。こうした事件が起こって思い出すようにそれを考えまた忘れてを繰り返す私達よりも、ずっと長い間、彼は考えていたと思うのです。もしくは、考えざるを得なかったと思うのです。私の憶測ですから確かなことは言えませんが、件の携帯掲示板にあったような単純な文章を書く人が、そういうことをずっと、じっと考えるということは、特殊なことではないでしょうか。その考えには、私や誰彼がこうした話題を話す時に混じるような知的好奇心のようなものが、きっと恐ろしいほど極端に、無い、ような気がします。それでも、彼は考え続けたのです。私は、それが一番不思議な気もするのです。だから、彼の考えは私達ほどなんというか進んでいませんし、とても感情的だったと思うのですが、今、私達が既に語り始めていることとは全く別なことのように思うのです。より切実であるということでもなく、彼にとっては自分のことで私達にとっては他人事であるというのでもなく、単に、考えの種類のようなものが違っているような気がするのです。私達の多くは、彼がイラッとしたことについて考えているのですが、彼はイラッとして殺すことそのものについて考えていたように思えるのです。私達は、そこの接続のことだけをうやむやにし、「なぜ」という言葉で片付けています。もしそれを考えるとして、彼がそのことを考えるのにかけた時間に遠く及ばないのです。とはいえ、本当のことはわかりませんし、もしそうだとしてもそんなことは犯罪を正当化する理由にはなりません。もちろん、まったく別の問題です。あの男は、気が狂っていておかしくて本当に最悪で死刑になればいいのです。私はそうも思えるのです。でも、私は、イラッとしてぶん殴る教授を見ていて、それ以外のことも考えなければいけないような気がしたのです。心の闇や社会の状況ではなく、彼のことでなく、私のことを、人間のこと自体を、考えなければいけないと思ったのです。そして、イラッとしてぶん殴りたくなる理由を、私は絶対に知らないのです。
私が我に返ると、ぶん殴られて床に女座りになった先生が、遠く私を見上げていました。その目! その顔! 私は、もし壇上にいたなら、イラッとしてぶん殴ってしまっているのだろうと思いました。
「須藤君、今日はおもしろい試みをしたいと思うんだ」
「なんでしょう」
「少しでもイラッとしたら、相手をぶん殴る」
「いいですね」
そこで、ドッと笑いが起こりました。お二人は口裏を合わせて、ふざけているのです。私も楽しくなって、くつくつと笑いました。こうした場で飛び出すユーモアというのが、私は大好きです。
「それでテーマなんだけど、何にしようか。僕は、『沈黙は、完全性の属性のひとつである』というカフカの言葉について話してみたいと思うんだがね」
「大学生には刺激になるでしょうね」
「相手を言い負かしたい連中ばかりだからね」
その時、先生が突然立ち上がると、教授をぶん殴りました。教授はパイプ椅子に座っていましたが、そのまま椅子ごと後ろに倒れました。マイクが飛んで床を跳ね、ドッドと音がしました。
私は唖然としました。教室に緊張が走るのがはっきりとわかりました。
「そんなことないでしょう」
先生が教授を見下ろしながらマイクを通さず直接空気を震わせた音は、一番後ろにいる私にも微かに聞き取ることができました。
教授は何も言わず、ガタガタと椅子を直して、また座りました。そして、何事もなかったように喋り始めました。
「君の方から何もなければ、それで一つ話してみようと思うよ」
「それなら僕はあれですね、カフカならば『意識に制約をもうけることは、社会的要求である。すべての徳行は個人的であり、すべての悪徳は社会的である。社会的徳行と見なされているもの、たとえば愛、無私、正義、自己犠牲などは、〈おどろくほど〉弱められた社会的悪徳にすぎない』というやつの方が」
その時、教授が飛び掛るように椅子を立って、先生をぶん殴りました。先生は「新婚さんいらっしゃい」の桂三枝のような動きで、椅子ごと横に倒れてしまいました。また、マイクが床に当たるゴツゴツとした音が教室に流れました。そして、教授がマイクを通さない声で言いました。
「それなら僕はあれですね、ってなんだよ」
私は、少し理不尽だと思いました。あの教授は、それしきのことでイラッとするなんて、大人気ないのではないでしょうか。先ほど先生が教授をぶん殴ったのは、私達大学生が侮辱されたからです。それなのに、教授の方は、個人的にイラッとしたので先生をぶん殴ったのです。
教授は、先生が椅子を戻す前に喋り始めました。
「今の二つは、ほとんど同じ話題なんじゃないか。意識の制約が社会的に強く要求されれば、究極には沈黙の形を取らざるを得ない。だからこそ、沈黙は完全性の一つの属性となる。愛や正義に基づく徳行を為せるとしても、それが個人的なものから逸脱すれば悪徳だ。徳行が沈黙しないのならね。逆に言って構わないなら、社会においては主張そのものが悪徳となる。報道なんて徳行のフィルター、悪徳の鋳型そのものだ。しかしそれならば、我々がこうして喋るのも悪徳ということになるね」
その間に、先生はようやく椅子を直して座りました。
「悪徳でしょうね」
教授は、また先生をぶん殴りました。先生は、今度は椅子ごと後ろに倒れました。でも、これは教授が倒れる時に一度見た動きです。先生は油断していたのか、マイクが派手に飛んで、離れたところに落ちました。ゴッ、ドッとこれまでで一番大きな音がしました。
「目を見て喋るな」
教授は、今度はマイクを口に当てたまま言いました。私は衝撃を受けました。私だけではありません、教室中が、ざわめきました。みんな、小さい頃から、人の目を見て喋ったり聞いたりするように教わってきたのです。
先生が黙って椅子を直すのを、私はじっと見つめていました。先生は襟を正してから椅子に座りましたが、教授をイラッとさせるのが怖いのか、なかなか喋りだそうとしませんでした。しかし、そのまま口を噤んでいたら、きっと教授をイラッとさせてしまうのです。沈黙は、完全性の属性の一つに過ぎないのです。
しばらくの間、教室は静寂に包まれました。私は息を呑んで、その様子を見守っていました。
やがて、教授が大きく息をついて、窓の外に目をやりました。が、次の瞬間、ゆっくりと先生の方を向きながら立ち上がり、歩み寄ると、思いきりぶん殴りました。
「あっ」
私は驚いて、思わず声を出してしまいましたが、そういう人は何人もいました。
教授のその拳は、今までで一番力のこもったものでした。先生は、斜め後ろに、吹き飛ばされるように倒れました。マイクも同じ方へ飛ばされて、学生の座っている最前列の席へぶつかって、その場所とスピーカーから大きな音が聞こえました。
誰もが、教授はどうしてイラッとしたのかと外に目をやりました。すると、雨がぽつぽつと降り出していました。
「傘を持ってきてないんだ!」
誰かが叫びました。私はなるほどと思いましたが、教授の荷物が置いてある場所を見ると、椅子のところに、傘の柄が見えました。
「傘は持ってきてるわ!」
私は一歩前に出て、そこを指さし、大きな声で叫びました。教室中の人が私を振り返りました。自分でもこんな大胆なことをするのに驚きましたが、私は知らぬ間に、ノリノリになっていたのです。
「傘はあるけど、ただ単にイラッとしたんだわ!」
私は、人間こうでなくっちゃと、なんだか途轍もない感銘を受けていることがはっきりとわかりました。私は今、人間のことが、どんな言葉で語られるよりも、ずっと鮮明にわかって、悲しくなるよりは、なんだか清々しいような気がしたのです。出かけた先で雨が降り出してイラッとした時、私達は、傘があろうとなかろうと、目の前の人間をぶん殴りたいに違いない、なぜだかそう思いました。
その時、私は、否応無く秋葉原の事件を思い起こしたのです。私達はイラッとします。彼の人生をなぞっても、彼のイラッを知ることは出来ません。誰のイラッも知ることが出来ません。でも、誰のイラッも同じような気もするのです。私は時々イラッとしますが、ずっとずっとイラッとしていたら、人をぶち殺してしまうというのは、今この瞬間だけかも知れませんし大きな声では言えませんが、なんだか少しわかる気がするのです。イラッとしてぶん殴れるような今のこの気持ちなら、イラッとして殺してしまうのも、もう一息だというような気もしてしまうのです。でも、私はまだこの先、いいことがあると自分で思っていますし、期待しているし、そして実際、いいことは多分あるのです。私を「普通の生活」にとどめて置いているのは、そのことだけかも知れません。そして彼は、他の人にとっての「かけがえのない人生」というのはそういうものであるということを、むしろ私達よりも考えていたように思えるのです。こうした事件が起こって思い出すようにそれを考えまた忘れてを繰り返す私達よりも、ずっと長い間、彼は考えていたと思うのです。もしくは、考えざるを得なかったと思うのです。私の憶測ですから確かなことは言えませんが、件の携帯掲示板にあったような単純な文章を書く人が、そういうことをずっと、じっと考えるということは、特殊なことではないでしょうか。その考えには、私や誰彼がこうした話題を話す時に混じるような知的好奇心のようなものが、きっと恐ろしいほど極端に、無い、ような気がします。それでも、彼は考え続けたのです。私は、それが一番不思議な気もするのです。だから、彼の考えは私達ほどなんというか進んでいませんし、とても感情的だったと思うのですが、今、私達が既に語り始めていることとは全く別なことのように思うのです。より切実であるということでもなく、彼にとっては自分のことで私達にとっては他人事であるというのでもなく、単に、考えの種類のようなものが違っているような気がするのです。私達の多くは、彼がイラッとしたことについて考えているのですが、彼はイラッとして殺すことそのものについて考えていたように思えるのです。私達は、そこの接続のことだけをうやむやにし、「なぜ」という言葉で片付けています。もしそれを考えるとして、彼がそのことを考えるのにかけた時間に遠く及ばないのです。とはいえ、本当のことはわかりませんし、もしそうだとしてもそんなことは犯罪を正当化する理由にはなりません。もちろん、まったく別の問題です。あの男は、気が狂っていておかしくて本当に最悪で死刑になればいいのです。私はそうも思えるのです。でも、私は、イラッとしてぶん殴る教授を見ていて、それ以外のことも考えなければいけないような気がしたのです。心の闇や社会の状況ではなく、彼のことでなく、私のことを、人間のこと自体を、考えなければいけないと思ったのです。そして、イラッとしてぶん殴りたくなる理由を、私は絶対に知らないのです。
私が我に返ると、ぶん殴られて床に女座りになった先生が、遠く私を見上げていました。その目! その顔! 私は、もし壇上にいたなら、イラッとしてぶん殴ってしまっているのだろうと思いました。
女とコーラ
木梨
不思議なことに、見知らぬ人たちへの好奇心が膨らんできた。私は彼らのキャンプの風下にいたので、スープの香りが漂ってきた。彼らは殺し屋かもしれないし、サディストとか野蛮人とか醜い類人猿とかいった存在かもしれないのだが、気づいたら私はこう考えていた。
「なんて魅力的な人たちだ。なんて才能なんだ。なんて美しいんだ。彼らと知り合えたらいいなあ」
それもみんな、おいしそうなスープの匂いのせいだ。
(ジョン・スタインベック『チャーリーとの旅』より)
「一汗かいたところで、さあ順番に1つの風呂へ入ってもらおう」
バズーカを背負った亀に命令されても町の青年団は黙っていた。炎天下を何十本もダッシュさせられたばかりで疲れ果てていた。
しかも、亀を3匹飼っているノリコが「バズーカを背負っているとはいえ、亀は動きが鈍いから回り込めば難なく勝てる」と襲いかかった時、2mの距離でバズーカに撃たれて爆発、冗談抜きで死んでいる。死肉の欠片を都会のものより小さくしなやかな烏が奪い合うのを見て、誰もが暗い気分になった。
火薬と血とうだるような暑さで陰惨に彩られた舞台は、大自然に突如現れた広大な駐車場。四方を囲む山では「廻」「向」「発」「願」という大文字がそれぞれ焼かれている。その駐車場のど真ん中、空高く、ヘリコ(プター)が現れた。
ヘリコは風呂をつり下げてゆっくりと降りてこようとしていた。湯をこぼさないようにしているとわかった。風呂の作る影にすっぽりおさまった青年団は惚けてそれを見上げていたが、タツノリが風呂釜の底指をさして叫んだ。
「あれは、オレんちの風呂!?」
「めちゃイケのノリをやめろ」身勝手な発言にバズーカを背負った亀がすぐさま忠告した。「単に同じメーカーさんのものを扱っているだけだ。あまりに口が過ぎるようなら、あの女のようにしてやるぞ!!」
あの女って誰だ……? と青年団の輪から少し外れて立っている木梨は思った。そしてすぐに(ノリコのことか)と思った。タツノリが声帯を除去された障害者のように黙るのを見て、木梨は(すごい、芸能人のフェラチオくらいすごい)と考えた。
体中に汗と土埃がまとわりつき、濁った膜を張っている。何せ、燃え盛る山に囲まれている上に、今日は観測史上最高気温を埼玉県熊谷市で記録した猛暑である。さっきバズーカを背負った亀が教えてくれたのだ。駐車場のアスファルトはまたもとの液体に戻ろうとテカり始めていた。
(ここは埼玉県熊谷市では無い)
遠い樹上からリスが問いかけてくる。しかしそんな小動物の屁理屈に返答するのも暑い。なぜならば。
(クソがしたいな……)
木梨は青年団の仲間達といるというのに便糞(べんぐそ)をもよおしていた。体感温度は4倍(しばい)に跳ね上がり、今はひとり160度の灼熱の中でもだえていた。どんなに不潔なお便所でも今は淀みなく、遠慮無しの動きで入り構えよう。
「もう一度言う。順番に風呂へ入るんだ」
バズーカを背負った亀の天から降ってくるように響く言葉で我に返った木梨に、暑苦しいヘリコの音と風が襲いかかる。地面に映る影はみるみる大きくなり、一度真っ暗になった風呂釜の底が再びはっきり浮かび上がった。
「風呂だ!」というノリヤスの叫び声が微かに聞こえた。「風呂の底が降りてくる!!」
同時にわざとらしく走って行く青年団の仲間達に、木梨は出遅れた。なぜ急に走り出したかと不思議に思って見ると、かがみこんだバズーカを背負った亀が彼らに照準を合わせてプレッシャーをかけていた。
するとクリッと音を立てて、バズーカが木梨に向けられた。体を小刻みに動かして、もう出る、今すぐにでもといういきなりなメッセージを伝えてくる。
亀が言った。何かを。
木梨は走り出した。(よかった)と思った。その震動を全てケツへの引力に変換するため、ひょこひょこ走った木梨。バズーカを背負った亀はすぐに体勢を起こし、何とも言えない動物らしいうるんだ瞳を差し向けていた。木梨は、さっきからこのバズーカを背負った亀が見せる言葉とは裏腹の穏やかな視線が気になって、便糞がしたいのはともかく、ノイズの多い中でも冷静な自分を保てていることに気づいた。
(あの亀は多分すごい亀だ。あの亀には便糞のことも僕のこともみんなバレているにちがいない)
殺されるという恐怖が先行しているのか、青年団の仲間達はまだ風呂が降りきっていないのに、その下に集まってさっそく服を脱ぎ始めていた。女も含めて、もう下着しかつけていないような状況になっている。無雑作に脱ぎ捨てられてあちこちで重なり合い、ヘリ風にあおられて絡み合う衣服を見下ろしているうちに空虚な殺意が木梨に生まれた。
風呂が湯を多少こぼしながら着陸し、ワイヤーをぶら下げたヘリコプターが山の向こうへ一瞬で飛んで行った。消えるまでみんなで見ていた。
音もなくなり、思い出したように青年団が風呂の周りに群がった時、一番前にいたノリヤスが手を広げて制した。
「待て! 順番を決めよう! あの亀は1人ずつ入れと言っていた。だから順番を決めよう。さもなければオレたち、殺されるぜ!!」
(一番前で今にも入ろうとしていたくせに)と木梨は一番後ろで思った。
そうだそうだ、順番を決めようと盛り上がる青年団のもとへ、バズーカを背負った亀がグッチャグッチャと不気味な音を立ててゆっくり歩いて来た。木梨は、ブーツの中にかなり多量の"精液"がたまっているようだと直感した。
しかしそんなことは気にしてないというように手を上げて、待て待てというジェスチャー。さらに親指を立てて肩越しに勢いよく向けた後方、東の「願」と燃えている山のふもとから、黄色いジープが走ってくるのが見えた。ここに来て亀がなぜ急に喋らなくなったのかはわからなかった。
そのジープは全く音もなく近づいてくるように思える。『しんぼる』冒頭より盛り上がる、胸。
永遠に退屈して死ぬんだと思えるほど長い時間が経った。それもそのはずジープは速度を変えなかったが、近づいてみると時速10キロほどしか出ていないことが判明した。横に「Nestle」と書いてある。シールとかではないようだ。何か関係があるのだろうか。すごい時間の無駄をした感じがした。
運転席には、今度は大砲を背負ったバッファローが乗っていた。風呂に横付けして顔を出し、
「安全運転で、きたぜ」
だからみんな、自分が言われたと思った。バッファローの毛はどこかに触れてこすれるたびに埃が立った。
それから誰もが、ジープの後ろのガラス無し窓から黒い照りのあるぼろに包まれた腕を投げ出して皺だらけの手を垂らしている、どこからどう見てもホームレスのジジイに注目した。興味ゼロ、性欲100の仏頂面で下着姿の若鶏たちを見ている。
「よし、降りろ」とバズーカを背負った亀。
視線を重たそうに持ち上げて、それと同じくらい冴えない動きでホームレスは降車した。全身がさらされたことで、より強い乞食の空気が暑さの中に解き放たれた。全員、思わず鼻をつまんだ。
ホームレスはどんな時でもおどおどしない。木梨は(それだけで本当に尊敬に値する)と思った。促されるまで全然降りないところも気に入った。
(これは世の中に珍しいもので、だからいいんだ)
一歩、また一歩と、ホームレスが風呂に近づく。でもその視線は風呂にない。女の体をなめるようにというか、ベロを押しつけるようにして見ている。なめらかな女の体でそのベロクソを無理矢理とらんとばかりに圧迫感のある瞳はにごつき、ダンロップのサンダルを引きずる鈍い音が品定めの時間を稼ぐように響くばかりの時間があった。
木梨には、見合わせている顔と顔でみんながどう思っているのかわかった。男たちが頼もし顔を作り始め、女たちは途端に体を縮こまらせて男の陰に隠れるように小さく足を運んだ。その後ろで木梨は、もはや気にすることなく放り出された彼女たちのだらしなくしわの寄ったパンティを見ていた。便糞がしたすぎのおかげか、ひ弱でどエロい劣情をもよおさずにすんだ。本当にクソがしたすぎてよかった。選ばれた材質の布越しに浮かび上がる小さな尻の雰囲気やメッセージの汚れ無き汚れに、中身のない殺意が風船のようにふくらんだ。
「そのホームレスの人も、君達のお風呂仲間に入れてやれ」
バズーカを背負った亀が急に叫ぶと同時に、どうせ予期していたのだろう、抜けの悪い悲鳴が上がった。鼻をつまんでいるせいだ。
「ありえないんだけど」「こんなくっさい乞食と同じ風呂に入るなんて、冗談でしょ?」
「だいたいこいつは何ヶ月風呂に入ってないんだよ」
「5年」
なぜかそんなことだけホームレスがすぐ答えたので、青年団はたじろいだ。
木梨は応援する気持ちで、ホームレスのとぎすまされた刃の切っ先によく似た横顔を見ていた。肌はどす黒い灰色にかたまってヒビが入り、そこだけ肌の色がやっと透けている。こんなに暑いのにコートのようなぼろを着て汗一つかいていないのは、汗腺も5年で塞がってしまったのか、生活の知恵か、体質か。
木梨は鼻もつままないで(ああ、ぼくはこの人が一番に風呂に入るべきだと思う)と考えた。
(それがいちばん価値のあることだ)
心の底からそう思っていて、それを言いたくて、みんなに近づいていった。本気で伝えれば、みんなきっとわかってくれるはずだ。でもまだ会話が続いているので様子を見ることにした。
「ていうか、どうしても入れなきゃいけないの?」
歯科衛生師になりたいとさんざん抜かすノリカの言葉にバズーカを背負った亀がうなずき、大砲を背負ったバッファローもクラクションを軽快に3度鳴らした。
「じゃあ、入れようぜ」
タツノリがちょっと笑みを浮かべて、さも、こともなげに言った。女たちから驚きの声と渋る声が飛ぶ。タツノリは得意げに少しとがった口を動かした。
「だって、そうじゃなきゃオレたちはノリコみたいに殺されてカラスに食われっちまうんだぞ。バズーカというのは、凄い威力を持った兵器だからさ、ヤバいよ。でも大丈夫、こいつを最後に入れればいいんだ。順番はこっちが決めていいんだから」
「そっか!」「タツ頭いいね!」
「じゃあ、女子がみんな先に入って、それからオレらが入って、そんでこいつを最後に入れりゃいいんだよ。それで何の問題もないじゃないか」
ホームレスはその会話を黙って聞いていた。もう全てのことに興味を失ってしまったように虚ろな瞳を、アスファルトの鈍い照り返しのせいで生々しさに欠けた女の体に、それでも執拗に向けているだけだ。垢がへばりつけなかったまぶただけが白く、滅多にしないまばたきのたびに光っているように見える。なんだかキレイで、便糞のしたい気持ちも少し落ち着いた。
会話が少し途切れた。それからまたわずかに沈黙が続いた。だから、木梨はやっと言葉を挟めることになった。
「あの、ちょっと」
みんなが僕を振り返る。だもんで、後ろからは見えなかった胸の谷間などを見ることが出来た。横からというか上からというか、盛り上がった胸の内側を鋭い角度で見ることが出来た。
「なんだ」
「どうしたの、木梨くん」
なんだか僕が喋るだけで質問が飛んでくる。疑うような、何を喋る気だという少しだけ反り返った視線が注がれる。
「僕は、このおじさんが、一番最初にお風呂に入るべきだと思うんだけど」
みんな呆気にとられたようだった。僕もなんだか変に思い始めた。口に出した途端、僕の言葉だけがらんどうになる。冗談にも本当にもとられない言葉が炎天下に放り出されて早くも汗をかき始めた。ホームレスも相変わらず汚れた顔に冴えた表情を浮かべてくれない。
「え? なんで?」
やけに形のしっかりしたピンクを黒で縁取ったような上下の下着をつけたミノリが本当に不愉快そうな顔を差し向ける。虚ろな殺意があぶくのように弾けながら増え続けて、はずみで便糞の意が発奮する。肛門が笑い出しそう。
「いや……ちょっと待って……そのブラジャーにはワイヤーが入ってるのか…も……?」
思わぬことを口走りながらも腰を反らせて肛門に全ての持ちうる力を集めていると、女としゃべっているつもりなのに、無関係のノリヤス、タツノリになめていると思われてしまったようだった。
「おい、ふざけろ?」
「人が死んでるんだぞ?」
人はすぐキレる。もうすぐキレそうな自分をちらつかせて「ふざけろ?」と言ったりするから手に負えない。なぜ僕はすぐ怒らないのに、人はすぐ怒るのかいつも不思議でならない。生まれたばかりの感情を自分の許から放り出してしまう人達とどう上手くやっていけばいいのかわからない。だってこれでは、僕ばかりが人を怒らせていることになってしまうではないか。
「でも、この人は5年もお風呂に入っていないんだ……じゃあ最初に入らせてあげようよ……」
「だから、風呂の湯が真っ黒になるぞ。こいつが入ったら」
「女子もいるんだ。そんな汚い風呂に入らせるわけにはいかないだろ」
「木梨、何も風呂に入らせないわけじゃないんだよ。俺らがキレイに入って、最後に入ってもらうだけなんだ」
こういうとき女たちは黙っている。男に任せて黙っている。でも女は、自分がどの男の味方をしているかわかるようにしているのだ。自分にも他人にも、その事実を体と色を用いて伝えている。そうでないと、いざという時に守ってもらえない……。すごい。
「価値あることをしようよ……」
僕は一人で体をくねらせて内からせり上がり下っていく何か、何かというか便糞に耐えている。無用の戦いに汗が止まらない。ケツが浮いてきた。
「おい、その動きはなんだ。ふざけているんだな」
「いや、そんなことは……」
「みんなの幸せのことを考えろよ」
「でも、この人はかれこれ5年もお風呂に入っていなくて、だから最初に入るべきだと僕は思う。みんなにはわからないかも、知れないけど、僕は本気でそう思うんだ。この人がかわいそうとかじゃなくて、ただ、なんとなく、でも強く、心からそう思って言うんだ」
僕は便糞に負けてしゃがみこんでしまった。しかし肛門が開きかけることに気づいたのですぐに立ち上がった。
「意味わかんない。何言ってんのか」
内容よりも感情を伝えるようにノリカが言う。便糞。こういう時に女の本性は出るんだ。全て脱ぎ捨てた時、己の腹を隠す術を女は持っていないんだ。だって女には他にもっと隠すべきところがあるから、手がふさがっていて、開き直ることが出来る。
僕は今ただ単に、その上にあるおっぱいもその下にある女性器も放っておいて、腹を刺したい。がら空きのいやに白いミノリの腹に良く研いだ清潔な包丁でぷつりと刺して、ずぶと半分ほど入ったところで鍵を開けるように、くるりと空気を混じらせる……。包丁よりも小さなナイフで、街頭のメガネ洗浄機につけておいたのを取って、水滴も拭わずに、ゆっくりとそんなふうに……便糞がしたい……。
「おかしいよ、わかんないなんて……普段から何も考えてないんじゃないの……?」
そしたら男が誰かずいと出てくる。こんなシーンを僕は知っているぞ。きっと君たちだってご存知のはず。殴るんだろう。蹴りはしないよ。同じことを繰り返すんだ。でも僕はそれを知っているだけマシに違いない。こうなることはわかってて言ったんだ。便糞がしたい……。
出てきたのはタツノリだ。全部放り出して便糞がしたい。誰が出てきたっていいのにわざわざ出てくるタツノリは、この現実で、事実として、本当に免許をとって恋人をつくってセックスをするんだろう。日常的にしているんだろう。手帳についているシールに「セックス」があったら便利に活用するはずだ。足りなくなって買い直すかもしれない。ここにいる全員が全員、そんなことをしているのだ。していなくても、することにやぶさかではあるまい。
「おい、おい」
と短く切れた強い声を放つと同時にタツノリが僕の胸を突く。後ろにふらついて流れた僕を追いかけてさらに突いて、どんどん二人で後ろに下がっていく。こんな光景だって見たことがある。
胸を突かれるたびに息が止まる。多少苦しいこともあるけれど、全部何かの繰り返しだ。問題はそれを自分だけに起こりうるのだと信じられるかどうかだろう。つまりタツノリの方ではこんなことの全部が全部を"自分"だけに起こると疑っていないのだ。それだからこんなに迷いがない。そんなこと、何の意味も無いのに大したもの……。
「俺をキレさせんなよ。木梨」
きちんとした顔。初めてきちんとタツノリの顔を見た。僕は言った。
「君が犬を飼ったら、その犬が君になつくのが納得いかない……」
僕はもともとなんにも怒ってなんかいないのだから、何を言っても心は晴れない。便糞がしたい心だけが国際的に本当だと思える。
「全員ぶち殺したいな……」
誰にともなくそう言っても結果は同じ恥の上塗り。怒っていない僕だけが人を怒らせる。
それからすぐに殴られて気を失った。少しだけ人間という感じがした。
いつ気がついたのかわからないけど、体はもうアスファルトにくっついたように熱く凝り固まっていた。便糞も一役買っているだろうか下半身の暑さの中に有機的なあたたかさが存在している。指はわずかに動くだろうか、それもなんだかわからない。アスファルトに密着した耳はどろどろに溶けてしまったらしくもう音を取り込もうとはしない。視線がごろりと音を立てたかと思うと、急にまわって地面にくっついた。
体全体ひどく熱いけれども、どこか入りたてのサウナのように快い。生きながら腐るのはこんな気分なのかもしれない。恥辱だけが残っていくように思われる。
ネスレのジープはもういなかった。バズーカを背負った亀はいつの間にかパイプ椅子を持ち出してくたびれたというように座っている。ブーツを脱いで足を組み、ブーツの中の精液を取ろうとしていた。やはりそこには精液が何ミリかたまっていたのだ。振られて跳ねた精液は僕の腹の上で、フライパンに落とした水滴のように小さな湯気を出して消えた。バズーカを背負った亀のくれた冷たい動物的一瞥で、自分が便糞をもらして腐りかけていることが本当に理解できた。
だから性懲りもなく思うのだが、結局、僕だけが人を悲しませたり、もしくは喜ばせたりすることになるではないか。僕を怒らせたり、喜ばせたり、悲しませたりする人がどこにいるのか知らないけれど、でも、とりあえずこんな僕みたいなのといたっておもしろくもなんともないだろう。単に息をしているだけだもの。そうなったら、どうあれ僕は最後、あすこにいるあの人のようになる。
ホームレスは少し離れた場所の地べたに片膝を立てて座り込んでいた。顔は風呂の方に向けている。どうせ女の肌を見ているのだろう。何もかも失って最後、そういうことだけに興味や欲望が残るのなら、僕は本当になんと無駄なことをしていたのだろうか。
それとも、うらぶれた彼の中にまだ何かあるのかも知れない。そこには、こんなに偉そうに全て決めつける僕をぶちのめすようなとてつもない何かが息を潜めているのだろうか……。
「廻向発願」の火はもう燃え尽きていた。四方で立ち上る黒い煙が空に消えなんとして掠れゆく様を見ていたら、駐車場の真ん中で誰かが一番風呂に入ったのだろう、にぎやかな声がどこかで響いた。どこか楽しげに水面が揺れる様が脳裏に焼き付いた。跳ねた湯の数滴が宙を舞い、僕の顔にかかる。
その湯はいつまでも蒸発せず粒だって残って、琥珀のように固まるつもりらしい。しかも彼らはそれを思い出と言うつもりらしい。
そうだ、風呂はもう汚れてしまった。風呂の湯はいつも少しずつ上手く汚れていく。まるで世界の誰もがそれを望んでいるようだ。実にこの世は糞だらけの割にけっこう盛り上がっている。ホームレスが誰にも聞こえない下手くそな口笛を吹くから、僕の夏、木梨の夏はいよいよ砕けてはがれ落ちそうになる。