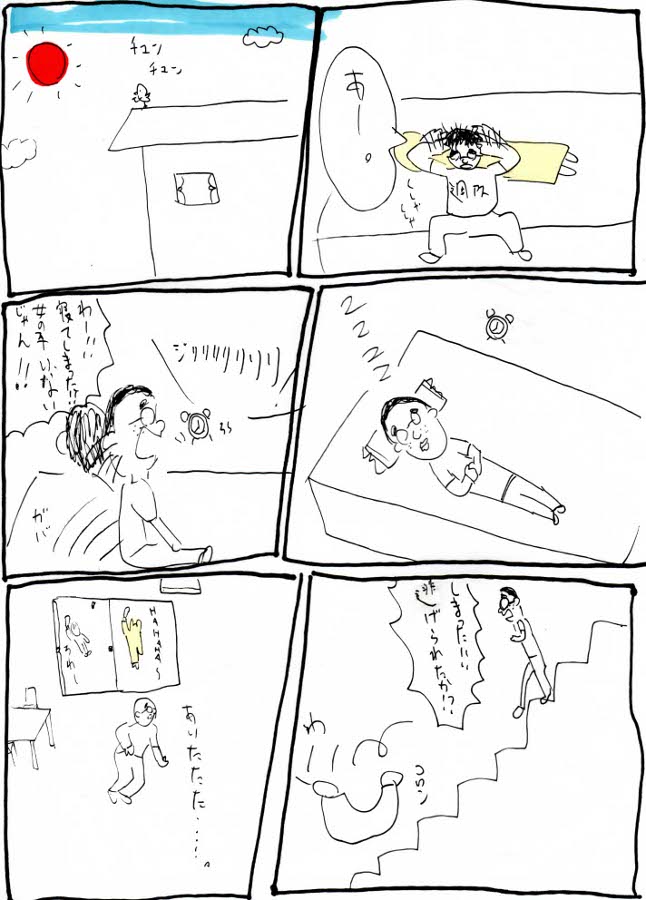椅子グラビア

椅子でーす


よろしくおねがいしまーす


最近よく背中がギチギチ鳴るんです


バネがおかしいのかな



お昼寝ターイム

 大胆ポーズにも挑戦
大胆ポーズにも挑戦


無機物にしかできないことっていうのかな
そういう部分を探していきたいですね


------------------------------------------------------------------------------------

なつかしーい

公園なんて何年ぶりだろう?

わわわわ


座られてるときですか?

「なんだこいつ」ってオーラを送ってますね



最近まで四角いものは

全て座布団だと思ってました



これでも小さい頃は運動神経よかったんですよー



びたーん!


リクライニングの加減っていうのがだんだん分かってきたんです
お芝居との両立もうまくやっていきたいな


棟梁は弁当と一緒に梁の上
結婚四年目の三人家族のものだという二階建ての新築家屋はもうすぐ木組みが完成するところだった。初夏、天気も良く、昼の休憩を告げる棟梁の声も心なしかいつもより高く響いた。
「鮭がうめえうめえ……」
僕たち、下っ端ヤング大工マンたち(低学歴)は、地上で弁当を食い、弁当を褒めて午後もがんばれる力を底上げしながら、子供部屋が二つできる二階部分へ渡した梁の上を見上げた。
棟梁はただ一人、縦置きしたヤングマガジンほどの幅(正ヤンマガ幅)で弁当を立ち食いしていた。これは棟梁の七百八個(ななひゃくやっこ)ある大工奥義の一つ「高い分、美味い」である。
僕たち下っ端ヤング大工マンたちは、犬のように地べたに這いつくばって弁当を食いながら、棟梁の美しい立ち食い姿を惚れ惚れと見上げるしかない。一体どれほどの修行を重ねたら、あんな芸当ができるというのか。そもそも、ああいうことは本当にしておいた方がいいのか。
まあ、もしも、今の自分たちがあそこで立ち食いをしたら、ろくに食べた気がしないだろう。主力級のオカズをぼろぼろ下へこぼした挙げ句、その上へ真っ逆さまに落下、のり弁の香をかぎながら惨めに息絶えることになるに決まってる。頬っぺたに海苔が張り付き、早起きしたお母さんが作ったおにぎりの昼ごろの質感になるに決まってる。
ところが見てください、そう考えてみたら、試しにそういう思考になってみたら、棟梁は本当に凄い。こんなに凄いのにTVチャンピオンに出ないなんて自殺行為ではないかという気持ちで僕たちは箸を口に運んだ。早く食べ終えて、みんなでピザポテトが食べたい。そんな気持ちだった。
しかしその時、棟梁が立っている梁の両側、柱の元に悪魔がいることに気づいた。
い、いつの間に。
「やっぱり悪魔って突然、現れるものなんだ!」
しかもだよ。体全体が濃い紫シッポが矢印の悪魔がカニ歩きで少しずつ近づいてきているんだ。よく見ると、一階部分の柱の両側に、サークルKサンクスでもらえる星形の穴が散りばめられたフォークを大きくしたようなものが立てかけてあった。その無雑作な感じは実に目的をもって来たという気がした。気まぐれではなく、棟梁を狙って、遠くから、来たんだ。弁当が、うまい。
「あの悪魔ども、弁当を立ち食いしてる棟梁を挟み撃ちにする気だぞ」
誰かの小さな声が聞こえ、僕はその時一瞬遅れて、これはえらいことになったなと思って血の気が引いた。みんな目配せする。
「どうしよう」
棟梁はまだ黙々と立ち食いを続けている。やっぱり素直に下で食べておけばよかったんだ。カッコつけてあんなとこで立ち食いなんかして、名人気取りで、だから悪魔に目をつけられてしまうんだ。山頂で食うおにぎりがうまいのは、単に気持ちの問題だ。正直言って、棟梁は、パズドラとかをやってる若い僕たちと何を喋っていいかわからない自分が惨めになるから逃げを打って、あんなところで弁当を立ち食いしているんだ。
片方の悪魔は黄色に赤水玉の箱を持って、横向きでじりじり、時々ふらついて腰をかくかくさせながら、通勤中のような真顔で、弁当を食っている棟梁に近づいていく。もう片方の悪魔は手ぶらで、両手を横に伸ばして、時折大きく息を吐きながら進んでいる。その息は少し紫色をしていて、僕らの手前まで拡散してかき消えた。
なんとなく弁当を手やフタで隠しながら、僕たちは話した。
「しかし、あっちの悪魔は、かなり安定しているな」
「何も持っていないからだよ。偉いのは箱を持っている悪魔だ。もしかしたらとんでもなく重い箱かも知れないというのに」
「かなり、トレーニングを積んでいる悪魔なのかな。確かに重そうだ」
「少なくとも、弁当よりは重いよ……」
日頃から棟梁のことをよく思っていない野津田がボソリとつぶやいた。
みな、はそはそと冷たいごはんを口に運んだ。冷たいごはんは割り箸になんてよく引っかかるのだろう。はっきり割れて、泣きたいぐらいに絡みついてくる。
「あ、見ろ」
ようやく悪魔の接近に気づいた棟梁は、弁当に顔を半ば突っ込みながら、明らかに慌てた様子で交互に振り返り、目だけをチラチラ上げて悪魔を何度も見やった。
そこまでかっこ悪い棟梁を見るのは初めてだったけど、梁の上で悪魔に挟み撃ちされたのでは止むを得まい。しかし、その慌てぶりを普段こき使っている僕たちに見られていると知ったら、棟梁のハートはギザギザになってしまうだろう。子守唄なしで。
僕たちは目配せし、棟梁にわからないよう「弁当8、チラ見2」のフォーメーションをしいた。シャケ、ご飯、卵焼き、白身魚のフライ、棟梁しっかり、ご飯のリズムに箸が陰鬱な調べを奏でようとするが、小豆色をした薄いプラスチック容器が立てるくぐもった音は、白飯部分の重みに全て吸収されてしまうようだ。よく考えられている。
食ってる間に大メインクライマックス、悪魔が棟梁のところまで到着した。
箱を持った悪魔が、やはり真顔で、その箱を棟梁に差し出す。
「これは……悪魔一流の罠に違いないぞ」
「舌切り雀の、大きいつづらのパターンだ」
「真顔で渡されるプレゼントは、絶対に受け取っちゃだめだ。受け取った瞬間、大爆発だぞ」
僕たちはひそひそ口を挟んだが、棟梁はどうやら物につられて受け取ろうとしているようだった。どうにかこうにか受け取ろうと、持っている弁当をどうしようか迷った様子で、きょろきょろしたり、しゃがもうとしたり、おたおたしている。そして、ちょっと照れている。
「まずいぞ。棟梁は悪魔のプレゼントを受け取る気マンマンだ。照れている」
「でも大丈夫。梁の上では、さすがの棟梁も弁当を手放すことができないよ。だからプレゼントももらえない。これでよかったんだ」
そかそか! 僕らがホッとしたその時、棟梁は首を180度、それから体を180度のカートゥーン振り向きをかまし、手ぶらの悪魔に「弁当持ってて……」と言わんばかりにおずおずと差し出した。箸は、ご飯に斜めに突っ込んで動かないようにする生活感になっているようだ。
「ま、まずい! あれじゃあ悪魔の思うツボだ!」
「おい、静かにしろよ。聞こえちゃうだろっ。悪魔の耳は……良いっ!」
「でも、そんなこと言ってる場合か。みすみす悪魔の手にかかるより、ハートがギザギザになった方がずいぶんましだ」
「俺もそう思う。棟梁は欲張り。喩えるなら、動物園で勃起してるライオンだ。もらえるものは悪魔からでももらっちまおうなんて、これだから闇米を体に入れた世代はいやなんだ」
野津田だけはニヤニヤしてしまう笑顔を、顔の前に掲げた鮭で隠していた。そのとき、鮭が自重でパックリ割れてぶら下がった。その隙間から尖りに尖った口角と八重歯がのぞいていた。
「あ、悪魔……」
思わずつぶやいてしまった自分の口をあわてて栗で塞ぐ。弁当に栗が入っていて本当によかった。栗のおかげで命拾い。本来の旬は秋なのに、夏でも栗が流通していて助かった。
そして野津田は割れた鮭を下から丸呑みした。僕はご飯も口の中に放り込み、ぐっと堪えた。口の中が栗とご飯なのか。
そんなこんなで下で盛り上がっていた隙に、梁の上の棟梁は手ぶらの悪魔に弁当を持ってもらうのを断られたような感じになっており、またもおたおたして、そしてなんでだろう、ちょっと笑っていた。
手ぶらの悪魔はバランスを取ったまま、棟梁に向かってしきりに横に首を振っていた。一方で、背中からは、早く早くという感じで悪魔が箱を押し付けている。
押し付けるたびに、棟梁だけでなく悪魔の方の足元もふらつき、さすがにびびっている様子だ。バランスを取るため、早く受け取って欲しいのだろう。それなら手ぶらの悪魔は弁当を持ってくれたっていいのに、いったい、悪魔どもはプレゼントを受け取って欲しいのか、欲しくないのか。絶体絶命のピンチだ。
「あの状況じゃ、悪魔のサプライズ・プレゼントを早く受け取った方が安全だな」
「でも、一瞬でもいいから弁当を持ってもらわないことには棟梁はいつまでもプレゼントを受け取れないぞ」
弁当を両手に持ったまま体をくの字に折った棟梁の皺だらけの笑顔が、かんべんしてくださいよ、と口を動かしたように見えたが、黙っていた。黙っていたけど、
「一瞬でいいんですけど!」という棟梁の声が聞こえた。
それでも悪魔は頑なに、首を振っている。真っ直ぐ横に手を広げ、足を前と後ろに付けていた。もしかしてつま先を見たら、目印の線が引いてあるかも知れない。
そこで棟梁は何かひらめいたのか、悪魔に何か言った。二度目に言った時、僕たちにも、どうにか聞こえた。
「すぐ食っちゃうね」
悪魔はそこで、少し後ずさりして、棟梁が弁当を食べる分のスペースを作ってくれた。言葉が通じるんだ。棟梁はすぐさま勢いよくで食べ始めた。
「こんなの、すぐよ」
不安になったのか、棟梁は割りと大きい声で、箸を耳の横で天に向けて刺すような小さな動きをつけて言い放った。バカ! そんなにプレゼントが欲しいのか。僕は、あの箱の中身は、相手が悪魔ということや水玉の柄から言って、90%の確率でピエロもしくは松井秀喜のバブルヘッドが飛び出すビックリ箱だとあたりをつけていたので、棟梁がそんなに必死になるのがとても情けなく思えた。きっと、大福とか、ダウンジャケットとか、重たい灰皿などが入っていると思っているのだ。
「一瞬よ」
一瞬とか言いながら、棟梁の食はいまいち進んでいなかった。食べるやる気を見せているだけだ。あんまりバクバク食べると、やはりそこは細い梁の上、いくら棟梁といえどもフラフラしてしまうのはわかるが、もう少し冒険してもいいんじゃないだろうか。何のために、今まで毎日そこで弁当を食っていたんだ。自分を守るためか?
悪魔もその様子を見てガッカリしたのか、なんだ、口だけ君か、と言わんばかりの冷たい視線を浴びせ、それから互いの目を合わせると、振り返ってそれぞれ、カニ歩きとバランス歩行で棟梁から離れて行き始めた。
それに気づいた棟梁は、かなりあせりながら、もはや箱を持っている悪魔だけの方しか見ずに叫んだ。
「待てって! 今食っちまうから! ねぇ! ほら!」
ちょっと弁当を傾けて見せた後、ようやくフルパワーの"食い"を見せ始めた棟梁は、その自分の食いの生み出す勢いに負けて肩口からバランスを崩し、もうそんなにねじれない老体を珍しくねじらせながら、空中に放り出された。
「あっ!!」
僕たちが叫んだ瞬間、悪魔の姿は一瞬にして消え、棟梁は腰から落下した。終わった。そう思った。
棟梁は顔を、まだかなり残っていたらしい惣菜まみれにして胸に弁当のガラを抱えながら、一階の便所が作られる予定の部分で、ピクリとも動かず目を閉じていた。この時はなんとなくそこまで深く考えず、全体的には「あーあ」という感じだった。
僕たちは手持ち無沙汰になり、誰が言うでもなく「弁当10、GO FIGHT」のフォーメーションをしき、それしか残っていない、普段はちょっと残す、飯の横の非常に狭いスペースにある漬物を全力でポリポリするしかなかった。
ややあって、野津田がピザポテトの袋を開ける音が青空に響いた。
漂ってきたクサ美味い、胸騒ぎの匂い。野津田の大きく開いた口の中でギザギザポテトが四つに八つに十六に割れて、またきつい匂いが立ちこめる。
僕はそこで初めて棟梁が死んだことがはっきりとわかった。間違いなく死んだんだ。もう弁当を食べる気を失くしていた。絶対、ピザポテトの匂いのせいだ。
「鮭がうめえうめえ……」
僕たち、下っ端ヤング大工マンたち(低学歴)は、地上で弁当を食い、弁当を褒めて午後もがんばれる力を底上げしながら、子供部屋が二つできる二階部分へ渡した梁の上を見上げた。
棟梁はただ一人、縦置きしたヤングマガジンほどの幅(正ヤンマガ幅)で弁当を立ち食いしていた。これは棟梁の七百八個(ななひゃくやっこ)ある大工奥義の一つ「高い分、美味い」である。
僕たち下っ端ヤング大工マンたちは、犬のように地べたに這いつくばって弁当を食いながら、棟梁の美しい立ち食い姿を惚れ惚れと見上げるしかない。一体どれほどの修行を重ねたら、あんな芸当ができるというのか。そもそも、ああいうことは本当にしておいた方がいいのか。
まあ、もしも、今の自分たちがあそこで立ち食いをしたら、ろくに食べた気がしないだろう。主力級のオカズをぼろぼろ下へこぼした挙げ句、その上へ真っ逆さまに落下、のり弁の香をかぎながら惨めに息絶えることになるに決まってる。頬っぺたに海苔が張り付き、早起きしたお母さんが作ったおにぎりの昼ごろの質感になるに決まってる。
ところが見てください、そう考えてみたら、試しにそういう思考になってみたら、棟梁は本当に凄い。こんなに凄いのにTVチャンピオンに出ないなんて自殺行為ではないかという気持ちで僕たちは箸を口に運んだ。早く食べ終えて、みんなでピザポテトが食べたい。そんな気持ちだった。
しかしその時、棟梁が立っている梁の両側、柱の元に悪魔がいることに気づいた。
い、いつの間に。
「やっぱり悪魔って突然、現れるものなんだ!」
しかもだよ。体全体が濃い紫シッポが矢印の悪魔がカニ歩きで少しずつ近づいてきているんだ。よく見ると、一階部分の柱の両側に、サークルKサンクスでもらえる星形の穴が散りばめられたフォークを大きくしたようなものが立てかけてあった。その無雑作な感じは実に目的をもって来たという気がした。気まぐれではなく、棟梁を狙って、遠くから、来たんだ。弁当が、うまい。
「あの悪魔ども、弁当を立ち食いしてる棟梁を挟み撃ちにする気だぞ」
誰かの小さな声が聞こえ、僕はその時一瞬遅れて、これはえらいことになったなと思って血の気が引いた。みんな目配せする。
「どうしよう」
棟梁はまだ黙々と立ち食いを続けている。やっぱり素直に下で食べておけばよかったんだ。カッコつけてあんなとこで立ち食いなんかして、名人気取りで、だから悪魔に目をつけられてしまうんだ。山頂で食うおにぎりがうまいのは、単に気持ちの問題だ。正直言って、棟梁は、パズドラとかをやってる若い僕たちと何を喋っていいかわからない自分が惨めになるから逃げを打って、あんなところで弁当を立ち食いしているんだ。
片方の悪魔は黄色に赤水玉の箱を持って、横向きでじりじり、時々ふらついて腰をかくかくさせながら、通勤中のような真顔で、弁当を食っている棟梁に近づいていく。もう片方の悪魔は手ぶらで、両手を横に伸ばして、時折大きく息を吐きながら進んでいる。その息は少し紫色をしていて、僕らの手前まで拡散してかき消えた。
なんとなく弁当を手やフタで隠しながら、僕たちは話した。
「しかし、あっちの悪魔は、かなり安定しているな」
「何も持っていないからだよ。偉いのは箱を持っている悪魔だ。もしかしたらとんでもなく重い箱かも知れないというのに」
「かなり、トレーニングを積んでいる悪魔なのかな。確かに重そうだ」
「少なくとも、弁当よりは重いよ……」
日頃から棟梁のことをよく思っていない野津田がボソリとつぶやいた。
みな、はそはそと冷たいごはんを口に運んだ。冷たいごはんは割り箸になんてよく引っかかるのだろう。はっきり割れて、泣きたいぐらいに絡みついてくる。
「あ、見ろ」
ようやく悪魔の接近に気づいた棟梁は、弁当に顔を半ば突っ込みながら、明らかに慌てた様子で交互に振り返り、目だけをチラチラ上げて悪魔を何度も見やった。
そこまでかっこ悪い棟梁を見るのは初めてだったけど、梁の上で悪魔に挟み撃ちされたのでは止むを得まい。しかし、その慌てぶりを普段こき使っている僕たちに見られていると知ったら、棟梁のハートはギザギザになってしまうだろう。子守唄なしで。
僕たちは目配せし、棟梁にわからないよう「弁当8、チラ見2」のフォーメーションをしいた。シャケ、ご飯、卵焼き、白身魚のフライ、棟梁しっかり、ご飯のリズムに箸が陰鬱な調べを奏でようとするが、小豆色をした薄いプラスチック容器が立てるくぐもった音は、白飯部分の重みに全て吸収されてしまうようだ。よく考えられている。
食ってる間に大メインクライマックス、悪魔が棟梁のところまで到着した。
箱を持った悪魔が、やはり真顔で、その箱を棟梁に差し出す。
「これは……悪魔一流の罠に違いないぞ」
「舌切り雀の、大きいつづらのパターンだ」
「真顔で渡されるプレゼントは、絶対に受け取っちゃだめだ。受け取った瞬間、大爆発だぞ」
僕たちはひそひそ口を挟んだが、棟梁はどうやら物につられて受け取ろうとしているようだった。どうにかこうにか受け取ろうと、持っている弁当をどうしようか迷った様子で、きょろきょろしたり、しゃがもうとしたり、おたおたしている。そして、ちょっと照れている。
「まずいぞ。棟梁は悪魔のプレゼントを受け取る気マンマンだ。照れている」
「でも大丈夫。梁の上では、さすがの棟梁も弁当を手放すことができないよ。だからプレゼントももらえない。これでよかったんだ」
そかそか! 僕らがホッとしたその時、棟梁は首を180度、それから体を180度のカートゥーン振り向きをかまし、手ぶらの悪魔に「弁当持ってて……」と言わんばかりにおずおずと差し出した。箸は、ご飯に斜めに突っ込んで動かないようにする生活感になっているようだ。
「ま、まずい! あれじゃあ悪魔の思うツボだ!」
「おい、静かにしろよ。聞こえちゃうだろっ。悪魔の耳は……良いっ!」
「でも、そんなこと言ってる場合か。みすみす悪魔の手にかかるより、ハートがギザギザになった方がずいぶんましだ」
「俺もそう思う。棟梁は欲張り。喩えるなら、動物園で勃起してるライオンだ。もらえるものは悪魔からでももらっちまおうなんて、これだから闇米を体に入れた世代はいやなんだ」
野津田だけはニヤニヤしてしまう笑顔を、顔の前に掲げた鮭で隠していた。そのとき、鮭が自重でパックリ割れてぶら下がった。その隙間から尖りに尖った口角と八重歯がのぞいていた。
「あ、悪魔……」
思わずつぶやいてしまった自分の口をあわてて栗で塞ぐ。弁当に栗が入っていて本当によかった。栗のおかげで命拾い。本来の旬は秋なのに、夏でも栗が流通していて助かった。
そして野津田は割れた鮭を下から丸呑みした。僕はご飯も口の中に放り込み、ぐっと堪えた。口の中が栗とご飯なのか。
そんなこんなで下で盛り上がっていた隙に、梁の上の棟梁は手ぶらの悪魔に弁当を持ってもらうのを断られたような感じになっており、またもおたおたして、そしてなんでだろう、ちょっと笑っていた。
手ぶらの悪魔はバランスを取ったまま、棟梁に向かってしきりに横に首を振っていた。一方で、背中からは、早く早くという感じで悪魔が箱を押し付けている。
押し付けるたびに、棟梁だけでなく悪魔の方の足元もふらつき、さすがにびびっている様子だ。バランスを取るため、早く受け取って欲しいのだろう。それなら手ぶらの悪魔は弁当を持ってくれたっていいのに、いったい、悪魔どもはプレゼントを受け取って欲しいのか、欲しくないのか。絶体絶命のピンチだ。
「あの状況じゃ、悪魔のサプライズ・プレゼントを早く受け取った方が安全だな」
「でも、一瞬でもいいから弁当を持ってもらわないことには棟梁はいつまでもプレゼントを受け取れないぞ」
弁当を両手に持ったまま体をくの字に折った棟梁の皺だらけの笑顔が、かんべんしてくださいよ、と口を動かしたように見えたが、黙っていた。黙っていたけど、
「一瞬でいいんですけど!」という棟梁の声が聞こえた。
それでも悪魔は頑なに、首を振っている。真っ直ぐ横に手を広げ、足を前と後ろに付けていた。もしかしてつま先を見たら、目印の線が引いてあるかも知れない。
そこで棟梁は何かひらめいたのか、悪魔に何か言った。二度目に言った時、僕たちにも、どうにか聞こえた。
「すぐ食っちゃうね」
悪魔はそこで、少し後ずさりして、棟梁が弁当を食べる分のスペースを作ってくれた。言葉が通じるんだ。棟梁はすぐさま勢いよくで食べ始めた。
「こんなの、すぐよ」
不安になったのか、棟梁は割りと大きい声で、箸を耳の横で天に向けて刺すような小さな動きをつけて言い放った。バカ! そんなにプレゼントが欲しいのか。僕は、あの箱の中身は、相手が悪魔ということや水玉の柄から言って、90%の確率でピエロもしくは松井秀喜のバブルヘッドが飛び出すビックリ箱だとあたりをつけていたので、棟梁がそんなに必死になるのがとても情けなく思えた。きっと、大福とか、ダウンジャケットとか、重たい灰皿などが入っていると思っているのだ。
「一瞬よ」
一瞬とか言いながら、棟梁の食はいまいち進んでいなかった。食べるやる気を見せているだけだ。あんまりバクバク食べると、やはりそこは細い梁の上、いくら棟梁といえどもフラフラしてしまうのはわかるが、もう少し冒険してもいいんじゃないだろうか。何のために、今まで毎日そこで弁当を食っていたんだ。自分を守るためか?
悪魔もその様子を見てガッカリしたのか、なんだ、口だけ君か、と言わんばかりの冷たい視線を浴びせ、それから互いの目を合わせると、振り返ってそれぞれ、カニ歩きとバランス歩行で棟梁から離れて行き始めた。
それに気づいた棟梁は、かなりあせりながら、もはや箱を持っている悪魔だけの方しか見ずに叫んだ。
「待てって! 今食っちまうから! ねぇ! ほら!」
ちょっと弁当を傾けて見せた後、ようやくフルパワーの"食い"を見せ始めた棟梁は、その自分の食いの生み出す勢いに負けて肩口からバランスを崩し、もうそんなにねじれない老体を珍しくねじらせながら、空中に放り出された。
「あっ!!」
僕たちが叫んだ瞬間、悪魔の姿は一瞬にして消え、棟梁は腰から落下した。終わった。そう思った。
棟梁は顔を、まだかなり残っていたらしい惣菜まみれにして胸に弁当のガラを抱えながら、一階の便所が作られる予定の部分で、ピクリとも動かず目を閉じていた。この時はなんとなくそこまで深く考えず、全体的には「あーあ」という感じだった。
僕たちは手持ち無沙汰になり、誰が言うでもなく「弁当10、GO FIGHT」のフォーメーションをしき、それしか残っていない、普段はちょっと残す、飯の横の非常に狭いスペースにある漬物を全力でポリポリするしかなかった。
ややあって、野津田がピザポテトの袋を開ける音が青空に響いた。
漂ってきたクサ美味い、胸騒ぎの匂い。野津田の大きく開いた口の中でギザギザポテトが四つに八つに十六に割れて、またきつい匂いが立ちこめる。
僕はそこで初めて棟梁が死んだことがはっきりとわかった。間違いなく死んだんだ。もう弁当を食べる気を失くしていた。絶対、ピザポテトの匂いのせいだ。