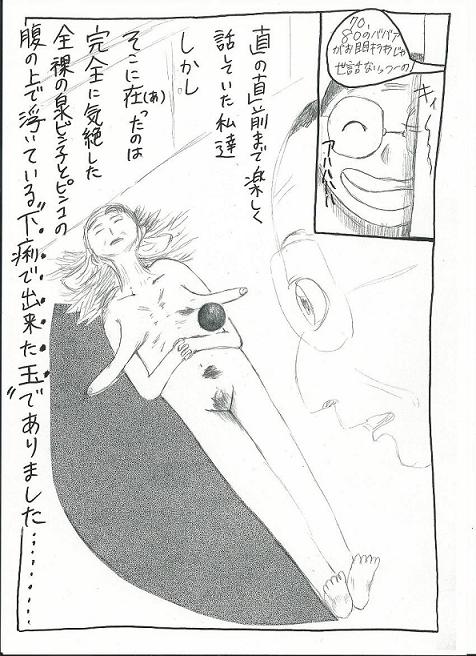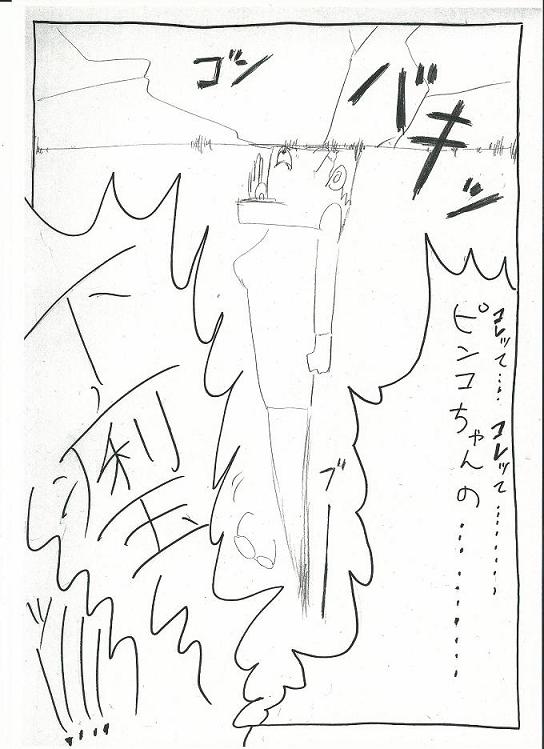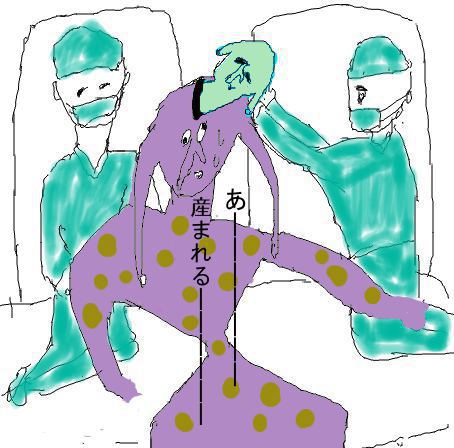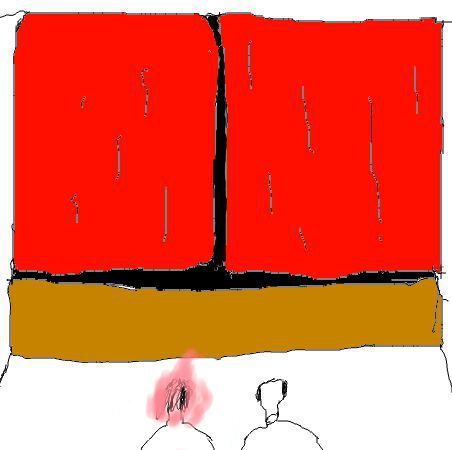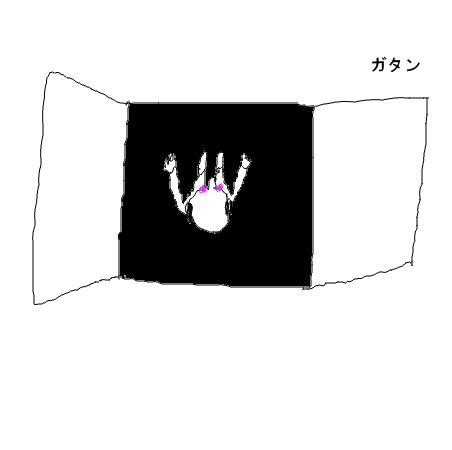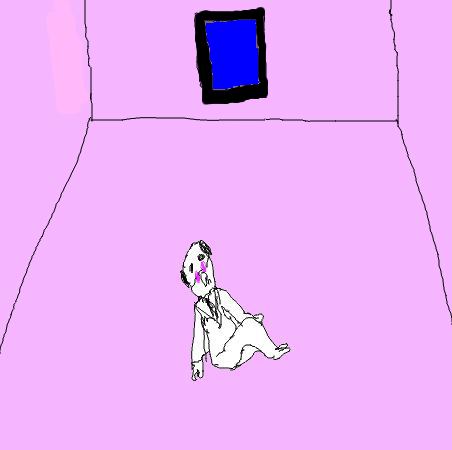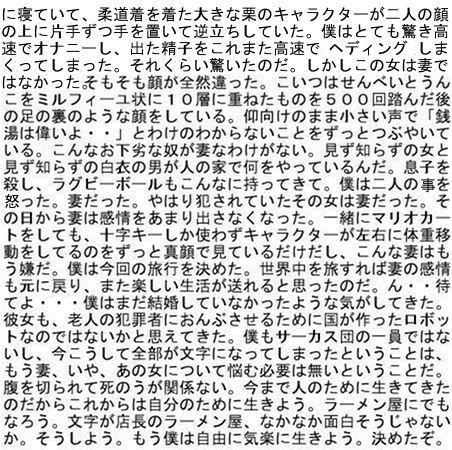ハッピーじゃないか
OK, Mr. Biegler, you've got your panties in evidence now.
『或る殺人』
5時には会社が終わるから、5時半には帰れる。帰れば母の作った夕飯があって、黙って食卓に着く。夕方のニュースを見ながら、準備してくれる母を待っている。小学生の時から変わらない。変わったことといえば、駅前の路上に駐車された迷惑な自転車を扱った特集を下世話だと思うぐらいだろうか。
そのうち、母が自分のものをお膳で運んできて座る。
「このピエトロのドレッシングさ」
「なに、気にくわない?」
「そんなこと言わない」
「じゃあ何よ」
いいね。そう言おうとしただけ。
「何よ」
レポーターは駅前の車通りの多い道沿いに密集して並んだ自転車と平行して走って行く。カメラはレポーターの正面からそれを追いかける。何十秒か走ってようやく自転車が途切れた。カメラが振り返ると、自転車の黒いカゴが空中に太く歪んだ筋をつくっている。遠くでかすかに踏切が鳴った。
「電車来ないときに撮ればいいのに」
母が言った。気にくわないことを気にしてしまうのはあなたの方じゃない。ここで何かもっとトゲの立ったことを言えば、私が同意しかねることをわかっているから、気にくわないことが始まってしまうのをわかっているから、核心を外して話をする。それでもやっぱり気にくわないところが口を突いてしまうのが、母らしく、女らしい。
「ほんとにね。でも、おっきい駅で電車多いし、何回かやってみて、もういいやってなったんじゃない」
「ああ、そっか。そうかもね」
私のこういう答えが母はたぶん気にくわないのだ。そしてこの人は、それを私のせいにする。もし母が我慢しきれず、自転車をとめて行った人達やわざとらしいレポーターを悪し様にあげつらったら、どう言ったろう。みんな仕事でやっているとまとめて味方をしたって納得しないだろう。同じようなことは何度もあったはずなのに、これといって思い出せない。
薄い豚肉で巻いたアスパラガスは私の好物。かみしめると、ほんのり甘い油がアスパラの水分と混じってさらさら口全体に広がってゆくのがわかる。母の料理は美味しい。私は何にもできないが、意地の悪い母の料理はこんなに美味しい。だから家でご飯を食べていると少し荷が重い。
画面ではまだ一塊になった自転車を映している。買い物袋の詰まった手押し車にとりすがるように歩く老人の視点からこの憂うべき問題が語られるみたい。同情は、誰かに伝えた瞬間その場で当てつけに変わる。私の同情を人に伝えようと思ったら、同情できた私もそこにいて、ニコニコ笑って邪魔をする。そして自分で慰まっている。私はこんなに同情できる女で、こんなに感じやすい心を持ったいい人なのよ。そんな奥底の思いが誰かを傷つける。
「これ、どこの駅?」
「埼玉だって言ってたじゃん、さっき」
「埼玉のどこ?」
「忘れた」
老人の背後に家のと同じエメラルド色の自転車が画面の隅に映し出されて、ぼやぼやと新しい考えが出始める。一台一台に持ち主が居て、みんながみんなそれを買うとき、気に入った色を選んだのだ。百台あれば百台に、千台あれば千台にそんな思いがちょっとも入っていないなんて考えられない。それは誰かの自転車だから。そういう色とりどりの思い入れがもっと極彩色の街に沈んで影を潜めて、人様に迷惑をかけているというその事実が上手く呑み込めなくて困った。
「あっ、見て。うちのと同じ色」
「そうだね」
つれない返事。私がスーパーにとめていた一家に一台の自転車を盗まれて、母が買いに行った時のことを思い出す。母は自転車の色を決めるアンケートを取って回った。あの時は兄もまだ家にいた。私は緑がいいと言ったのだ。兄はグレーがいいと言い、父は赤。母は緑を買ってきた。あんなに淡い緑だとは思わなくて、意外そうに笑ったら、母は腹を立てた。今では私も、それこそ同情してしまって気に入っているんだけど。
「話変わるけど、岡部さんのお母さん再婚したんだって」
母が思い出したように言って、私は驚く。春菜ちゃんは小学校の同級生だ。細いけどふっくらした顔と、愛嬌のあるガチャピンみたいな二重がかわいくて、それがお母さんとよく似ている子。
「えっ、春菜ちゃんのお母さん?」
「今日歩いてたらさ、声かけられて。そしたら岡部さんで。立ち話だったんだけど、再婚したのってすぐ言ってきて」
「えー、すごい」
「どういう関係の人だったと思う?」
「わかんない」
「小学校の同級生だって」
「わっ、詳しく聞いた?」
「同窓会で会って、それですぐに。離婚して、すぐ再婚」
「うれしそうだった?」
「うん」
「ふうん。なんだろう。ずっと好きだったのかな。初恋の人とか?」
「どうだろうね。実は好きだったみたいなこと言われて、燃え上がっちゃったのかもね。お互いに」
「春菜ちゃんはどう思ってるんだろ。ていうか、春菜ちゃんの話、なんか聞いた? 何してるんだろ」
「聞いてないけど、まだ青森にいるんじゃないの」
「そっか。寒くて大変だろうね」
そっかそっか。日々の淡々とした忙しさに翻弄されて春菜ちゃんが青森へ行ってたなんてそんなこと、私はすっかり忘れていた。何の仕事をしているんだっけ?
そうこうしている間に食べ終わって、さっさと片づけて部屋に退散しようと立ち上がる。同じような食器を抱えて、家族そろって何千回、何万回と通ったシンクに続くこの動線は、床板が少しへこんでいる。絶対そう。目をつぶっても歩けるそこには道ができていて、でも、この道を通っている限り、私はどこにも行けない。
自分の部屋でダラダラとネットをしているうちにお風呂が沸いた。
熱いお湯に身を委ねると、その身に背負い込んだ一日の疲れが溶け出してゆく気がする。だから私はいつも最初に入りたい。仕事のことなんか考えるのはやめるんだ。
新しく入ってきた後輩に声をかけたとき、そんな私の声かけすら侮辱ととった証として放り出された「一応こんな感じでやっときました」というひどく得意気でぶっきらぼうな声の響きとか、駅のホーム、私が待っているところに疲れた態度で歩いて来て、電車の訪れと共に、疲れたところへちょうどよかったと自然を装って割り込み乗車をするおばさんの赤い髪の白い生え際とか、そのおばさんがいるから読みたい週刊現代の下世話な車内広告に目を向けられないで、サンマーク出版の広告を全文覚えて脳みその中で持て余している混み合った車内のそんな感じとか。
私はグズでノロマで運が悪くて、人が集まったところで損をする。損しても、損をしていると思われるのはいやだし、恵まれなくても、恵まれないと思われるのはいやだ。紛れもない事実でも、それだけがいやだ。同情されるべきと自分で思っても、同情されるのがいやだ。
ほっとけと一つだけ願いを流した風呂上がり。バスタオルで念入りに体を拭いて、素裸で洗面所に立つこの時間。お風呂に入っている間に洗面所の明かりを母に消されてしまったせいでお風呂場のドア越しの薄明かりだけを横から浴びてぼんやり浮かび上がっている私の身体は綺麗だ。30過ぎても、お風呂上がりの私はバカみたいに綺麗だ。
私には密かな日課がある。それはみんなやっているんじゃないかと思うほど手軽にできて健康によく、おすすめである。洗濯機の上、少し厚手のTシャツの上に置かれた薄いピンクのパンティを見る。今日の後ろめたさ、明日への不安、見えないおりもの。馬鹿らしいのはわかってる。むんずとつかんで、洗面所の壁の一角に思い切り、力を込めて投げつける。大型の草食動物か何か殺すつもりで本当に思いきり。手加減なし。手加減したら、そのぶん何かが心に残る。
[広告] VPS
パンティは、ふぱんと壁にはりついて、何秒もそこで静止したように見えた。それから素直に、ピンクの微かな残像を壁に残して、素敵な音でするするストンと落ちていった。
何事もなかったように拾って足を通す。乙女のパンティは無敵で、傷一つ無い。
「上がったよ」
上はTシャツ一枚で居間に向かって声をかけると、母はテレビを見ながら舟をこいでいた。こんな時はすぐに起こさないと、どうして声をかけなかったのと憎まれ口を叩かれる。でも、知ったこっちゃない。声をかけなくても私は平気だ。あなたの場合。
午後11時頃、なんとなくお腹が空いたので買っておいたカップヌードルを持って部屋を出てキッチンへ向かう。
お腹の前に据えたカップヌードルと、座ってテレビを見ている母の間に体を入れて、キッチンへすべりこむ。どうせお湯を沸かすからバレるのに、相変わらずそんなことをしている。案の定、母が何か察知する。
「あんた、さっき食べたばっかりでまたそんなの食べて」
「いいの」
「寝る前に。太るからね」
「私が太らないの、知ってるでしょ」
「お母さんぐらいの年になって、ボディーブローのように効いてくるんだよ」
母から初めて聞いたそんな言い回し、どこで覚えたものなのか。いや、どうせテレビだけどね。苦笑できずになんか腹立つ。恥ずかしげもなく老いてゆく様も何もかも。
「私は違うもん」
「ほんと、いよいよ結婚できなくなるからね。自分で婚期を遅らせてさ」
「してたまるかい」
「またそういうこと言う。こっちは心配して言ってるんだから」
そこで打ち切り。逃げるように、でも湯をこぼすまいとそろそろ歩いて部屋に戻る。
テーブルの上にはさっきまで見ていた、運良くきちんと勤め始めて2年、もう少しで百万円貯まる青い貯金通帳が半分口を開けている。時間と自由を買うために打ち込まれた私だけの数字。その間に挟まれた○の数の風通しの良さを想像して、風呂上がりにパンティを壁に投げつけなくても済むのではという予感が走った。通帳をひっくり返して、これまで積み上げた重みで黙らせる。膝を立ててなるべく男らしくカップヌードルをすすったら、浅間山荘みたいだと思った。
二ヶ月後、百万円貯まっても相変わらずパンティはまだ投げている。でも、まだまだ壁はへこまないし、我が家のドレッシングは何も言わないのに二本連続ピエトロの和風となった。でも、私はだんだん飽き始めている。母は全然気付かない。何だってそう。いつもそう。本当に本当に気にくわない。
レッスン1は死ねボケナス
唯一あるドアのノブが音を立てて回った瞬間、喉元さんは教室全体が、自分のいつも会社で感じているような張り詰めて重苦しい心そのものになったように思われた。
ノブだけが回されたまま、ドアはしばらく動かなかった。やがてゆっくりと開き、襟の大きい緑色のスーツを着てきつい印象のメガネをかけた中年女性が入ってきて、いやに丁寧にドアを閉めた。背が低く、顔が小さいから、もともと大きめの襟が異様なほど広がって、顔を包み込むように見える。
部屋の真ん中、右端に座っていた喉元さんは、みんながみんなフジツボのように教室の後ろに詰めて着席している理由が一目でわかった。この先生はきっと怖い。大きな不安が吸い取りの悪い小さな胸に去来してみるみるうちに積もっていくから息が詰まる。
何も持たない先生は教卓に向かって斜めに立つと、いきなりしゃべり始めた。
「いいの、あんた達、今日もレッスン始めるわよ。根暗も根暗、ダンゴムシと同じ石裏からミミズの糞に塗れて這い出てきた生粋の根暗なんだろ。人前で喋れるようになりたいんだろ。知ってるよ。雁首揃えてそのために金払ってる。じゃあ精一杯やれよ。先生は、その金から払われる給料で、メチャクチャ性具を買ってます」
性具という言葉を知っていた喉元さんも、そんな文脈でそんな言葉が出てくるとは思わないのでわからないまま聞いていた。ただし一生懸命聞いていた。
「とにかく言いたいことは一つ。ぶちぶち文句言ってないで、やれよ。文句言ってる暇あったらやれ。動かせ口を。じゃあいつものように発声練習だよ。『死ねボケナス』からね」
みんながプリントを手にして席や姿勢を正す慌ただしい音が背中に聞こえたので、喉元さんは突然、一年分の勇気を奮い立たせてしまうことになった。
「あ、あの……」
自分の声が小さいのはわかっているから、同時におずおずと手を上げる。
「私……初めて…なんですけど……」
「何も聞こえない。あんたの声は何も聞こえない。防音ガラスの中にいるのか?」
前からの責めるような視線と、後ろからの哀れむような視線。その視線が下着以外の衣服を貫くようで、上半身がかゆくて痛い。喉元さんはくじけそうになり突っ伏して泣き出しそうになり、新たな言葉もすぐには出せない。同じことを繰り返すしかなかった。
「私……初めて…なんですけど……」
「だから?」先生のメガネは三角形に近いような形の赤いフレームのメガネだったが、それを外して目頭を押さえつけた。そしてそのままじっとしている。
「説明を……してください……」
「じゃあ最初から、私初めてなんですけど説明をしてください、って一息つかって言えばいいじゃないのよ。何で区切ったの。ベしゃりをリボ払いにしてどうすんの。何考えてんの。1人でエレベーターに乗ってる時とか何考えてんの。なんでちょっと…上を見てんの。あの、階数の、あれを見てんの? おい!!」
喉元さんは最後の怒鳴り声、先生が矢継ぎ早にツバを飛ばして喋る迫力に大ショックを受け、一人でエレベーターに乗ってる時に何を考えているか、そしてどうしてちょっと上を見るのか思い出そうとして、黙り込んでしまった。
「言っておこうか。説明はするわよ。しろって言われたら、こっちはする。しろって言われなかったら、しない。でも、するなって言われたら、それはしちゃうわよ。天邪鬼だから。だから、なんでも言ってみないと始まらないの。言えばいいでしょ。言えよ。無理でもいいから言え。そしたらなんか起こるわよ。説明して欲しいって思ってるだけじゃ落第よ。説明しろ説明しろって、念じてもダメ。念じてどうすんの。念じるな念じるな。言えよ。何のためのお口なんだ。かすかに胃酸の混じった空気を吐き出し続ける、それだけのためか?」
「説明をお願いします」喉元さんは少し声を張って言ったが、それでもひどく小さい、ささやくような声だった。
「いいよ、説明してやるよ。これはわかってると思うけど、ここでは、根暗で人前で喋れないお前ら、社会の蛆を腹に溜め込んだ食いっぱぐれの不適合者どものために、喋り方を教えてるのよ。それはもう独自なやり方でやってるのよ。そうじゃなきゃお前らみたいな、性根がマイナス思考の糞便にまみれた暗澹冥濛のグズは更生しないから。お前ら絶対、ご飯まずそうに食べるもんな。もそもそ食べるんだろ どうせ。気が滅入る。同じクラスじゃなくて本当に良かったというそんなお前らに、普通に喋り方教えたって時間と労力と口を潤す唾液の無駄よ。だからここでは悪口を教えてんの。わかるでしょ。悪口をレッスンすれば、人前で挨拶ぐらいできるようになるだろってこと、な? そういう考え。10教えたら糞バエの、3代続いた奇形児でも1は出来るだろってことよ。わかった?」
「あ……わかりました」と喉元さんはうなずいた。「すみません…」
「なんで謝んだよ ボケナスが。じゃあ、発声練習いくよ、はい、レッスン1……死ねボケナスッ!」
「あの……死ねボケナス」
生徒達が全員小声で繰り返した。喉元さんは、最初のボケナスは発声練習でなく自分に向けられた単なる悪口だったことにショックを隠せず、思わず涙ぐんで、何も言うことができなかった。
「小せえ小せえ、声小せ。お前らビックリマーク使ったことないだろ、マジで。絶対、未熟児だっただろ。あと、なんで全員、揃いも揃って最初に『あの……』ってつけんの? 相談してんのか? お前らは束になってもフンコロガシ1匹より使えないのに群れるな。あと新入り、やる気無いなら家帰って持ってるCDあいうえお順に並べてたら? お人形さんみたいな綺麗な顔しちゃって。そんな顔で黙り込んで生きれば一目置かれるかも知れないけど、そんなの私だったら全然楽しくないね。楽しくないし傍目にもおもしろくない」
喉元さんは何も言うことができなかったどころか、とうとう泣いてしまった。ますます背を丸め、涙を頬に伝わせるように、顔の角度を変えて、手の中に握り込むようにしたハンカチで押しつけるようにそっと拭き取る。化粧なんかしていないし、涙をこぼしてしまうよりはずっといい。こぼした涙は落ちる前に見てしまう。
先生はそんなことは気にしないで続けている。
「はい次、合う服ねえなら痩せろ肉団子!」
「合う服が無いなら…痩せろ、あの……お肉…お団子……」喉元さんもみなと一緒に勇気を振り絞り、コウモリがなんとか聞き取れるほどの声を出した。
先生は一人残らず歯切れの悪い様子に、すぐにでも殺したいという顔でにらみつけたが、続けた。生徒達は全員下を向いた。
「足広げて椅子に座るな無能が!」
「足を広げて椅子に座る…む…のう。が……」
「ツーペアではしゃぐな正月の凧あげブスが!!」
「ツーペアで、はしゃぐお正月の…凧あげ……」
「レッドキングみてえだな小顔だな~~~~ドクソ!!」
「死んでくれ木村祐一!!」
「安い黄色いワンタンみたいなチンコしやがって」
「安い黄色いワンタンみたいなチンコ……」
「頼むから死んでくれ木村祐一!!」
もうほとんど先生しか喋らなくなっていた。ワンタンのだけなぜ復唱したのかとやるせない怒りに堪忍袋の緒が切れた先生は、木村祐一の名残で頭の前で合わせていた手を解いて腰にあてると、床に粘りけのあるつばを吐いてホワイトボードの方を向き、蓋の取れていた黒いマジックを手に取り、もう出ないそれを、ホワイトボードに書き殴るようにして無茶苦茶に押し付けた。よく見ると、「死」というふうに何度も動かしていた。そして、腕を凄い速さ振り乱したまま、
「全員、殺し合えっ!」
と叫んだ。そして急に動きを止めて、振り返った。不気味なほど穏やかな顔をしていた。「お前達はなんなのか。便所コオロギが糞尿の飛沫を浴びて惨めに巨大化した存在なのか? もういいから次のレッスンに行くよ。おい、そこの坊主頭、誰だお前。今日はお前やってみな。死ね」
「は、はい……」中学生で学ランを着ている坊主頭の子は田中といったが、指名されてしまって本当につらいという今にも泣き出しそうな顔でひどくゆっくりと立ち上がった。
喉元さんは一瞬振り返ってその姿を確認すると、怒られやしないかとまた前を向く。ああ、あの子は私よりずっと年下なのに、本当にかわいそう…。
「イルカをぼろくそに言ってみな」
ひと事ながら、喉元さんは心臓が止まりそうになるほど驚いた。
これは、先ほどの、10教えればクズにも1は出来るだろう、という方針のもとに考え出されたレッスンである。動物として隙がないイルカに悪口を言えれば、人間のデブやハゲやワキガ、若いのに白髪がいっぱいある人、文句の多い童貞、などをぼろくそに言うことなど朝飯前、そういうことなのだ。
坊主の田中は口ごもり、どんどん顔色が悪くなり、網のないつるつるしたメロンみたいな薄緑色になってしまった。
「さっさとイルカをこきおろすんだよ!」
坊主の田中の体は、前後左右に小さくふらつきだした。
「早くしろ! イルカが逃げちまうよ!! 悪口を言え!! ああ、もう、殺す!!」
その言葉と、ドンと教卓を叩く音を聞いて、坊主の田中は朦朧とした顔でさらに大きくふらつき、そして、いきなりかがみこむと、机の上にあった自分の筆箱の中にゲロを吐き、口から糸を引きながら慌てた様子でポケットの中の小銭を机にばらまき、指をさしながらいくらあるか大急ぎで数え、それが終わると走り出し、一目散に背中をかきむしりながら、もう一方の手で窓を開けて、「328円!」と叫びながら飛び降りた。ラーメンも食べれやしねえ。
窓からは冬の冷たい風が吹き込み、生徒達は震えた。
この教室は2階にあるので、喉元さんはとても心配した。寒さのせいでなく震えながらまた涙があふれる。でも、イルカの悪口を言え、なんて本当の無理難題を言われたら、自分だってきっとああなってしまうだろうと考えた。
生徒達は、手を膝に置き、男の人はその手をグーにして、窓を閉めることもなく下を向いてずっと震えていた。
「正解は、イルカに対する悪口の一つの正解は、『高樹沙耶と仲いいんだって?』だよ。小谷実可子でもいける。イルカそのものに弱点がない場合、友人関係から突破口を見いだすんだ。これでイルカは寝られない、今日夜寝られないよ。右脳と左脳、交互に寝るって言ったって、そんなこと言われたら右脳でも左脳でも寝られない。わかったかい。胸に残る『ざまあみろ』という思いと一緒に、よーく覚えておくんだ」
先生はそう言うと出て行った。残された生徒達はますます寒くなっていく教室で、先生がいる時と同じようにじっと座っていた。眠れないイルカのことを考えた喉元さんの謂われのない興奮に高鳴る胸が落ち着く間もなく、先生は坊主の田中の襟をつかみ、引きずりながら帰ってきた。坊主の田中はそのまま乱暴に教室の隅に転がされた。意識はあるようだが、口はゲロまみれ、黄色がかった糸を口元に引きながら半笑いでこっちを向いて、目元につくったアザを濡らすように、流した涙が顔の上半分全体にだらしなく広がっていた。
先生は生徒達を見回した。生徒達は伏目がちに、世界のどこでもそうするように所在なさげに見返し、目が合いそうになる何秒も前からすぐ下を向いた。
「お前らは本当に、本当にダメだね……でも、あたしもそうだった」
先生は突然、神妙な顔で話し始め、机と机の間を歩いて行き、開いている窓をそっと閉めた。
「何を隠そう、あたしも、ここの卒業生なのさ」
その言葉を呑み込んで呼吸を止めた教室は水を打ったように静かになり、それぞれ下に向けられていた両の目の瞳孔がにわかに開きかける音まで聞こえるようだった。
「十年前の私は、引っ込み思案でシャイで、人に悪口を言うどころか、喋りかけてくる人間がとにかく怖くて、ローソンで箸をつけるかどうか聞かれただけで慌てふためいてハンカチを自分の口に詰め込んで、いったんハンカチを取り出し、そいつで顔をごしごし拭いたあと、問答無用で卒倒していたもんだよ。自分がいやでたまらなかった。変わりたかった。だからここに通い始めたんだよ。あんた達と同じようにね。最初は辛かった。地獄だった。硬水で薄めたゲロを朝晩飲むような日々だったよ」
伏し目がちだった教室中の顔が、だんだんと時計の短針が朝9時から12時に向かうように上がっていった。
喉元さんも涙で少し湿ったハンカチを握りしめる手を少しゆるめながら、先生の目を見ることが出来た。十年後の自分は何をしているだろう。十年前の自分に見上げられるような、そんな自分になっているだろうか。
坊主の田中も、いつの間にか体を半分起こして熱心に話を聞いていた。先ほど冷気にさらされた教室は、人間から出る淡い熱を少しずつためこみ始めている。
「一人立たされてペンギンの悪口を言えと言われた時は、ちぢこまって顔面蒼白になって自分のカバン目掛けて一筋細いゲロを吐いて、口から糸を引きながら大急ぎで財布の中のポイントカードを机の上に広げてたまり具合を確認した挙句の果てに走り出して、一目散に背中をかきむしりながら『引っ越す前のやつ!』と叫んで窓を突き破って飛び降りたもんだよ」
「だいたい俺と一緒だ!」坊主の田中は顔をキラキラ輝かせて大きな声を出した。そのあと、そんなに大きな声を出した自分を恥じるように頭をかいた。
「そうさ。名前は知らないけど、あんたのせいで思い出しちまったよ。あたしは、今はこんなに悪口が言えるようになった。だからみんな、絶対にあきらめちゃいけないよ。変わるんだ。誰だって、努力すればきっと、口の悪い人間になれるさ。大丈夫。その時を信じて、今はただ何も考えず、悪口を言うんだよ。一日中、どんな悪口を言ってやろうかと頭をめぐらすのさ。そして、誰かが目の前に立ったら、向こうが何か言う前に、思いついた全ての悪口を浴びせて先手を取るんだ。言い訳する暇も与えない集中砲火。言えばさっさと帰りゃいい。気持ちいいよ」
生徒達は今、初めてはっきりと顔を上げて、わずかに、背負いこんできたものの重さが消えていく心地よさを感じていた。自分たちを追い立てる声は、自分たちを呼ぶ声でもあったのだと、初めて気づいた。そんな声が存在するのだということも、初めて知った。
「悪口がいいのは、誰かに聞いてもらえること。それだけだからね」
喉元さんは、まだ初日だけれど、この教室に入って本当に良かったと思った。きっとこんな私でも、頑張れば、気兼ねなく人に、イルカにペンギンにハムスターに、おじいさんおばあさんに、「死ねボケナス」と言えるようになるんだ。そうすればみんな、私の話に耳を傾けてくれる。今はその気持ちが全然わからないけど、もしそうなれたら、先生のようになれたら、どんなに素敵なことだろう。
「勘違いしちゃいけないよ。そんなこともわからないで悪口を言う奴の目玉を見てご覧。見た目はきれいなもんだがどうだか。肺がんのジジイの肺に50年埋めてあった、焼き場で出てきたビー玉そのものだよ」
喉元さんはさっきとは別の涙があふれそうになるのに備えてハンカチを握りしめた。そうだ。私の話が聞いてもらえるなら、思った通りに口が動いて、空気が震えて、それが誰かの鼓膜に届いて、頭の中に巡るなら、それだけでどんなにいいだろう。それなら私はいくら嫌われたってかまわない。いやな気持ちになってかまわない。体をよじるのを見られるかも知れない。泣いてるところを見られるかも知れない。ひょっとしてそんな滅多にないものが見られるかも知れない。そのとき私は笑っているだろうか。傷ついているだろうか。
「誰かに聞いてもらうってそれ以上のことを求めるなら、そのあとのことは知らないよ。そこまでいったら、掃き溜めの鶴の糞になる。まして自分でそれを喰らうことだってあるだろうよ。あたしの知ったこっちゃないけどね」
悪口にはきっと特別な力がある。どんなことだって、どこからか、どんなふうにかわからないけど、知らせてしまう。覚悟がなければ、何を言っても意味が無い。私の口から出た言葉で人や世界がたわむのがわかったその瞬間の甘くて苦い絶望的な歓びと引き換えに、何を奪われたって構わない。私は私が嫌いでたまらなかった。悪口ばかり言ってる人も嫌いでたまらなかった。でも、羨ましくて仕方なかった。こんな時代に生きているんだもの、自分を傷つける術は自分で考えられたけれど、人を傷つける術はきっと人に習わなければ、あんまり上手に身につかない。その習い事がいやでいやで、私は何も言えなかったし、誰の話も本当には聞かないことにしていた。それこそずっと防音ガラスの中にいたようだった。でも私は、実はそれがとてもつまらないことだと、みんなの顔を見ていただけでわかっていたのだろう。そして今、やっと言葉が通る。
「じゃあ続けるよ、ボケナスども」
それからずっと小さな声でつぶやいていただけの喉元さんの声は、レッスンが終わる頃にはすっかり枯れてしまって、ささやくことも出来なくなった。でもその震えの無い喉に、不思議な充実感がおこげのように貼りついている。
こんなに楽しいのは初めて。
帰り支度をして我先にと帰って行く勝手知ったる仲間の後ろ姿を見ながら声にならない声を出すと、こんな気持ちの方をこそ滅多に口に出すべきではないように喉元さんには思えた。
ノブだけが回されたまま、ドアはしばらく動かなかった。やがてゆっくりと開き、襟の大きい緑色のスーツを着てきつい印象のメガネをかけた中年女性が入ってきて、いやに丁寧にドアを閉めた。背が低く、顔が小さいから、もともと大きめの襟が異様なほど広がって、顔を包み込むように見える。
部屋の真ん中、右端に座っていた喉元さんは、みんながみんなフジツボのように教室の後ろに詰めて着席している理由が一目でわかった。この先生はきっと怖い。大きな不安が吸い取りの悪い小さな胸に去来してみるみるうちに積もっていくから息が詰まる。
何も持たない先生は教卓に向かって斜めに立つと、いきなりしゃべり始めた。
「いいの、あんた達、今日もレッスン始めるわよ。根暗も根暗、ダンゴムシと同じ石裏からミミズの糞に塗れて這い出てきた生粋の根暗なんだろ。人前で喋れるようになりたいんだろ。知ってるよ。雁首揃えてそのために金払ってる。じゃあ精一杯やれよ。先生は、その金から払われる給料で、メチャクチャ性具を買ってます」
性具という言葉を知っていた喉元さんも、そんな文脈でそんな言葉が出てくるとは思わないのでわからないまま聞いていた。ただし一生懸命聞いていた。
「とにかく言いたいことは一つ。ぶちぶち文句言ってないで、やれよ。文句言ってる暇あったらやれ。動かせ口を。じゃあいつものように発声練習だよ。『死ねボケナス』からね」
みんながプリントを手にして席や姿勢を正す慌ただしい音が背中に聞こえたので、喉元さんは突然、一年分の勇気を奮い立たせてしまうことになった。
「あ、あの……」
自分の声が小さいのはわかっているから、同時におずおずと手を上げる。
「私……初めて…なんですけど……」
「何も聞こえない。あんたの声は何も聞こえない。防音ガラスの中にいるのか?」
前からの責めるような視線と、後ろからの哀れむような視線。その視線が下着以外の衣服を貫くようで、上半身がかゆくて痛い。喉元さんはくじけそうになり突っ伏して泣き出しそうになり、新たな言葉もすぐには出せない。同じことを繰り返すしかなかった。
「私……初めて…なんですけど……」
「だから?」先生のメガネは三角形に近いような形の赤いフレームのメガネだったが、それを外して目頭を押さえつけた。そしてそのままじっとしている。
「説明を……してください……」
「じゃあ最初から、私初めてなんですけど説明をしてください、って一息つかって言えばいいじゃないのよ。何で区切ったの。ベしゃりをリボ払いにしてどうすんの。何考えてんの。1人でエレベーターに乗ってる時とか何考えてんの。なんでちょっと…上を見てんの。あの、階数の、あれを見てんの? おい!!」
喉元さんは最後の怒鳴り声、先生が矢継ぎ早にツバを飛ばして喋る迫力に大ショックを受け、一人でエレベーターに乗ってる時に何を考えているか、そしてどうしてちょっと上を見るのか思い出そうとして、黙り込んでしまった。
「言っておこうか。説明はするわよ。しろって言われたら、こっちはする。しろって言われなかったら、しない。でも、するなって言われたら、それはしちゃうわよ。天邪鬼だから。だから、なんでも言ってみないと始まらないの。言えばいいでしょ。言えよ。無理でもいいから言え。そしたらなんか起こるわよ。説明して欲しいって思ってるだけじゃ落第よ。説明しろ説明しろって、念じてもダメ。念じてどうすんの。念じるな念じるな。言えよ。何のためのお口なんだ。かすかに胃酸の混じった空気を吐き出し続ける、それだけのためか?」
「説明をお願いします」喉元さんは少し声を張って言ったが、それでもひどく小さい、ささやくような声だった。
「いいよ、説明してやるよ。これはわかってると思うけど、ここでは、根暗で人前で喋れないお前ら、社会の蛆を腹に溜め込んだ食いっぱぐれの不適合者どものために、喋り方を教えてるのよ。それはもう独自なやり方でやってるのよ。そうじゃなきゃお前らみたいな、性根がマイナス思考の糞便にまみれた暗澹冥濛のグズは更生しないから。お前ら絶対、ご飯まずそうに食べるもんな。もそもそ食べるんだろ どうせ。気が滅入る。同じクラスじゃなくて本当に良かったというそんなお前らに、普通に喋り方教えたって時間と労力と口を潤す唾液の無駄よ。だからここでは悪口を教えてんの。わかるでしょ。悪口をレッスンすれば、人前で挨拶ぐらいできるようになるだろってこと、な? そういう考え。10教えたら糞バエの、3代続いた奇形児でも1は出来るだろってことよ。わかった?」
「あ……わかりました」と喉元さんはうなずいた。「すみません…」
「なんで謝んだよ ボケナスが。じゃあ、発声練習いくよ、はい、レッスン1……死ねボケナスッ!」
「あの……死ねボケナス」
生徒達が全員小声で繰り返した。喉元さんは、最初のボケナスは発声練習でなく自分に向けられた単なる悪口だったことにショックを隠せず、思わず涙ぐんで、何も言うことができなかった。
「小せえ小せえ、声小せ。お前らビックリマーク使ったことないだろ、マジで。絶対、未熟児だっただろ。あと、なんで全員、揃いも揃って最初に『あの……』ってつけんの? 相談してんのか? お前らは束になってもフンコロガシ1匹より使えないのに群れるな。あと新入り、やる気無いなら家帰って持ってるCDあいうえお順に並べてたら? お人形さんみたいな綺麗な顔しちゃって。そんな顔で黙り込んで生きれば一目置かれるかも知れないけど、そんなの私だったら全然楽しくないね。楽しくないし傍目にもおもしろくない」
喉元さんは何も言うことができなかったどころか、とうとう泣いてしまった。ますます背を丸め、涙を頬に伝わせるように、顔の角度を変えて、手の中に握り込むようにしたハンカチで押しつけるようにそっと拭き取る。化粧なんかしていないし、涙をこぼしてしまうよりはずっといい。こぼした涙は落ちる前に見てしまう。
先生はそんなことは気にしないで続けている。
「はい次、合う服ねえなら痩せろ肉団子!」
「合う服が無いなら…痩せろ、あの……お肉…お団子……」喉元さんもみなと一緒に勇気を振り絞り、コウモリがなんとか聞き取れるほどの声を出した。
先生は一人残らず歯切れの悪い様子に、すぐにでも殺したいという顔でにらみつけたが、続けた。生徒達は全員下を向いた。
「足広げて椅子に座るな無能が!」
「足を広げて椅子に座る…む…のう。が……」
「ツーペアではしゃぐな正月の凧あげブスが!!」
「ツーペアで、はしゃぐお正月の…凧あげ……」
「レッドキングみてえだな小顔だな~~~~ドクソ!!」
「死んでくれ木村祐一!!」
「安い黄色いワンタンみたいなチンコしやがって」
「安い黄色いワンタンみたいなチンコ……」
「頼むから死んでくれ木村祐一!!」
もうほとんど先生しか喋らなくなっていた。ワンタンのだけなぜ復唱したのかとやるせない怒りに堪忍袋の緒が切れた先生は、木村祐一の名残で頭の前で合わせていた手を解いて腰にあてると、床に粘りけのあるつばを吐いてホワイトボードの方を向き、蓋の取れていた黒いマジックを手に取り、もう出ないそれを、ホワイトボードに書き殴るようにして無茶苦茶に押し付けた。よく見ると、「死」というふうに何度も動かしていた。そして、腕を凄い速さ振り乱したまま、
「全員、殺し合えっ!」
と叫んだ。そして急に動きを止めて、振り返った。不気味なほど穏やかな顔をしていた。「お前達はなんなのか。便所コオロギが糞尿の飛沫を浴びて惨めに巨大化した存在なのか? もういいから次のレッスンに行くよ。おい、そこの坊主頭、誰だお前。今日はお前やってみな。死ね」
「は、はい……」中学生で学ランを着ている坊主頭の子は田中といったが、指名されてしまって本当につらいという今にも泣き出しそうな顔でひどくゆっくりと立ち上がった。
喉元さんは一瞬振り返ってその姿を確認すると、怒られやしないかとまた前を向く。ああ、あの子は私よりずっと年下なのに、本当にかわいそう…。
「イルカをぼろくそに言ってみな」
ひと事ながら、喉元さんは心臓が止まりそうになるほど驚いた。
これは、先ほどの、10教えればクズにも1は出来るだろう、という方針のもとに考え出されたレッスンである。動物として隙がないイルカに悪口を言えれば、人間のデブやハゲやワキガ、若いのに白髪がいっぱいある人、文句の多い童貞、などをぼろくそに言うことなど朝飯前、そういうことなのだ。
坊主の田中は口ごもり、どんどん顔色が悪くなり、網のないつるつるしたメロンみたいな薄緑色になってしまった。
「さっさとイルカをこきおろすんだよ!」
坊主の田中の体は、前後左右に小さくふらつきだした。
「早くしろ! イルカが逃げちまうよ!! 悪口を言え!! ああ、もう、殺す!!」
その言葉と、ドンと教卓を叩く音を聞いて、坊主の田中は朦朧とした顔でさらに大きくふらつき、そして、いきなりかがみこむと、机の上にあった自分の筆箱の中にゲロを吐き、口から糸を引きながら慌てた様子でポケットの中の小銭を机にばらまき、指をさしながらいくらあるか大急ぎで数え、それが終わると走り出し、一目散に背中をかきむしりながら、もう一方の手で窓を開けて、「328円!」と叫びながら飛び降りた。ラーメンも食べれやしねえ。
窓からは冬の冷たい風が吹き込み、生徒達は震えた。
この教室は2階にあるので、喉元さんはとても心配した。寒さのせいでなく震えながらまた涙があふれる。でも、イルカの悪口を言え、なんて本当の無理難題を言われたら、自分だってきっとああなってしまうだろうと考えた。
生徒達は、手を膝に置き、男の人はその手をグーにして、窓を閉めることもなく下を向いてずっと震えていた。
「正解は、イルカに対する悪口の一つの正解は、『高樹沙耶と仲いいんだって?』だよ。小谷実可子でもいける。イルカそのものに弱点がない場合、友人関係から突破口を見いだすんだ。これでイルカは寝られない、今日夜寝られないよ。右脳と左脳、交互に寝るって言ったって、そんなこと言われたら右脳でも左脳でも寝られない。わかったかい。胸に残る『ざまあみろ』という思いと一緒に、よーく覚えておくんだ」
先生はそう言うと出て行った。残された生徒達はますます寒くなっていく教室で、先生がいる時と同じようにじっと座っていた。眠れないイルカのことを考えた喉元さんの謂われのない興奮に高鳴る胸が落ち着く間もなく、先生は坊主の田中の襟をつかみ、引きずりながら帰ってきた。坊主の田中はそのまま乱暴に教室の隅に転がされた。意識はあるようだが、口はゲロまみれ、黄色がかった糸を口元に引きながら半笑いでこっちを向いて、目元につくったアザを濡らすように、流した涙が顔の上半分全体にだらしなく広がっていた。
先生は生徒達を見回した。生徒達は伏目がちに、世界のどこでもそうするように所在なさげに見返し、目が合いそうになる何秒も前からすぐ下を向いた。
「お前らは本当に、本当にダメだね……でも、あたしもそうだった」
先生は突然、神妙な顔で話し始め、机と机の間を歩いて行き、開いている窓をそっと閉めた。
「何を隠そう、あたしも、ここの卒業生なのさ」
その言葉を呑み込んで呼吸を止めた教室は水を打ったように静かになり、それぞれ下に向けられていた両の目の瞳孔がにわかに開きかける音まで聞こえるようだった。
「十年前の私は、引っ込み思案でシャイで、人に悪口を言うどころか、喋りかけてくる人間がとにかく怖くて、ローソンで箸をつけるかどうか聞かれただけで慌てふためいてハンカチを自分の口に詰め込んで、いったんハンカチを取り出し、そいつで顔をごしごし拭いたあと、問答無用で卒倒していたもんだよ。自分がいやでたまらなかった。変わりたかった。だからここに通い始めたんだよ。あんた達と同じようにね。最初は辛かった。地獄だった。硬水で薄めたゲロを朝晩飲むような日々だったよ」
伏し目がちだった教室中の顔が、だんだんと時計の短針が朝9時から12時に向かうように上がっていった。
喉元さんも涙で少し湿ったハンカチを握りしめる手を少しゆるめながら、先生の目を見ることが出来た。十年後の自分は何をしているだろう。十年前の自分に見上げられるような、そんな自分になっているだろうか。
坊主の田中も、いつの間にか体を半分起こして熱心に話を聞いていた。先ほど冷気にさらされた教室は、人間から出る淡い熱を少しずつためこみ始めている。
「一人立たされてペンギンの悪口を言えと言われた時は、ちぢこまって顔面蒼白になって自分のカバン目掛けて一筋細いゲロを吐いて、口から糸を引きながら大急ぎで財布の中のポイントカードを机の上に広げてたまり具合を確認した挙句の果てに走り出して、一目散に背中をかきむしりながら『引っ越す前のやつ!』と叫んで窓を突き破って飛び降りたもんだよ」
「だいたい俺と一緒だ!」坊主の田中は顔をキラキラ輝かせて大きな声を出した。そのあと、そんなに大きな声を出した自分を恥じるように頭をかいた。
「そうさ。名前は知らないけど、あんたのせいで思い出しちまったよ。あたしは、今はこんなに悪口が言えるようになった。だからみんな、絶対にあきらめちゃいけないよ。変わるんだ。誰だって、努力すればきっと、口の悪い人間になれるさ。大丈夫。その時を信じて、今はただ何も考えず、悪口を言うんだよ。一日中、どんな悪口を言ってやろうかと頭をめぐらすのさ。そして、誰かが目の前に立ったら、向こうが何か言う前に、思いついた全ての悪口を浴びせて先手を取るんだ。言い訳する暇も与えない集中砲火。言えばさっさと帰りゃいい。気持ちいいよ」
生徒達は今、初めてはっきりと顔を上げて、わずかに、背負いこんできたものの重さが消えていく心地よさを感じていた。自分たちを追い立てる声は、自分たちを呼ぶ声でもあったのだと、初めて気づいた。そんな声が存在するのだということも、初めて知った。
「悪口がいいのは、誰かに聞いてもらえること。それだけだからね」
喉元さんは、まだ初日だけれど、この教室に入って本当に良かったと思った。きっとこんな私でも、頑張れば、気兼ねなく人に、イルカにペンギンにハムスターに、おじいさんおばあさんに、「死ねボケナス」と言えるようになるんだ。そうすればみんな、私の話に耳を傾けてくれる。今はその気持ちが全然わからないけど、もしそうなれたら、先生のようになれたら、どんなに素敵なことだろう。
「勘違いしちゃいけないよ。そんなこともわからないで悪口を言う奴の目玉を見てご覧。見た目はきれいなもんだがどうだか。肺がんのジジイの肺に50年埋めてあった、焼き場で出てきたビー玉そのものだよ」
喉元さんはさっきとは別の涙があふれそうになるのに備えてハンカチを握りしめた。そうだ。私の話が聞いてもらえるなら、思った通りに口が動いて、空気が震えて、それが誰かの鼓膜に届いて、頭の中に巡るなら、それだけでどんなにいいだろう。それなら私はいくら嫌われたってかまわない。いやな気持ちになってかまわない。体をよじるのを見られるかも知れない。泣いてるところを見られるかも知れない。ひょっとしてそんな滅多にないものが見られるかも知れない。そのとき私は笑っているだろうか。傷ついているだろうか。
「誰かに聞いてもらうってそれ以上のことを求めるなら、そのあとのことは知らないよ。そこまでいったら、掃き溜めの鶴の糞になる。まして自分でそれを喰らうことだってあるだろうよ。あたしの知ったこっちゃないけどね」
悪口にはきっと特別な力がある。どんなことだって、どこからか、どんなふうにかわからないけど、知らせてしまう。覚悟がなければ、何を言っても意味が無い。私の口から出た言葉で人や世界がたわむのがわかったその瞬間の甘くて苦い絶望的な歓びと引き換えに、何を奪われたって構わない。私は私が嫌いでたまらなかった。悪口ばかり言ってる人も嫌いでたまらなかった。でも、羨ましくて仕方なかった。こんな時代に生きているんだもの、自分を傷つける術は自分で考えられたけれど、人を傷つける術はきっと人に習わなければ、あんまり上手に身につかない。その習い事がいやでいやで、私は何も言えなかったし、誰の話も本当には聞かないことにしていた。それこそずっと防音ガラスの中にいたようだった。でも私は、実はそれがとてもつまらないことだと、みんなの顔を見ていただけでわかっていたのだろう。そして今、やっと言葉が通る。
「じゃあ続けるよ、ボケナスども」
それからずっと小さな声でつぶやいていただけの喉元さんの声は、レッスンが終わる頃にはすっかり枯れてしまって、ささやくことも出来なくなった。でもその震えの無い喉に、不思議な充実感がおこげのように貼りついている。
こんなに楽しいのは初めて。
帰り支度をして我先にと帰って行く勝手知ったる仲間の後ろ姿を見ながら声にならない声を出すと、こんな気持ちの方をこそ滅多に口に出すべきではないように喉元さんには思えた。