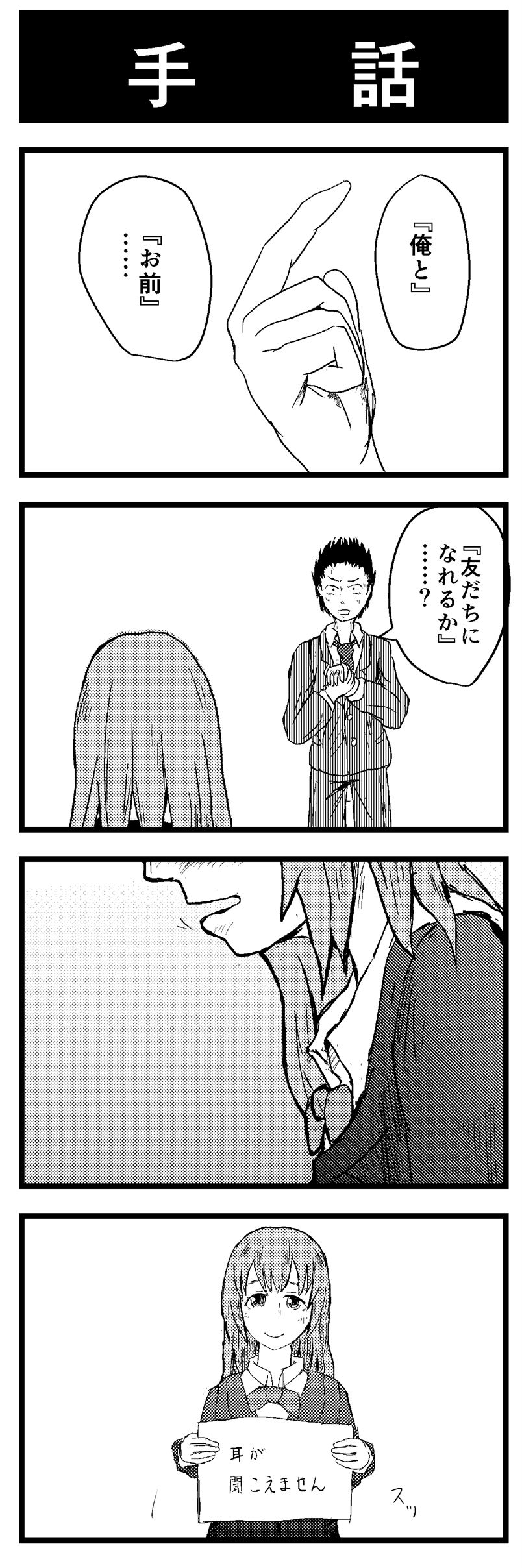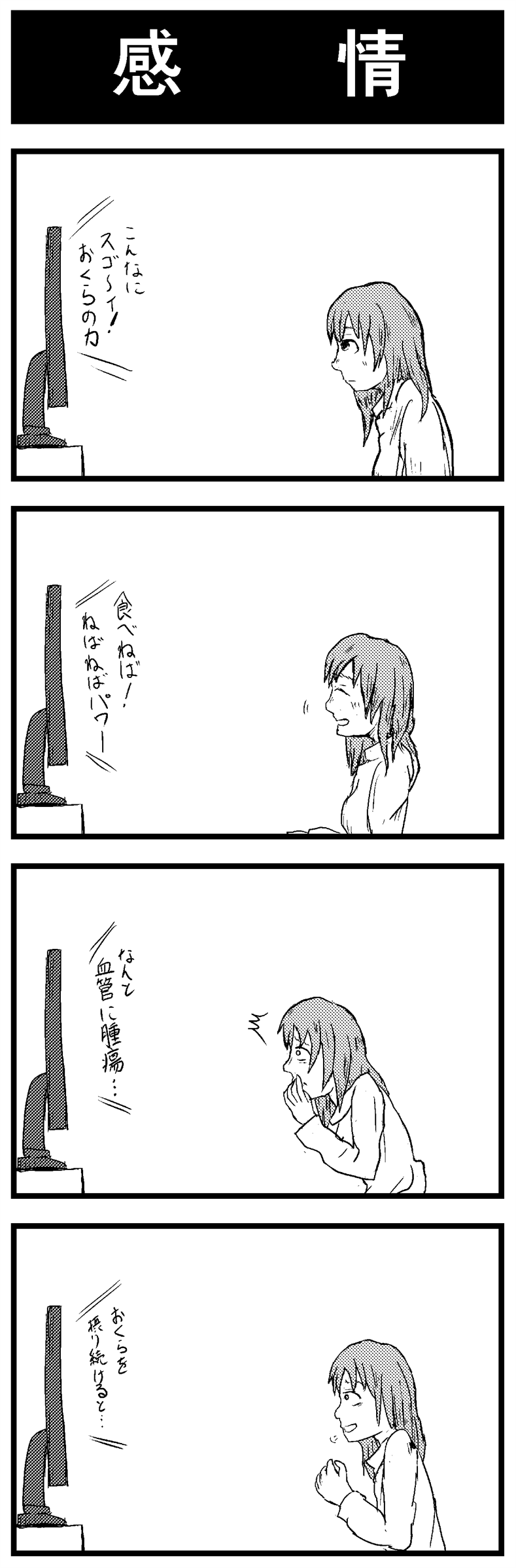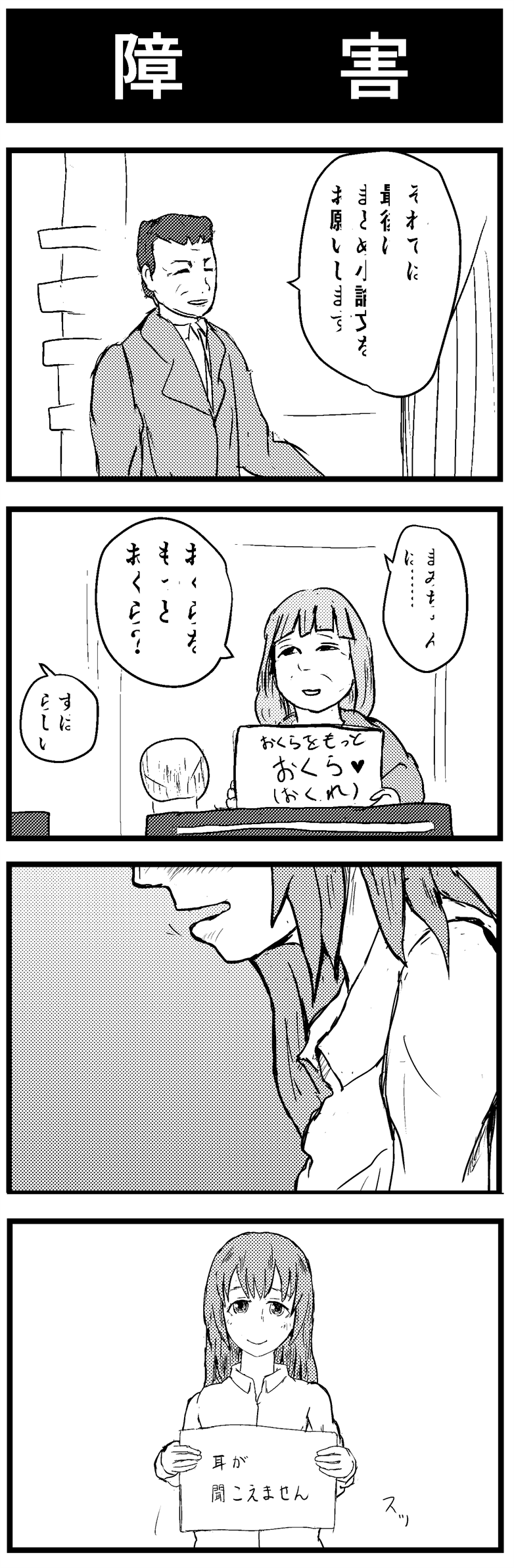予感おやじ
「…来る」
予感おやじは確信した。昔からそうだった。彼は、人一倍感受性が強く、来るかどうかがよく分かった。記憶に残っている範囲で最初に予感したのは、幼稚園の年中さんの頃だった。年中さんになると、年少さんのときは入ることが許されなかったプールが解禁される。幼稚園の施設内に備え付けられている、小さく、底の浅いプールだ。同級生は皆プールに大興奮だった。幼少期の予感おやじも例外ではなく、同級生と水かけっこをしたり、浅い場所を這ったりして遊んでいた。水しぶきの冷たさや、地上とはまた違った体への抵抗が新鮮である。我を忘れて楽しんでいた。そんな矢先である。
「…来る」
直観が脳裏をよぎる。思わず空を見る。夏の空は、能天気とも言えるほどに青い。白い雲とのコントラストが美しい。時間が止まっているかのような感覚を覚える。だが、幼少期の予感おやじははっきりと感じていた。来るのだ、と。
記憶はそこで途切れ、実際に来たところや、来た後にどうなったかということは、一切覚えていない。ただ、彼の両親の話や当時の記録を見る限り、予感の通り来ていたらしい。それも、予感おやじが年中さんだった時期とちょうど合致している。
「こうしてはいられない」
予感おやじは、すぐにパターの練習をやめた。彼も、予感おやじと言えどおやじには違いないので、ゴルフをする。家でも気軽に練習できるように、パッティングのグッズをリビングに置いている。道を塞ぐように縦に伸びているため、妻からは大変不評である。そんなことはいいのだ。長男と長女に電話をかけなくては。
予感おやじには二人の子供がいる。予感しない女性との間に設けた。長男は、地元の公務員として就職し、現在は寮に入っている。長女は上京し、都内の大学で心理学を専攻している。
「予感?」
おやじのそわそわを見透かしたかのように、妻が自分の部屋から顔を出した。
「そうだよ」
予感おやじは携帯で長男の連絡先を探しながら答える。
「本当によく当たるもんねえ。来るかどうか。不思議だよねえ」
「自分でもそう思っている」
「結婚して25年経つけどさ、あなたって何なの?」
予感おやじは答えられない。こちらが教えてほしいくらいだ。来る。来る。来る。予感。予感。予感。的中。予感。予感。的中。この人生は常に予感と共にあった。どうしてなのかは分からない。だけど、受け入れるしかないではないか。予感してしまうものは止められないのだから。
予感おやじは長男に電話をかける。日曜日の朝だから、出かけていなければ家にいるはずだ。数コールの後、声が聞こえた。
「もしもし?」
「おお。お父さんだよ。元気だったか」
「珍しいね、電話かけてくるなんて」
「ちょっと急ぎの用事があってな」
「どうしたの?」
長男の声が曇る。予感おやじはゆっくり含ませるように言った。
「実はな…来るんだ」
「来るって…あの?予感で分かったの?」
「そうだよ」
「気のせいとかってことはないの?」
「生憎、この予感は生まれてから一度も外れたことがない。実績があるんだ」
「…分かった。準備しておく」
長男はそう言って電話を切った。次は長女だ。
「もしもし」
ずぼらな長男と違い、長女は1コールで電話に出る。
「もしもし」
「おお。お父さんだよ。久しぶり」
「どうしたの?来るの?」
察しがいい。妻に似たのだろう。
「ああそうだ。来るよ」
「予感?」
「そうだよ」
「毎回すごいよね。生まれてから18年経つけどさ、お父さんって何なの?」
前言撤回だ。長女は妻に似たのではない。妻そのものかもしれない。二人で作った子供なのに、私の遺伝子はどこへ行ってしまったのか。彼方か。
「…とにかく、来るから、用意しておくように」
予感おやじは強引に電話を切った。一日に二度も存在の根源を問われてしまった。少し動揺している。こんなときは手を動かすのが一番だ。常備菜としてほうれん草のおひたしを作っておくことにした。
台所へ繰り出し、ほうれん草を水洗いする。沸騰したお湯で茹でてアク抜きをした後、ザルに移して冷ます。この後、めんつゆと混ぜ合わせて適当な大きさに切れば出来上がりだ。鰹節をかけようか考えるとわくわくしてくる。予感おやじは、若干高揚した心持ちで何気なく窓の方を見やると、来ていた。
予感おやじは確信した。昔からそうだった。彼は、人一倍感受性が強く、来るかどうかがよく分かった。記憶に残っている範囲で最初に予感したのは、幼稚園の年中さんの頃だった。年中さんになると、年少さんのときは入ることが許されなかったプールが解禁される。幼稚園の施設内に備え付けられている、小さく、底の浅いプールだ。同級生は皆プールに大興奮だった。幼少期の予感おやじも例外ではなく、同級生と水かけっこをしたり、浅い場所を這ったりして遊んでいた。水しぶきの冷たさや、地上とはまた違った体への抵抗が新鮮である。我を忘れて楽しんでいた。そんな矢先である。
「…来る」
直観が脳裏をよぎる。思わず空を見る。夏の空は、能天気とも言えるほどに青い。白い雲とのコントラストが美しい。時間が止まっているかのような感覚を覚える。だが、幼少期の予感おやじははっきりと感じていた。来るのだ、と。
記憶はそこで途切れ、実際に来たところや、来た後にどうなったかということは、一切覚えていない。ただ、彼の両親の話や当時の記録を見る限り、予感の通り来ていたらしい。それも、予感おやじが年中さんだった時期とちょうど合致している。
「こうしてはいられない」
予感おやじは、すぐにパターの練習をやめた。彼も、予感おやじと言えどおやじには違いないので、ゴルフをする。家でも気軽に練習できるように、パッティングのグッズをリビングに置いている。道を塞ぐように縦に伸びているため、妻からは大変不評である。そんなことはいいのだ。長男と長女に電話をかけなくては。
予感おやじには二人の子供がいる。予感しない女性との間に設けた。長男は、地元の公務員として就職し、現在は寮に入っている。長女は上京し、都内の大学で心理学を専攻している。
「予感?」
おやじのそわそわを見透かしたかのように、妻が自分の部屋から顔を出した。
「そうだよ」
予感おやじは携帯で長男の連絡先を探しながら答える。
「本当によく当たるもんねえ。来るかどうか。不思議だよねえ」
「自分でもそう思っている」
「結婚して25年経つけどさ、あなたって何なの?」
予感おやじは答えられない。こちらが教えてほしいくらいだ。来る。来る。来る。予感。予感。予感。的中。予感。予感。的中。この人生は常に予感と共にあった。どうしてなのかは分からない。だけど、受け入れるしかないではないか。予感してしまうものは止められないのだから。
予感おやじは長男に電話をかける。日曜日の朝だから、出かけていなければ家にいるはずだ。数コールの後、声が聞こえた。
「もしもし?」
「おお。お父さんだよ。元気だったか」
「珍しいね、電話かけてくるなんて」
「ちょっと急ぎの用事があってな」
「どうしたの?」
長男の声が曇る。予感おやじはゆっくり含ませるように言った。
「実はな…来るんだ」
「来るって…あの?予感で分かったの?」
「そうだよ」
「気のせいとかってことはないの?」
「生憎、この予感は生まれてから一度も外れたことがない。実績があるんだ」
「…分かった。準備しておく」
長男はそう言って電話を切った。次は長女だ。
「もしもし」
ずぼらな長男と違い、長女は1コールで電話に出る。
「もしもし」
「おお。お父さんだよ。久しぶり」
「どうしたの?来るの?」
察しがいい。妻に似たのだろう。
「ああそうだ。来るよ」
「予感?」
「そうだよ」
「毎回すごいよね。生まれてから18年経つけどさ、お父さんって何なの?」
前言撤回だ。長女は妻に似たのではない。妻そのものかもしれない。二人で作った子供なのに、私の遺伝子はどこへ行ってしまったのか。彼方か。
「…とにかく、来るから、用意しておくように」
予感おやじは強引に電話を切った。一日に二度も存在の根源を問われてしまった。少し動揺している。こんなときは手を動かすのが一番だ。常備菜としてほうれん草のおひたしを作っておくことにした。
台所へ繰り出し、ほうれん草を水洗いする。沸騰したお湯で茹でてアク抜きをした後、ザルに移して冷ます。この後、めんつゆと混ぜ合わせて適当な大きさに切れば出来上がりだ。鰹節をかけようか考えるとわくわくしてくる。予感おやじは、若干高揚した心持ちで何気なく窓の方を見やると、来ていた。