ルイージマンション2からの問題
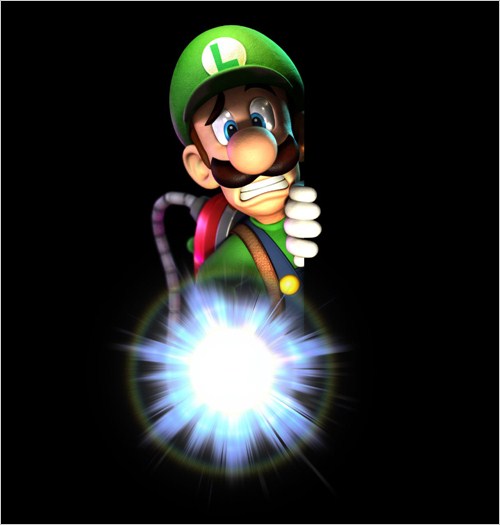
突然ですが、ここでルイージマンション2からの問題。
「終わった後に全て話したいが、終わった後では話せないし、何より終わった後で聞く気も無いらしい。そのくせ終わる前からしゃべり出しているらしい」
久しぶりの晴天もいつになく風が強くて布団が干せないのだ。部屋の日の当たらない位置に立て掛けた白い網に取り付けた南京錠を悩んだ挙げ句に今日は四つ外してから出かけました。
数個のフルーツを抱えた佐川急便の男性とすれ違い、強張った菌類が遊具の柱元に群生している妙な縁起の公園を通りすぎ、駅のまたがる大きな国道の脇の何一つ植わっていない植え込みスペースに横たわり返っている、鳩かもしれない鳩を目にした時は、ただならぬスケールを感存、オッと告げると同時にひるがえしていた。自分やその軟弱な構成要素、魂から糸を引いた残飯の(大事な)跡取りのようなものを。
揚々と寄れば無変哲な死んでる鳩だ。体が覚えている。乾いて土だらけになって、赤足の付け根が破けて座布団の四隅のようになるのだ。継ぎ目から傷んでいくその様を、自分の番が来るまで、自分の身に起こるまで、何度見せつけられてもわからないのだろうか。

見下ろしているうちに急速に無趣味、パチンコぐらい、そんな感じの心境になってきたので所在なく「皆様」と言いながらツイッターに死鳩をうpした。弁護できない無、非存在の陥穽、何よりうれしい一万円。今し方あんなにひるがえしたものはどこにいったかという努力賞のような記念写真に★が細々とついていき、トンボの歩く脳裏に夜汽車が走って、シガレットの折れるような音が断続的に響いた。若い身空で主張すなすな……。
もはや意味無しの鳩を眺めて、駅に貼られた時刻表の写真を今後ぜってー便利だと思い撮っていたら、あれは小学2年のタイミングだったか、飼育中のミドリガメがぐったりしていたのを飽かず眺めたあの日のあれは、心配ではなく楽しみだったかも知れないと、急に胸にせり上がってむざむざ反映してくるものがあった。例えば何かが起こりつつあって、でもまだ起こってはおらず、よって現実と何の関係も感慨もないままと言っていいはずな、思い思いの電気を脳みそに青白く血走らせ、現存しない死の亀を明滅させた時のやわら熱ぼったい瞬間のきらめき、奴こそ幸福の正体だったかも知れないという意味で。名も付けず終いだった亀が閉じた一重瞼、その直径5ミリの線そのものにわざとらしく滲ませ塗り込めた不安心配可哀想、その刺激を口に含んで涙を誘い、心ゆくまでゆすいだ後、吐き出す気でいたのだろう。だとしたら、みんながみんな、全部が全部、そうかもしれない。
小さな種が果肉をまとっていくように労作ができあがりつつある圧縮された時間や、その実を口にした者が考えを巡らせていると予期されるような時間。幸福だと思うその時間。完成したから、褒められたから幸福なのではなく、完成してもいないうちに完成を体験し、褒められてもいないのに褒められた気になるから幸福なのであって。だから何をせずとも幸福にはなれようね。した気になって、した風な口を利いて。是非そうしたい。みんな是非そうしている様子だ。上手すぎる、手際よすぎる、出遅れたと感じている。あれから身動き一つしていないはずなのに、面倒が勝ってきたような……大体そんな感じ……。
それでも用事があって郵便局に。ああもしかして、だから死ぬのが恐いのですねと郵便局のパートのおば(実の伯母)に言ったら、速達ですかと聞かれたので、普通でお願いしますと答えた。何卒……。90円です。ならばですよ、死ぬ前に死んだ気になれたらそれは幸福なのかな……?……言下に答えた時には、もうATMでマイナ2万円ほどの残高照会をしていた。癖なのです。ATMを見ると、どうも残高照会する。
帰ったら馬鹿がプレステしたみたいに6時間も経っている。出る前は、レースのカーテン越しに窓枠を縁取って、あんなに薄曇りのあざな光が、部屋中にらって、らっていたのに。
「ちょっとこれ…自分が生きることで自分の道が妨害されてませんか?」
「そろそろ慣れたか――?」
「慣れたし、そうでないと生きてる気がしないようになったかも……」
「……」
「今まさに舐めつつある不幸はあきらめがつくけれども、起こりはしないかと心配していることについてはそうはいかず、でもそこにしか楽しみもないのです……」
「……」
家は答えない。家だから。でもそこで暮らす。家だから。
腹が減って、飯も食ったし、今後ずっと夜。そのとある瞬間に、笛も野次も拍手も賞状も無く一瞬の一発で全ての波が引いて、穏やかだから優しく見えるだけの静心に言い聞かせてくるものがある。マンションだろうか…?
「何も起こりはしなかった」
シェイクスピアの台詞にこんなのがありましたね。僕はそんな風に言われたらいちばん恐いと思うんですけど。みなさんはどうですか(ルイージマンション2からの問題)。

棟梁は弁当と一緒に梁の上
結婚四年目の三人家族のものだという二階建ての新築家屋はもうすぐ木組みが完成するところだった。初夏、天気も良く、昼の休憩を告げる棟梁の声も心なしかいつもより高く響いた。
「鮭がうめえうめえ……」
僕たち、下っ端ヤング大工マンたち(低学歴)は、地上で弁当を食い、弁当を褒めて午後もがんばれる力を底上げしながら、子供部屋が二つできる二階部分へ渡した梁の上を見上げた。
棟梁はただ一人、縦置きしたヤングマガジンほどの幅(正ヤンマガ幅)で弁当を立ち食いしていた。これは棟梁の七百八個(ななひゃくやっこ)ある大工奥義の一つ「高い分、美味い」である。
僕たち下っ端ヤング大工マンたちは、犬のように地べたに這いつくばって弁当を食いながら、棟梁の美しい立ち食い姿を惚れ惚れと見上げるしかない。一体どれほどの修行を重ねたら、あんな芸当ができるというのか。そもそも、ああいうことは本当にしておいた方がいいのか。
まあ、もしも、今の自分たちがあそこで立ち食いをしたら、ろくに食べた気がしないだろう。主力級のオカズをぼろぼろ下へこぼした挙げ句、その上へ真っ逆さまに落下、のり弁の香をかぎながら惨めに息絶えることになるに決まってる。頬っぺたに海苔が張り付き、早起きしたお母さんが作ったおにぎりの昼ごろの質感になるに決まってる。
ところが見てください、そう考えてみたら、試しにそういう思考になってみたら、棟梁は本当に凄い。こんなに凄いのにTVチャンピオンに出ないなんて自殺行為ではないかという気持ちで僕たちは箸を口に運んだ。早く食べ終えて、みんなでピザポテトが食べたい。そんな気持ちだった。
しかしその時、棟梁が立っている梁の両側、柱の元に悪魔がいることに気づいた。
い、いつの間に。
「やっぱり悪魔って突然、現れるものなんだ!」
しかもだよ。体全体が濃い紫シッポが矢印の悪魔がカニ歩きで少しずつ近づいてきているんだ。よく見ると、一階部分の柱の両側に、サークルKサンクスでもらえる星形の穴が散りばめられたフォークを大きくしたようなものが立てかけてあった。その無雑作な感じは実に目的をもって来たという気がした。気まぐれではなく、棟梁を狙って、遠くから、来たんだ。弁当が、うまい。
「あの悪魔ども、弁当を立ち食いしてる棟梁を挟み撃ちにする気だぞ」
誰かの小さな声が聞こえ、僕はその時一瞬遅れて、これはえらいことになったなと思って血の気が引いた。みんな目配せする。
「どうしよう」
棟梁はまだ黙々と立ち食いを続けている。やっぱり素直に下で食べておけばよかったんだ。カッコつけてあんなとこで立ち食いなんかして、名人気取りで、だから悪魔に目をつけられてしまうんだ。山頂で食うおにぎりがうまいのは、単に気持ちの問題だ。正直言って、棟梁は、パズドラとかをやってる若い僕たちと何を喋っていいかわからない自分が惨めになるから逃げを打って、あんなところで弁当を立ち食いしているんだ。
片方の悪魔は黄色に赤水玉の箱を持って、横向きでじりじり、時々ふらついて腰をかくかくさせながら、通勤中のような真顔で、弁当を食っている棟梁に近づいていく。もう片方の悪魔は手ぶらで、両手を横に伸ばして、時折大きく息を吐きながら進んでいる。その息は少し紫色をしていて、僕らの手前まで拡散してかき消えた。
なんとなく弁当を手やフタで隠しながら、僕たちは話した。
「しかし、あっちの悪魔は、かなり安定しているな」
「何も持っていないからだよ。偉いのは箱を持っている悪魔だ。もしかしたらとんでもなく重い箱かも知れないというのに」
「かなり、トレーニングを積んでいる悪魔なのかな。確かに重そうだ」
「少なくとも、弁当よりは重いよ……」
日頃から棟梁のことをよく思っていない野津田がボソリとつぶやいた。
みな、はそはそと冷たいごはんを口に運んだ。冷たいごはんは割り箸になんてよく引っかかるのだろう。はっきり割れて、泣きたいぐらいに絡みついてくる。
「あ、見ろ」
ようやく悪魔の接近に気づいた棟梁は、弁当に顔を半ば突っ込みながら、明らかに慌てた様子で交互に振り返り、目だけをチラチラ上げて悪魔を何度も見やった。
そこまでかっこ悪い棟梁を見るのは初めてだったけど、梁の上で悪魔に挟み撃ちされたのでは止むを得まい。しかし、その慌てぶりを普段こき使っている僕たちに見られていると知ったら、棟梁のハートはギザギザになってしまうだろう。子守唄なしで。
僕たちは目配せし、棟梁にわからないよう「弁当8、チラ見2」のフォーメーションをしいた。シャケ、ご飯、卵焼き、白身魚のフライ、棟梁しっかり、ご飯のリズムに箸が陰鬱な調べを奏でようとするが、小豆色をした薄いプラスチック容器が立てるくぐもった音は、白飯部分の重みに全て吸収されてしまうようだ。よく考えられている。
食ってる間に大メインクライマックス、悪魔が棟梁のところまで到着した。
箱を持った悪魔が、やはり真顔で、その箱を棟梁に差し出す。
「これは……悪魔一流の罠に違いないぞ」
「舌切り雀の、大きいつづらのパターンだ」
「真顔で渡されるプレゼントは、絶対に受け取っちゃだめだ。受け取った瞬間、大爆発だぞ」
僕たちはひそひそ口を挟んだが、棟梁はどうやら物につられて受け取ろうとしているようだった。どうにかこうにか受け取ろうと、持っている弁当をどうしようか迷った様子で、きょろきょろしたり、しゃがもうとしたり、おたおたしている。そして、ちょっと照れている。
「まずいぞ。棟梁は悪魔のプレゼントを受け取る気マンマンだ。照れている」
「でも大丈夫。梁の上では、さすがの棟梁も弁当を手放すことができないよ。だからプレゼントももらえない。これでよかったんだ」
そかそか! 僕らがホッとしたその時、棟梁は首を180度、それから体を180度のカートゥーン振り向きをかまし、手ぶらの悪魔に「弁当持ってて……」と言わんばかりにおずおずと差し出した。箸は、ご飯に斜めに突っ込んで動かないようにする生活感になっているようだ。
「ま、まずい! あれじゃあ悪魔の思うツボだ!」
「おい、静かにしろよ。聞こえちゃうだろっ。悪魔の耳は……良いっ!」
「でも、そんなこと言ってる場合か。みすみす悪魔の手にかかるより、ハートがギザギザになった方がずいぶんましだ」
「俺もそう思う。棟梁は欲張り。喩えるなら、動物園で勃起してるライオンだ。もらえるものは悪魔からでももらっちまおうなんて、これだから闇米を体に入れた世代はいやなんだ」
野津田だけはニヤニヤしてしまう笑顔を、顔の前に掲げた鮭で隠していた。そのとき、鮭が自重でパックリ割れてぶら下がった。その隙間から尖りに尖った口角と八重歯がのぞいていた。
「あ、悪魔……」
思わずつぶやいてしまった自分の口をあわてて栗で塞ぐ。弁当に栗が入っていて本当によかった。栗のおかげで命拾い。本来の旬は秋なのに、夏でも栗が流通していて助かった。
そして野津田は割れた鮭を下から丸呑みした。僕はご飯も口の中に放り込み、ぐっと堪えた。口の中が栗とご飯なのか。
そんなこんなで下で盛り上がっていた隙に、梁の上の棟梁は手ぶらの悪魔に弁当を持ってもらうのを断られたような感じになっており、またもおたおたして、そしてなんでだろう、ちょっと笑っていた。
手ぶらの悪魔はバランスを取ったまま、棟梁に向かってしきりに横に首を振っていた。一方で、背中からは、早く早くという感じで悪魔が箱を押し付けている。
押し付けるたびに、棟梁だけでなく悪魔の方の足元もふらつき、さすがにびびっている様子だ。バランスを取るため、早く受け取って欲しいのだろう。それなら手ぶらの悪魔は弁当を持ってくれたっていいのに、いったい、悪魔どもはプレゼントを受け取って欲しいのか、欲しくないのか。絶体絶命のピンチだ。
「あの状況じゃ、悪魔のサプライズ・プレゼントを早く受け取った方が安全だな」
「でも、一瞬でもいいから弁当を持ってもらわないことには棟梁はいつまでもプレゼントを受け取れないぞ」
弁当を両手に持ったまま体をくの字に折った棟梁の皺だらけの笑顔が、かんべんしてくださいよ、と口を動かしたように見えたが、黙っていた。黙っていたけど、
「一瞬でいいんですけど!」という棟梁の声が聞こえた。
それでも悪魔は頑なに、首を振っている。真っ直ぐ横に手を広げ、足を前と後ろに付けていた。もしかしてつま先を見たら、目印の線が引いてあるかも知れない。
そこで棟梁は何かひらめいたのか、悪魔に何か言った。二度目に言った時、僕たちにも、どうにか聞こえた。
「すぐ食っちゃうね」
悪魔はそこで、少し後ずさりして、棟梁が弁当を食べる分のスペースを作ってくれた。言葉が通じるんだ。棟梁はすぐさま勢いよくで食べ始めた。
「こんなの、すぐよ」
不安になったのか、棟梁は割りと大きい声で、箸を耳の横で天に向けて刺すような小さな動きをつけて言い放った。バカ! そんなにプレゼントが欲しいのか。僕は、あの箱の中身は、相手が悪魔ということや水玉の柄から言って、90%の確率でピエロもしくは松井秀喜のバブルヘッドが飛び出すビックリ箱だとあたりをつけていたので、棟梁がそんなに必死になるのがとても情けなく思えた。きっと、大福とか、ダウンジャケットとか、重たい灰皿などが入っていると思っているのだ。
「一瞬よ」
一瞬とか言いながら、棟梁の食はいまいち進んでいなかった。食べるやる気を見せているだけだ。あんまりバクバク食べると、やはりそこは細い梁の上、いくら棟梁といえどもフラフラしてしまうのはわかるが、もう少し冒険してもいいんじゃないだろうか。何のために、今まで毎日そこで弁当を食っていたんだ。自分を守るためか?
悪魔もその様子を見てガッカリしたのか、なんだ、口だけ君か、と言わんばかりの冷たい視線を浴びせ、それから互いの目を合わせると、振り返ってそれぞれ、カニ歩きとバランス歩行で棟梁から離れて行き始めた。
それに気づいた棟梁は、かなりあせりながら、もはや箱を持っている悪魔だけの方しか見ずに叫んだ。
「待てって! 今食っちまうから! ねぇ! ほら!」
ちょっと弁当を傾けて見せた後、ようやくフルパワーの"食い"を見せ始めた棟梁は、その自分の食いの生み出す勢いに負けて肩口からバランスを崩し、もうそんなにねじれない老体を珍しくねじらせながら、空中に放り出された。
「あっ!!」
僕たちが叫んだ瞬間、悪魔の姿は一瞬にして消え、棟梁は腰から落下した。終わった。そう思った。
棟梁は顔を、まだかなり残っていたらしい惣菜まみれにして胸に弁当のガラを抱えながら、一階の便所が作られる予定の部分で、ピクリとも動かず目を閉じていた。この時はなんとなくそこまで深く考えず、全体的には「あーあ」という感じだった。
僕たちは手持ち無沙汰になり、誰が言うでもなく「弁当10、GO FIGHT」のフォーメーションをしき、それしか残っていない、普段はちょっと残す、飯の横の非常に狭いスペースにある漬物を全力でポリポリするしかなかった。
ややあって、野津田がピザポテトの袋を開ける音が青空に響いた。
漂ってきたクサ美味い、胸騒ぎの匂い。野津田の大きく開いた口の中でギザギザポテトが四つに八つに十六に割れて、またきつい匂いが立ちこめる。
僕はそこで初めて棟梁が死んだことがはっきりとわかった。間違いなく死んだんだ。もう弁当を食べる気を失くしていた。絶対、ピザポテトの匂いのせいだ。
「鮭がうめえうめえ……」
僕たち、下っ端ヤング大工マンたち(低学歴)は、地上で弁当を食い、弁当を褒めて午後もがんばれる力を底上げしながら、子供部屋が二つできる二階部分へ渡した梁の上を見上げた。
棟梁はただ一人、縦置きしたヤングマガジンほどの幅(正ヤンマガ幅)で弁当を立ち食いしていた。これは棟梁の七百八個(ななひゃくやっこ)ある大工奥義の一つ「高い分、美味い」である。
僕たち下っ端ヤング大工マンたちは、犬のように地べたに這いつくばって弁当を食いながら、棟梁の美しい立ち食い姿を惚れ惚れと見上げるしかない。一体どれほどの修行を重ねたら、あんな芸当ができるというのか。そもそも、ああいうことは本当にしておいた方がいいのか。
まあ、もしも、今の自分たちがあそこで立ち食いをしたら、ろくに食べた気がしないだろう。主力級のオカズをぼろぼろ下へこぼした挙げ句、その上へ真っ逆さまに落下、のり弁の香をかぎながら惨めに息絶えることになるに決まってる。頬っぺたに海苔が張り付き、早起きしたお母さんが作ったおにぎりの昼ごろの質感になるに決まってる。
ところが見てください、そう考えてみたら、試しにそういう思考になってみたら、棟梁は本当に凄い。こんなに凄いのにTVチャンピオンに出ないなんて自殺行為ではないかという気持ちで僕たちは箸を口に運んだ。早く食べ終えて、みんなでピザポテトが食べたい。そんな気持ちだった。
しかしその時、棟梁が立っている梁の両側、柱の元に悪魔がいることに気づいた。
い、いつの間に。
「やっぱり悪魔って突然、現れるものなんだ!」
しかもだよ。体全体が濃い紫シッポが矢印の悪魔がカニ歩きで少しずつ近づいてきているんだ。よく見ると、一階部分の柱の両側に、サークルKサンクスでもらえる星形の穴が散りばめられたフォークを大きくしたようなものが立てかけてあった。その無雑作な感じは実に目的をもって来たという気がした。気まぐれではなく、棟梁を狙って、遠くから、来たんだ。弁当が、うまい。
「あの悪魔ども、弁当を立ち食いしてる棟梁を挟み撃ちにする気だぞ」
誰かの小さな声が聞こえ、僕はその時一瞬遅れて、これはえらいことになったなと思って血の気が引いた。みんな目配せする。
「どうしよう」
棟梁はまだ黙々と立ち食いを続けている。やっぱり素直に下で食べておけばよかったんだ。カッコつけてあんなとこで立ち食いなんかして、名人気取りで、だから悪魔に目をつけられてしまうんだ。山頂で食うおにぎりがうまいのは、単に気持ちの問題だ。正直言って、棟梁は、パズドラとかをやってる若い僕たちと何を喋っていいかわからない自分が惨めになるから逃げを打って、あんなところで弁当を立ち食いしているんだ。
片方の悪魔は黄色に赤水玉の箱を持って、横向きでじりじり、時々ふらついて腰をかくかくさせながら、通勤中のような真顔で、弁当を食っている棟梁に近づいていく。もう片方の悪魔は手ぶらで、両手を横に伸ばして、時折大きく息を吐きながら進んでいる。その息は少し紫色をしていて、僕らの手前まで拡散してかき消えた。
なんとなく弁当を手やフタで隠しながら、僕たちは話した。
「しかし、あっちの悪魔は、かなり安定しているな」
「何も持っていないからだよ。偉いのは箱を持っている悪魔だ。もしかしたらとんでもなく重い箱かも知れないというのに」
「かなり、トレーニングを積んでいる悪魔なのかな。確かに重そうだ」
「少なくとも、弁当よりは重いよ……」
日頃から棟梁のことをよく思っていない野津田がボソリとつぶやいた。
みな、はそはそと冷たいごはんを口に運んだ。冷たいごはんは割り箸になんてよく引っかかるのだろう。はっきり割れて、泣きたいぐらいに絡みついてくる。
「あ、見ろ」
ようやく悪魔の接近に気づいた棟梁は、弁当に顔を半ば突っ込みながら、明らかに慌てた様子で交互に振り返り、目だけをチラチラ上げて悪魔を何度も見やった。
そこまでかっこ悪い棟梁を見るのは初めてだったけど、梁の上で悪魔に挟み撃ちされたのでは止むを得まい。しかし、その慌てぶりを普段こき使っている僕たちに見られていると知ったら、棟梁のハートはギザギザになってしまうだろう。子守唄なしで。
僕たちは目配せし、棟梁にわからないよう「弁当8、チラ見2」のフォーメーションをしいた。シャケ、ご飯、卵焼き、白身魚のフライ、棟梁しっかり、ご飯のリズムに箸が陰鬱な調べを奏でようとするが、小豆色をした薄いプラスチック容器が立てるくぐもった音は、白飯部分の重みに全て吸収されてしまうようだ。よく考えられている。
食ってる間に大メインクライマックス、悪魔が棟梁のところまで到着した。
箱を持った悪魔が、やはり真顔で、その箱を棟梁に差し出す。
「これは……悪魔一流の罠に違いないぞ」
「舌切り雀の、大きいつづらのパターンだ」
「真顔で渡されるプレゼントは、絶対に受け取っちゃだめだ。受け取った瞬間、大爆発だぞ」
僕たちはひそひそ口を挟んだが、棟梁はどうやら物につられて受け取ろうとしているようだった。どうにかこうにか受け取ろうと、持っている弁当をどうしようか迷った様子で、きょろきょろしたり、しゃがもうとしたり、おたおたしている。そして、ちょっと照れている。
「まずいぞ。棟梁は悪魔のプレゼントを受け取る気マンマンだ。照れている」
「でも大丈夫。梁の上では、さすがの棟梁も弁当を手放すことができないよ。だからプレゼントももらえない。これでよかったんだ」
そかそか! 僕らがホッとしたその時、棟梁は首を180度、それから体を180度のカートゥーン振り向きをかまし、手ぶらの悪魔に「弁当持ってて……」と言わんばかりにおずおずと差し出した。箸は、ご飯に斜めに突っ込んで動かないようにする生活感になっているようだ。
「ま、まずい! あれじゃあ悪魔の思うツボだ!」
「おい、静かにしろよ。聞こえちゃうだろっ。悪魔の耳は……良いっ!」
「でも、そんなこと言ってる場合か。みすみす悪魔の手にかかるより、ハートがギザギザになった方がずいぶんましだ」
「俺もそう思う。棟梁は欲張り。喩えるなら、動物園で勃起してるライオンだ。もらえるものは悪魔からでももらっちまおうなんて、これだから闇米を体に入れた世代はいやなんだ」
野津田だけはニヤニヤしてしまう笑顔を、顔の前に掲げた鮭で隠していた。そのとき、鮭が自重でパックリ割れてぶら下がった。その隙間から尖りに尖った口角と八重歯がのぞいていた。
「あ、悪魔……」
思わずつぶやいてしまった自分の口をあわてて栗で塞ぐ。弁当に栗が入っていて本当によかった。栗のおかげで命拾い。本来の旬は秋なのに、夏でも栗が流通していて助かった。
そして野津田は割れた鮭を下から丸呑みした。僕はご飯も口の中に放り込み、ぐっと堪えた。口の中が栗とご飯なのか。
そんなこんなで下で盛り上がっていた隙に、梁の上の棟梁は手ぶらの悪魔に弁当を持ってもらうのを断られたような感じになっており、またもおたおたして、そしてなんでだろう、ちょっと笑っていた。
手ぶらの悪魔はバランスを取ったまま、棟梁に向かってしきりに横に首を振っていた。一方で、背中からは、早く早くという感じで悪魔が箱を押し付けている。
押し付けるたびに、棟梁だけでなく悪魔の方の足元もふらつき、さすがにびびっている様子だ。バランスを取るため、早く受け取って欲しいのだろう。それなら手ぶらの悪魔は弁当を持ってくれたっていいのに、いったい、悪魔どもはプレゼントを受け取って欲しいのか、欲しくないのか。絶体絶命のピンチだ。
「あの状況じゃ、悪魔のサプライズ・プレゼントを早く受け取った方が安全だな」
「でも、一瞬でもいいから弁当を持ってもらわないことには棟梁はいつまでもプレゼントを受け取れないぞ」
弁当を両手に持ったまま体をくの字に折った棟梁の皺だらけの笑顔が、かんべんしてくださいよ、と口を動かしたように見えたが、黙っていた。黙っていたけど、
「一瞬でいいんですけど!」という棟梁の声が聞こえた。
それでも悪魔は頑なに、首を振っている。真っ直ぐ横に手を広げ、足を前と後ろに付けていた。もしかしてつま先を見たら、目印の線が引いてあるかも知れない。
そこで棟梁は何かひらめいたのか、悪魔に何か言った。二度目に言った時、僕たちにも、どうにか聞こえた。
「すぐ食っちゃうね」
悪魔はそこで、少し後ずさりして、棟梁が弁当を食べる分のスペースを作ってくれた。言葉が通じるんだ。棟梁はすぐさま勢いよくで食べ始めた。
「こんなの、すぐよ」
不安になったのか、棟梁は割りと大きい声で、箸を耳の横で天に向けて刺すような小さな動きをつけて言い放った。バカ! そんなにプレゼントが欲しいのか。僕は、あの箱の中身は、相手が悪魔ということや水玉の柄から言って、90%の確率でピエロもしくは松井秀喜のバブルヘッドが飛び出すビックリ箱だとあたりをつけていたので、棟梁がそんなに必死になるのがとても情けなく思えた。きっと、大福とか、ダウンジャケットとか、重たい灰皿などが入っていると思っているのだ。
「一瞬よ」
一瞬とか言いながら、棟梁の食はいまいち進んでいなかった。食べるやる気を見せているだけだ。あんまりバクバク食べると、やはりそこは細い梁の上、いくら棟梁といえどもフラフラしてしまうのはわかるが、もう少し冒険してもいいんじゃないだろうか。何のために、今まで毎日そこで弁当を食っていたんだ。自分を守るためか?
悪魔もその様子を見てガッカリしたのか、なんだ、口だけ君か、と言わんばかりの冷たい視線を浴びせ、それから互いの目を合わせると、振り返ってそれぞれ、カニ歩きとバランス歩行で棟梁から離れて行き始めた。
それに気づいた棟梁は、かなりあせりながら、もはや箱を持っている悪魔だけの方しか見ずに叫んだ。
「待てって! 今食っちまうから! ねぇ! ほら!」
ちょっと弁当を傾けて見せた後、ようやくフルパワーの"食い"を見せ始めた棟梁は、その自分の食いの生み出す勢いに負けて肩口からバランスを崩し、もうそんなにねじれない老体を珍しくねじらせながら、空中に放り出された。
「あっ!!」
僕たちが叫んだ瞬間、悪魔の姿は一瞬にして消え、棟梁は腰から落下した。終わった。そう思った。
棟梁は顔を、まだかなり残っていたらしい惣菜まみれにして胸に弁当のガラを抱えながら、一階の便所が作られる予定の部分で、ピクリとも動かず目を閉じていた。この時はなんとなくそこまで深く考えず、全体的には「あーあ」という感じだった。
僕たちは手持ち無沙汰になり、誰が言うでもなく「弁当10、GO FIGHT」のフォーメーションをしき、それしか残っていない、普段はちょっと残す、飯の横の非常に狭いスペースにある漬物を全力でポリポリするしかなかった。
ややあって、野津田がピザポテトの袋を開ける音が青空に響いた。
漂ってきたクサ美味い、胸騒ぎの匂い。野津田の大きく開いた口の中でギザギザポテトが四つに八つに十六に割れて、またきつい匂いが立ちこめる。
僕はそこで初めて棟梁が死んだことがはっきりとわかった。間違いなく死んだんだ。もう弁当を食べる気を失くしていた。絶対、ピザポテトの匂いのせいだ。
社長の息子マジックショー
なんだか僕ばかり更新しているようですが、月1ペースです。
社長の息子(二階堂)は前に出てくると、日高屋に通い慣れた人のような横柄な態度で5年1組の36人を見回した。真ん中あたりに座っている亀山ノブヒコは両肘を突いて不満げな顔で、その憎きダブルのスーツをじっと見つめていた。
「出席番号23番、社長の息子です。ではマジックショーを始めます」
「はいみんな拍手~!!」
先生に促されるようにして拍手が起こり、社長の息子はうんうんと深く頷き、両手を前にかざした。そしてそのまま3歩前に出て、1番前の小島くんのところまでやって来た。
「僕が合図をすると、小島はもう動くことが出来なくなるよ。家がクリーニング屋でも全然関係ないよ。ハイいくよ、ズンズンズンズンズンズンズズン」
ミスターマリックのテーマを口ずさみながら、社長の息子は片手を自分のスーツの内ポケットに突っ込んだ。それからその手を抜くと、机の上にたたきつけた。バシンと大きな音がした。そして、小島くんは動かなくなった。
いや違う、小島くんの右手だけがまだ動いている。そして「すいません」という小さな声も聞こえた。ノブヒコを含むクラスの何人かが、小島くんの右手と二つにたたんだ一万円札とが一体感をもってポケットにすべりこんでいくのを目撃した。
「小島くん、動ける?」
「う、動けない」
「ザッツ・オール!」
社長の息子は、拳を握った両手をあげて少し横に引く動きで、1つ目のマジックが見事成功したことを示した。
「はい拍手~~!!」
また先生をはじめとして、拍手が起こった。
「こりゃあ幸先がいいぞ」
社長の息子は、すぐに落ちてくるスーツの袖を何度もまくりながら言った。
「小島ぁ、マジかよ。お前本当に動けないのかよー!」
後ろの方の窓際から石井くんの声が飛ぶ。
「う、動けない」
「すげーな!」
石井くんはそこで初めて大きな拍手をした。
「ぼく、死んじゃったのかな」
「そこまで言っちゃう!?」
「じゃあ次、その石井くんいっちゃおうかな。よかったね」
「ホントに!」
社長の息子は石井くんの方に自信のみなぎった足取りでずんずん歩き始める。
我慢ならないノブヒコは社長の息子が横にきた時、すっころばしてやろうと足を出した。
前を向いたままで気づいた様子は無かったのに、社長の息子はその手前で立ち止まった。ゆっくりとノブヒコの方に首を回す。そして小さい声で言った。
「よしてよ。亀山くん」
ノブヒコは肘をついて手を組み、妻の出産のその時を待つ父親のように動かなかった。
「マジックでわかっちゃったよ」
「大・ウソつきめ……」
小声で返す。社長の息子は何も言わない。ノブヒコは密かに視線を動かして、その下半身を見つめる。折り目のついた半ズボンからのぞいたきれいな膝の小僧を焼き尽くそうと見つめるが、すぐに視界を出て行った。
その最中にも集中力散漫なノブヒコは気づいてしまった。憎きあいつの下半身、その奥にある柔らかく折り曲げられた運動神経をたたえたしなやかで細い足。その微妙にひねられた向きだけで、体をつないだその上に自分に向けられた視線があるであろうことに気づいてしまった。
隣の席の的場さんが自分を見つめている。
大好きだ。こんな時でもノブヒコはどぎまぎして、みんながみんな社長の息子の動きを追って、椅子を引き引き見物の体勢を整えるのも気にせず、水色の短いソックスからのぞくくるぶしや、自分のと違って申し訳程度の汚れが浮かぶだけの清潔な白い上履きを見ていた。足を出したイジワルを、見られただろうか……。
「石井くん、じゃあいくよ。石井くんは東西一の幸せものだよ」
クラス全員に背を向けるようにして石井くんの前に立つと、社長の息子は語りかけ、バン!と掌を机に叩きつけた。その時、石井くんの「えっこんなに」という小さい声が、また何人かに聞こえた。「おじいちゃんだってこんなには……」
その声をかき消すように、社長の息子は大声を出した。
「石井くんは、ひっくりかえったカブトムシになるよ! ていうか……なるでしょコレは!?」
遠い人はマジックにお目にかかろうと椅子の上に膝で立ち、行方を見守った。石井、本当なのか。身も心もひっくりかえったカブトムシになってしまうのか。
「ズンズンズンズンズンズズン」
「う、うわー!」 ガタタタズダーン!!
石井くんはそのまま、運動神経はそんなに良くないし、度胸も無いはずなのに、派手に椅子ごと倒れてひっくり返った。そして、勢いそのまま椅子から放り出されると、床に仰向けに寝転がり、肘と膝を内側に曲げて、一斉に上下へ動かし始めた。
「起こしてくれー。お願いだー。カブトムシからの、お願いだー」
「いった……!」「えらいことになってきたな」
感嘆の声がところどころから上がった。「トリックだ」が三度の飯より口癖の石井が、ここまでどっぷりマジックにかかってしまうとなると、こいつぁ本当にホンモノなのかもしれない。東野が催眠にかかるぐらいの信頼性があった。
「はい拍手~~!!」
ノブヒコだけはその様子を見ていなかった。的場さんが途中で膝立ちしてしまってからはずっと前を向いていた。
しかし、やんややんやと拍手が起こり始めると、怒りに任せて立ち上がった。ズダダダダダと機関銃を撃つようなけたたましい椅子の音が鳴り響き、一瞬にして静まった教室の視線が、特にマジックをしているわけでもないノブヒコに集まる。きっと的場さんも見ているだろう。
ノブヒコは社長の息子には一瞥もくれず、ひっくりかえったカブトムシ状態をキープしている石井くんに向かって歩いていった。社長の息子は、体の前で手を重ねた大人の「やすめ」の体勢のまま、やや大股で一歩、二歩、後ろへ下がって石井くんのそばを離れた。
「嘘だろ石井くん! おいてめえクソ石井! 親友の!!」
ノブヒコは石井の頭のそばに立ち、のぞきこんで声をかけた。
「か、亀山ー。お願いだ起こしてくれー。俺はカブトムシだー。ひっくりかえっちまったー、短い短い、夏だってぇのによー」
手と足を交互に動かして石井は言った。
「まだ言ってんのかよ! 目を覚ませ! 今ならまだ正直者でいられるぞ!!」
「海外のカブトムシが強くてなー」
「石井くん、石井くん!!」
「スイカ、樹液、メスカブト」
「何言ってんだよ白々しい! 味方をしてくれよ!!」
「マリオパーティー」
それから石井は目を閉じて黙った。
「石井! 石井くん! 起きろよ! トリックだろこんなの! そうだろ!! もしもし!!」
「……」
「ねえ! ちょっと!! 今日遊べる!? 石井くん!!」
「……」
いつもなら、こんな時はちょっとふざけて話しかけるだけですぐに吹き出してしまう石井くんがまったく、廃業した遊園地のメリーゴーランドのカボチャの馬車のようにまったく動かない。なんだよ。でも、石井くんは最後にマリオパーティーとつぶやいていた。みんなで一緒にゲームして遊ぶたび「アレあったら最高なんだけどな、なんつうの? マリオパーティー」と喉から手が出るほど欲しがっていたゲームソフトの名前を。ひっくりかえったカブトムシなら言うはずがない。
クラスは少し重苦しい雰囲気に包まれた。でも、誰も何も言わなかった。先生も拍手を始めようという手つきのまま、声を出すのはためらっているようだ。
パン、パン!「みんなこっちに注目!」
その音と声は教室の反対側、廊下側の一番前から聞こえた。凝り固まった首の関節が鳴る音があちこちからパキパキ響いた。
石井くんがひっくり返っているちょうど対角線上の席の前に、社長の息子がいつの間にかふてぶてしい顔で立っていた。
そしてなんということだろう。その机の上で、学級委員長、塾通い、チタンフレーム、ELLEのハンカチの花形くんがビートたけしの往年のギャグ、コマネチの動きを繰り返していた。
「コマネチッ…… やばい。コマネチッ…… 止まらないよ。ハッ、コマネチッ…… が、止まらないんだ。よせよ二階堂くんコマネチッ…… ほ、ほんとによせって二階堂くん! 二階堂バカ野郎この野郎」
ノブヒコは立ち尽くした。コマネチを見てこんなに沈んだ気分になってしまうなんて初めてだった。いつもなら、本当バカだな~たけしは、という思いはあるにしろ、朗らかな気持ちで見ているのに、今はただただ、むなしい。
「花形くん……学級委員長の君まで」
「いやこれはすごい…マジック、コマネチッ…… だよ。痛い痛い、アレちょっと痛い! 節々が痛い! コマネチッ…… 何だコレは…すごいぞ! 正真正銘、混じりっけ無しのマジックだ!!」
「花形くん、こっちを見てくれ。挨拶と正義にあふれる最高の5年1組をつくると言うから、僕は君に投票したんだ」
花形くんはノブヒコと目が合うと視線を逸らして斜めに俯き、コマネチのアクセルをゆるめた。
その不安を見て取った社長の息子が後ろに回り、花形くんのバックポケットに手を突っ込んだ。クシャリという音が響くと同時に、ぜんまいを巻かれたように花形くんがしゃべり出す。
「あんちゃん、投票ありがとう。オイラに言わせりゃ、あんちゃんの方がよっぽどエラいよ。で、もっとエラいのが若いおネエちゃん(笑)。石坂浩二さんはね、女を口説くときにベランダに出てハイネの詩を読むんだよね。ともかく何が言いたいかっていうと義太夫のかみさんはブスって事だな。そしたら離婚しちゃったでやんの(笑)……コマネチッ……」
今までで一番反り返り、天井を見つめたまま、花形くんはそこで動きを止めた。
「はい、拍手~~!!」
その通りに教室は拍手で埋まった。モノマネに対する拍手も混じっていた。
「みんな、本当にこれでいいのか」
次は誰か、俺か私かと一心に社長の息子を見ているみんなを見回してから、ノブヒコは足元でカブトムシになっている石井を見下ろした。固く固く、震えるほどに目を閉じていた。
「先生、こんなこと、許されるんですか」
小川先生は女の先生でまだ20代と若く、少し生徒にからかわれてしまうタイプだった。黄色いカーディガンの一番上のボタンをいじりながら、小川先生は3歩進んで2歩下がり、結果的に1歩前に出た。
「あのねえ、亀山くん。なんでも疑ってかかるのは先生、よくないと思うの。心の目で物事を見るように、4月に約束したはずね。今とは席がちがうけど、この教室で約束したのよ。みんな、とってもいい声で返事をしてくれた。先生は、亀山くんの声が一番よく聞こえたんだけどな」
ノブヒコは唇をかんで黙り込んだ。
「二階堂くんのマジック、すごいって、そう思わないかしら? こんなにすごいのに、どうしてそんな態度を取るの。石井くんも花形くんもあんなに見事にかかっているのに、どうしてその言葉を信じられないの? 石井くんと亀山くんは大の仲良しでしょう」
「先生、ぼくもですっ」
「小島くんもそうね、かかってたね、ありがとう。とにかく亀山くん……こんなこと言うのはずるいかもしれないけど、先生ちょっとだけがっかりしちゃったの。先生は、飼育係でハマちゃんの世話をしている時の亀山くんの目がキラキラ輝いて、大好きなんだけどな」
「そんなこと今関係ないだろ!」
クラスで飼っているウーパールーパーの世話が楽しいことなんか、今は関係ない。先生はずるい。本当にずるい。ずるいと面と向かって言う価値も無いほどに。
ノブヒコは先生に近づいていった。すると、先生の動きが止まった。いや、少しだけ動いている。力をこめてやっと少し動けるというように、わずかに震えながら手を前に伸ばしている。
「アレ亀山くん、先生、動けないわ!」
先生は震えながら、なんとか社長の息子、二階堂の方を見た。そっちに向けて、大きく広げた掌を、苦しく喘ぐように徐々に伸ばして突き出した。そして4月から今までで一番大きな声で言った。
「やめなさい!!! 二階堂くん、先生にマジックをナニするのはやめなさい!!!」
「ナニする……?」社長の息子は小首を傾げる。
「マジックをかけるのはやめなさい、という意味!」
先生は苦悶の表情を浮かべて、わかりやすく風呂縁につかまる上島竜平のような体勢になったあと、もう一度叫んだ。
「絶対にマジックをかけるな、という意味!!」
ハッと目を見開いた社長の息子はその瞬間、サッと先生に向けて手をかざした。
「ズンズンズンズンズンズンズズン」
大人の日本語の勉強にもなる一連のやりとりにノブヒコは、でかい川を渡ろうとしたら仲間がワニに食べられた草食動物のような悲しいけれど本当にそう思っているのかはわからない澄んだ瞳になって、そこで立ち止まった。もう歩を前に進める気力が出なかった。
「先生、一つだけ聞かせてください。先生はどうして小学校の先生になろうと思ったんですか」
ノブヒコが言い終わらないうちに、先生は、今完全に動くことも喋ることも出来なくなった、とでも言うように、やや下を向き、目を見開いたまま、ロボットダンスのような手足ばらばらの体勢で、一切の動きを止めた。しかしわずかに、野生のシマウマと化して神経が常に死と隣り合わせの暮らしによって研ぎ澄まされたノブヒコにだけ聞こえる声でホソリと呟いた。
「ドラム式洗濯機……」
実を言うと、ノブヒコには、先生の机の上にみずほ銀行のATMに備え付けてある封筒の厚いのが置いてあるのはずっと見えていた。ノブヒコは孤独な戦いになることを承知で立ち上がったのだ。
ノブヒコはたっぷりと先生を見つめた。しかし、先生は大人の、本気の、悲しいパントマイムを続けていた。教え子たちは、日頃の教え通りにお口をチャックし、固唾をのんでその様を見つめていた。
やがて、開きっぱなしになっていた先生の口元からよだれが垂れて、床まで粘り輝く糸が引いた。それでも頑なに石像となっている先生を見て、ノブヒコは諦めたように目を伏せ、丁寧でわざとらしい「回れ右」をした。
先生、僕がここで学んだものは、こんな悲しい動作だけなのですか……?
「セコな連中ばかりだ」
みんなの視線を受けてノブヒコはつぶやいた。小島くんを見たら、こちらも律儀にまだ動きを止めていた。
席に戻ると全身の力が抜けた。無邪気に風の子でならした小学生とは思えないほど疲労しており、このあとの給食当番がだるかった。
「ていうか、マジックとか言ってたけど、全部、超能力か催眠術じゃないか」
それだけ言うと、机の手前の淵におでこだけを乗せ、頭を腕で囲い、床をじっと見ることで5年1組の全てをシャットダウンした。そして、自分だけの世界へ沈潜していった。今度はシマウマではなかった。ザウルス系で埋め尽くされたシダ植物の世界。
しかし今、図鑑そのまま好ましいはずの世界では、ノブヒコの大好きなザウルスたちが全員うつむき、胡乱な目でほっつき歩いていた。時折立ち止まったかと思えば、全員ゲリ気味で、またよたよた苦しそうに歩き出した。今、ノブヒコの心はかつてないほどやさぐれていた。
でも、まだ恐竜たちはなんとか動き回っている。南の空にお日様が出ているからなんとかやっていける。的場さんがまたこっちを向いているのが、視界の端に引っかかった上履きの向きで期待できる。
「僕の家の会社は、僕が生まれる8年も前に一部上場しているんだよね」
いつの間にか社長の息子がそばまで近寄ってきていたらしく、すぐ近くで声が聞こえた。
「さぁ~てウサギだ! 次は女子だよ! はい、的場さんはウサギになります!」
ザウルスたちが一斉に体を持ち上げ、苦しそうな高い悲鳴を上げた。
「え……私……」
ちょっとかすれた的場さんの地声は戸惑いに満ちていた。
間髪入れず、平たい便利な紙が何枚か、的場さんの爽やかなカリフォルニア・オレンジ色のワンピースの首元に、カサリと価値ある音を立てて差し込まれるのを、教室の上空を飛行中のプテラノドンが発見した。びっくりして一瞬口を開けて、そのまま苦しそうに血を吐いて、錐揉み状に落ちていく。ウーパールーパーの水槽へ派手な水音を立てて墜落した。
「ズンズンズンズンズンズンズズン」
不吉な音に耐えかねて恐竜たちが次々と息絶え、パネルを外すように外の世界が徐々に露わになる。その最初の兆候として、ノブヒコは隣で椅子が動く音を自分の耳で聞いた。
下を向いたまま隣に目玉をスライドさせると、音を立てないように気持ち持ち上げられて動いた椅子の前にスペースが空くと同時にすくと立つ的場さんの足が見えた。
それから、これはノブヒコからは見えなかったが、的場さんはすでに頭の上にウサ耳代わりの手を添えていた。でもやっぱり、腰から下しか視界に捉えることができないノブヒコにも、白く長い、耳らしく見えるように親指を畳んだウサ耳がはっきりと見えていた。
「リラックマ文房具セットそのほか」
そう言いながら机の間の通路に出てくる的場さんのそんな声も本当には出ていなかったが、ノブヒコにはたまらないほど聞こえていた。そして実際にその音がノブヒコの鼓膜にヒビを入れてしまった。
気付くと涙があふれている。顔の下はすぐに涙でいっぱいになり、暑い湿気を放っている。机の淵からは涙が穏やかな滝のように音もなく流れ落ち、床に大きな水たまりを作り始めている。だのに誰も気づかない。
ビチャッ。
最初のウサギ跳びで、涙の海の一番先の、かなしく愛らしいおばけのような丸みにそのつま先を着地した的場さんは、まるで何にも気にも留めない。
さらに悪いことに、少しよろけて咄嗟に踏ん張った的場さんの足に、ノブヒコの机の横にかかっている過剰に膨らんだ道具袋が引っかかった。
足に触れた道具袋が身をよじるように、いやむしろ的場さんの足にその身をこすりつけるように動いているのがノブヒコに見えた。やはり的場さんは気にする様子も無い。どころか足に力がこもった。どうやらそのまま飛ぶらしい。
「ピョンッ」
ウサギを演じられているかどうか不安になったのか、的場さんは短く言ってまた跳んだ。踏みにじられて砕かれて、細かい涙の飛沫が舞って消える。
未練がましくまとわりついたノブヒコの道具袋は、大きな跳躍で遠く離れた的場さんの足を、弧を描くように離れた。勢いよく戻ってきて机の脚にぶつかった道具袋は、ガチャンと大きな音を立てた。その音はノブヒコの鼓膜をとうとう破いただけではとても足らず、その余りに乱暴な振動は、金属製の脚を伝って直接ガチャンと響くや灰色の脳を一気に溶かしてびしょびしょにした。
そんな頭蓋の空洞にクシャリと乾いた音がした。
「にんじんポリポリポリポリッ」
それなりに長い言葉を喋るとかすれた印象が少しずつなくなっていく。ノブヒコは、容姿とちぐはぐな、自分にしか聞こえていないようなその声が好きだった。でも、二度と同じようには聴くことができない。
「またまたピョンッ」
ウサギは遠くに行ってしまった。今度は自然にわき上がった拍手に送られて、恐竜が絶滅した。
社長の息子(二階堂)は前に出てくると、日高屋に通い慣れた人のような横柄な態度で5年1組の36人を見回した。真ん中あたりに座っている亀山ノブヒコは両肘を突いて不満げな顔で、その憎きダブルのスーツをじっと見つめていた。
「出席番号23番、社長の息子です。ではマジックショーを始めます」
「はいみんな拍手~!!」
先生に促されるようにして拍手が起こり、社長の息子はうんうんと深く頷き、両手を前にかざした。そしてそのまま3歩前に出て、1番前の小島くんのところまでやって来た。
「僕が合図をすると、小島はもう動くことが出来なくなるよ。家がクリーニング屋でも全然関係ないよ。ハイいくよ、ズンズンズンズンズンズンズズン」
ミスターマリックのテーマを口ずさみながら、社長の息子は片手を自分のスーツの内ポケットに突っ込んだ。それからその手を抜くと、机の上にたたきつけた。バシンと大きな音がした。そして、小島くんは動かなくなった。
いや違う、小島くんの右手だけがまだ動いている。そして「すいません」という小さな声も聞こえた。ノブヒコを含むクラスの何人かが、小島くんの右手と二つにたたんだ一万円札とが一体感をもってポケットにすべりこんでいくのを目撃した。
「小島くん、動ける?」
「う、動けない」
「ザッツ・オール!」
社長の息子は、拳を握った両手をあげて少し横に引く動きで、1つ目のマジックが見事成功したことを示した。
「はい拍手~~!!」
また先生をはじめとして、拍手が起こった。
「こりゃあ幸先がいいぞ」
社長の息子は、すぐに落ちてくるスーツの袖を何度もまくりながら言った。
「小島ぁ、マジかよ。お前本当に動けないのかよー!」
後ろの方の窓際から石井くんの声が飛ぶ。
「う、動けない」
「すげーな!」
石井くんはそこで初めて大きな拍手をした。
「ぼく、死んじゃったのかな」
「そこまで言っちゃう!?」
「じゃあ次、その石井くんいっちゃおうかな。よかったね」
「ホントに!」
社長の息子は石井くんの方に自信のみなぎった足取りでずんずん歩き始める。
我慢ならないノブヒコは社長の息子が横にきた時、すっころばしてやろうと足を出した。
前を向いたままで気づいた様子は無かったのに、社長の息子はその手前で立ち止まった。ゆっくりとノブヒコの方に首を回す。そして小さい声で言った。
「よしてよ。亀山くん」
ノブヒコは肘をついて手を組み、妻の出産のその時を待つ父親のように動かなかった。
「マジックでわかっちゃったよ」
「大・ウソつきめ……」
小声で返す。社長の息子は何も言わない。ノブヒコは密かに視線を動かして、その下半身を見つめる。折り目のついた半ズボンからのぞいたきれいな膝の小僧を焼き尽くそうと見つめるが、すぐに視界を出て行った。
その最中にも集中力散漫なノブヒコは気づいてしまった。憎きあいつの下半身、その奥にある柔らかく折り曲げられた運動神経をたたえたしなやかで細い足。その微妙にひねられた向きだけで、体をつないだその上に自分に向けられた視線があるであろうことに気づいてしまった。
隣の席の的場さんが自分を見つめている。
大好きだ。こんな時でもノブヒコはどぎまぎして、みんながみんな社長の息子の動きを追って、椅子を引き引き見物の体勢を整えるのも気にせず、水色の短いソックスからのぞくくるぶしや、自分のと違って申し訳程度の汚れが浮かぶだけの清潔な白い上履きを見ていた。足を出したイジワルを、見られただろうか……。
「石井くん、じゃあいくよ。石井くんは東西一の幸せものだよ」
クラス全員に背を向けるようにして石井くんの前に立つと、社長の息子は語りかけ、バン!と掌を机に叩きつけた。その時、石井くんの「えっこんなに」という小さい声が、また何人かに聞こえた。「おじいちゃんだってこんなには……」
その声をかき消すように、社長の息子は大声を出した。
「石井くんは、ひっくりかえったカブトムシになるよ! ていうか……なるでしょコレは!?」
遠い人はマジックにお目にかかろうと椅子の上に膝で立ち、行方を見守った。石井、本当なのか。身も心もひっくりかえったカブトムシになってしまうのか。
「ズンズンズンズンズンズズン」
「う、うわー!」 ガタタタズダーン!!
石井くんはそのまま、運動神経はそんなに良くないし、度胸も無いはずなのに、派手に椅子ごと倒れてひっくり返った。そして、勢いそのまま椅子から放り出されると、床に仰向けに寝転がり、肘と膝を内側に曲げて、一斉に上下へ動かし始めた。
「起こしてくれー。お願いだー。カブトムシからの、お願いだー」
「いった……!」「えらいことになってきたな」
感嘆の声がところどころから上がった。「トリックだ」が三度の飯より口癖の石井が、ここまでどっぷりマジックにかかってしまうとなると、こいつぁ本当にホンモノなのかもしれない。東野が催眠にかかるぐらいの信頼性があった。
「はい拍手~~!!」
ノブヒコだけはその様子を見ていなかった。的場さんが途中で膝立ちしてしまってからはずっと前を向いていた。
しかし、やんややんやと拍手が起こり始めると、怒りに任せて立ち上がった。ズダダダダダと機関銃を撃つようなけたたましい椅子の音が鳴り響き、一瞬にして静まった教室の視線が、特にマジックをしているわけでもないノブヒコに集まる。きっと的場さんも見ているだろう。
ノブヒコは社長の息子には一瞥もくれず、ひっくりかえったカブトムシ状態をキープしている石井くんに向かって歩いていった。社長の息子は、体の前で手を重ねた大人の「やすめ」の体勢のまま、やや大股で一歩、二歩、後ろへ下がって石井くんのそばを離れた。
「嘘だろ石井くん! おいてめえクソ石井! 親友の!!」
ノブヒコは石井の頭のそばに立ち、のぞきこんで声をかけた。
「か、亀山ー。お願いだ起こしてくれー。俺はカブトムシだー。ひっくりかえっちまったー、短い短い、夏だってぇのによー」
手と足を交互に動かして石井は言った。
「まだ言ってんのかよ! 目を覚ませ! 今ならまだ正直者でいられるぞ!!」
「海外のカブトムシが強くてなー」
「石井くん、石井くん!!」
「スイカ、樹液、メスカブト」
「何言ってんだよ白々しい! 味方をしてくれよ!!」
「マリオパーティー」
それから石井は目を閉じて黙った。
「石井! 石井くん! 起きろよ! トリックだろこんなの! そうだろ!! もしもし!!」
「……」
「ねえ! ちょっと!! 今日遊べる!? 石井くん!!」
「……」
いつもなら、こんな時はちょっとふざけて話しかけるだけですぐに吹き出してしまう石井くんがまったく、廃業した遊園地のメリーゴーランドのカボチャの馬車のようにまったく動かない。なんだよ。でも、石井くんは最後にマリオパーティーとつぶやいていた。みんなで一緒にゲームして遊ぶたび「アレあったら最高なんだけどな、なんつうの? マリオパーティー」と喉から手が出るほど欲しがっていたゲームソフトの名前を。ひっくりかえったカブトムシなら言うはずがない。
クラスは少し重苦しい雰囲気に包まれた。でも、誰も何も言わなかった。先生も拍手を始めようという手つきのまま、声を出すのはためらっているようだ。
パン、パン!「みんなこっちに注目!」
その音と声は教室の反対側、廊下側の一番前から聞こえた。凝り固まった首の関節が鳴る音があちこちからパキパキ響いた。
石井くんがひっくり返っているちょうど対角線上の席の前に、社長の息子がいつの間にかふてぶてしい顔で立っていた。
そしてなんということだろう。その机の上で、学級委員長、塾通い、チタンフレーム、ELLEのハンカチの花形くんがビートたけしの往年のギャグ、コマネチの動きを繰り返していた。
「コマネチッ…… やばい。コマネチッ…… 止まらないよ。ハッ、コマネチッ…… が、止まらないんだ。よせよ二階堂くんコマネチッ…… ほ、ほんとによせって二階堂くん! 二階堂バカ野郎この野郎」
ノブヒコは立ち尽くした。コマネチを見てこんなに沈んだ気分になってしまうなんて初めてだった。いつもなら、本当バカだな~たけしは、という思いはあるにしろ、朗らかな気持ちで見ているのに、今はただただ、むなしい。
「花形くん……学級委員長の君まで」
「いやこれはすごい…マジック、コマネチッ…… だよ。痛い痛い、アレちょっと痛い! 節々が痛い! コマネチッ…… 何だコレは…すごいぞ! 正真正銘、混じりっけ無しのマジックだ!!」
「花形くん、こっちを見てくれ。挨拶と正義にあふれる最高の5年1組をつくると言うから、僕は君に投票したんだ」
花形くんはノブヒコと目が合うと視線を逸らして斜めに俯き、コマネチのアクセルをゆるめた。
その不安を見て取った社長の息子が後ろに回り、花形くんのバックポケットに手を突っ込んだ。クシャリという音が響くと同時に、ぜんまいを巻かれたように花形くんがしゃべり出す。
「あんちゃん、投票ありがとう。オイラに言わせりゃ、あんちゃんの方がよっぽどエラいよ。で、もっとエラいのが若いおネエちゃん(笑)。石坂浩二さんはね、女を口説くときにベランダに出てハイネの詩を読むんだよね。ともかく何が言いたいかっていうと義太夫のかみさんはブスって事だな。そしたら離婚しちゃったでやんの(笑)……コマネチッ……」
今までで一番反り返り、天井を見つめたまま、花形くんはそこで動きを止めた。
「はい、拍手~~!!」
その通りに教室は拍手で埋まった。モノマネに対する拍手も混じっていた。
「みんな、本当にこれでいいのか」
次は誰か、俺か私かと一心に社長の息子を見ているみんなを見回してから、ノブヒコは足元でカブトムシになっている石井を見下ろした。固く固く、震えるほどに目を閉じていた。
「先生、こんなこと、許されるんですか」
小川先生は女の先生でまだ20代と若く、少し生徒にからかわれてしまうタイプだった。黄色いカーディガンの一番上のボタンをいじりながら、小川先生は3歩進んで2歩下がり、結果的に1歩前に出た。
「あのねえ、亀山くん。なんでも疑ってかかるのは先生、よくないと思うの。心の目で物事を見るように、4月に約束したはずね。今とは席がちがうけど、この教室で約束したのよ。みんな、とってもいい声で返事をしてくれた。先生は、亀山くんの声が一番よく聞こえたんだけどな」
ノブヒコは唇をかんで黙り込んだ。
「二階堂くんのマジック、すごいって、そう思わないかしら? こんなにすごいのに、どうしてそんな態度を取るの。石井くんも花形くんもあんなに見事にかかっているのに、どうしてその言葉を信じられないの? 石井くんと亀山くんは大の仲良しでしょう」
「先生、ぼくもですっ」
「小島くんもそうね、かかってたね、ありがとう。とにかく亀山くん……こんなこと言うのはずるいかもしれないけど、先生ちょっとだけがっかりしちゃったの。先生は、飼育係でハマちゃんの世話をしている時の亀山くんの目がキラキラ輝いて、大好きなんだけどな」
「そんなこと今関係ないだろ!」
クラスで飼っているウーパールーパーの世話が楽しいことなんか、今は関係ない。先生はずるい。本当にずるい。ずるいと面と向かって言う価値も無いほどに。
ノブヒコは先生に近づいていった。すると、先生の動きが止まった。いや、少しだけ動いている。力をこめてやっと少し動けるというように、わずかに震えながら手を前に伸ばしている。
「アレ亀山くん、先生、動けないわ!」
先生は震えながら、なんとか社長の息子、二階堂の方を見た。そっちに向けて、大きく広げた掌を、苦しく喘ぐように徐々に伸ばして突き出した。そして4月から今までで一番大きな声で言った。
「やめなさい!!! 二階堂くん、先生にマジックをナニするのはやめなさい!!!」
「ナニする……?」社長の息子は小首を傾げる。
「マジックをかけるのはやめなさい、という意味!」
先生は苦悶の表情を浮かべて、わかりやすく風呂縁につかまる上島竜平のような体勢になったあと、もう一度叫んだ。
「絶対にマジックをかけるな、という意味!!」
ハッと目を見開いた社長の息子はその瞬間、サッと先生に向けて手をかざした。
「ズンズンズンズンズンズンズズン」
大人の日本語の勉強にもなる一連のやりとりにノブヒコは、でかい川を渡ろうとしたら仲間がワニに食べられた草食動物のような悲しいけれど本当にそう思っているのかはわからない澄んだ瞳になって、そこで立ち止まった。もう歩を前に進める気力が出なかった。
「先生、一つだけ聞かせてください。先生はどうして小学校の先生になろうと思ったんですか」
ノブヒコが言い終わらないうちに、先生は、今完全に動くことも喋ることも出来なくなった、とでも言うように、やや下を向き、目を見開いたまま、ロボットダンスのような手足ばらばらの体勢で、一切の動きを止めた。しかしわずかに、野生のシマウマと化して神経が常に死と隣り合わせの暮らしによって研ぎ澄まされたノブヒコにだけ聞こえる声でホソリと呟いた。
「ドラム式洗濯機……」
実を言うと、ノブヒコには、先生の机の上にみずほ銀行のATMに備え付けてある封筒の厚いのが置いてあるのはずっと見えていた。ノブヒコは孤独な戦いになることを承知で立ち上がったのだ。
ノブヒコはたっぷりと先生を見つめた。しかし、先生は大人の、本気の、悲しいパントマイムを続けていた。教え子たちは、日頃の教え通りにお口をチャックし、固唾をのんでその様を見つめていた。
やがて、開きっぱなしになっていた先生の口元からよだれが垂れて、床まで粘り輝く糸が引いた。それでも頑なに石像となっている先生を見て、ノブヒコは諦めたように目を伏せ、丁寧でわざとらしい「回れ右」をした。
先生、僕がここで学んだものは、こんな悲しい動作だけなのですか……?
「セコな連中ばかりだ」
みんなの視線を受けてノブヒコはつぶやいた。小島くんを見たら、こちらも律儀にまだ動きを止めていた。
席に戻ると全身の力が抜けた。無邪気に風の子でならした小学生とは思えないほど疲労しており、このあとの給食当番がだるかった。
「ていうか、マジックとか言ってたけど、全部、超能力か催眠術じゃないか」
それだけ言うと、机の手前の淵におでこだけを乗せ、頭を腕で囲い、床をじっと見ることで5年1組の全てをシャットダウンした。そして、自分だけの世界へ沈潜していった。今度はシマウマではなかった。ザウルス系で埋め尽くされたシダ植物の世界。
しかし今、図鑑そのまま好ましいはずの世界では、ノブヒコの大好きなザウルスたちが全員うつむき、胡乱な目でほっつき歩いていた。時折立ち止まったかと思えば、全員ゲリ気味で、またよたよた苦しそうに歩き出した。今、ノブヒコの心はかつてないほどやさぐれていた。
でも、まだ恐竜たちはなんとか動き回っている。南の空にお日様が出ているからなんとかやっていける。的場さんがまたこっちを向いているのが、視界の端に引っかかった上履きの向きで期待できる。
「僕の家の会社は、僕が生まれる8年も前に一部上場しているんだよね」
いつの間にか社長の息子がそばまで近寄ってきていたらしく、すぐ近くで声が聞こえた。
「さぁ~てウサギだ! 次は女子だよ! はい、的場さんはウサギになります!」
ザウルスたちが一斉に体を持ち上げ、苦しそうな高い悲鳴を上げた。
「え……私……」
ちょっとかすれた的場さんの地声は戸惑いに満ちていた。
間髪入れず、平たい便利な紙が何枚か、的場さんの爽やかなカリフォルニア・オレンジ色のワンピースの首元に、カサリと価値ある音を立てて差し込まれるのを、教室の上空を飛行中のプテラノドンが発見した。びっくりして一瞬口を開けて、そのまま苦しそうに血を吐いて、錐揉み状に落ちていく。ウーパールーパーの水槽へ派手な水音を立てて墜落した。
「ズンズンズンズンズンズンズズン」
不吉な音に耐えかねて恐竜たちが次々と息絶え、パネルを外すように外の世界が徐々に露わになる。その最初の兆候として、ノブヒコは隣で椅子が動く音を自分の耳で聞いた。
下を向いたまま隣に目玉をスライドさせると、音を立てないように気持ち持ち上げられて動いた椅子の前にスペースが空くと同時にすくと立つ的場さんの足が見えた。
それから、これはノブヒコからは見えなかったが、的場さんはすでに頭の上にウサ耳代わりの手を添えていた。でもやっぱり、腰から下しか視界に捉えることができないノブヒコにも、白く長い、耳らしく見えるように親指を畳んだウサ耳がはっきりと見えていた。
「リラックマ文房具セットそのほか」
そう言いながら机の間の通路に出てくる的場さんのそんな声も本当には出ていなかったが、ノブヒコにはたまらないほど聞こえていた。そして実際にその音がノブヒコの鼓膜にヒビを入れてしまった。
気付くと涙があふれている。顔の下はすぐに涙でいっぱいになり、暑い湿気を放っている。机の淵からは涙が穏やかな滝のように音もなく流れ落ち、床に大きな水たまりを作り始めている。だのに誰も気づかない。
ビチャッ。
最初のウサギ跳びで、涙の海の一番先の、かなしく愛らしいおばけのような丸みにそのつま先を着地した的場さんは、まるで何にも気にも留めない。
さらに悪いことに、少しよろけて咄嗟に踏ん張った的場さんの足に、ノブヒコの机の横にかかっている過剰に膨らんだ道具袋が引っかかった。
足に触れた道具袋が身をよじるように、いやむしろ的場さんの足にその身をこすりつけるように動いているのがノブヒコに見えた。やはり的場さんは気にする様子も無い。どころか足に力がこもった。どうやらそのまま飛ぶらしい。
「ピョンッ」
ウサギを演じられているかどうか不安になったのか、的場さんは短く言ってまた跳んだ。踏みにじられて砕かれて、細かい涙の飛沫が舞って消える。
未練がましくまとわりついたノブヒコの道具袋は、大きな跳躍で遠く離れた的場さんの足を、弧を描くように離れた。勢いよく戻ってきて机の脚にぶつかった道具袋は、ガチャンと大きな音を立てた。その音はノブヒコの鼓膜をとうとう破いただけではとても足らず、その余りに乱暴な振動は、金属製の脚を伝って直接ガチャンと響くや灰色の脳を一気に溶かしてびしょびしょにした。
そんな頭蓋の空洞にクシャリと乾いた音がした。
「にんじんポリポリポリポリッ」
それなりに長い言葉を喋るとかすれた印象が少しずつなくなっていく。ノブヒコは、容姿とちぐはぐな、自分にしか聞こえていないようなその声が好きだった。でも、二度と同じようには聴くことができない。
「またまたピョンッ」
ウサギは遠くに行ってしまった。今度は自然にわき上がった拍手に送られて、恐竜が絶滅した。



